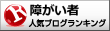今日から8月です

雨も降らず暑い毎日が続いていますが、
2日前の7月30日。
この日も洗濯物が山のようにあり、
利用者が到着する前に下準備をして、



爽介さんも到着後に手伝ってくれてます。
さあ!今日も大量の洗濯作業
と思っていると、9時前には津波注意報が発令されました!
注意報なら、と思い洗濯機・乾燥機をフル稼働して
体操終了後シーツを畳み始めると、なんと「津波警報」
に切り替わり発令されました

津波到達予想時刻は11時頃、3mの予測です。

沢尻海岸のすぐ近くにある地活では即座に作業を中断し、
急遽2台の車に分乗し山側の道を通って古民家に避難しました。



客船はもうすぐ接岸でしたが津波警報発令を受け
急遽引き返したようです。
よたね広場から桟橋~沖を見ると、さるびあ丸の姿は
ありませんでした。


福祉課職員も駆けつけてくれて、古民家に避難です。
保存食など災害用備品も運び込みました。

「古民家」は文字通り昔の作りで段差などもあり
障がいを抱えた方の移動には人手がいります。



冷房も入れて横になったり、それぞれ一休みです。
そして昼食
この日はスーパーの弁当を頼んでいた人以外に、
やすらぎの里の給食を頼んでいた人
地活の冷蔵庫に弁当を置いてある人がいましたが
地活に戻ることも出来ず
スーパーの弁当を購入して食べることになりました。





テーブルで食べる人、座位が取れず押入れを利用して車いす上で食べる人
色々でしたが、食べやすいように工夫して摂ることが出来ました。
自宅から通っている利用者には家族に引き取りに来てもらったり、
グループホームの方は避難先の生きがい健康センターに
送迎するなどの対応を取りました。
津波警報はその日の夕方には注意報に変わり
31日夕方にようやく注意報も解除されました。
今回は島内でも、日本においても大きな被害もなく済んだようですが、
神津に着く寸前で津波警報が発令され、引き返さなければならなかった方々、
神津での休日を過ごし東京へ帰ろうとしていた方々、私用・公用で
帰島・上京しようとしていた方々、
多くの方が大変な思いをされたことかと思います。
いつ大災害がくるかわかりません。
地活では普段から災害に備えマニュアルを作成し
様々な訓練に取り組んでいます。
南海トラフで想定される十数分後の津波到来の場合は
とにかく人命第一で高い場所への避難を最優先の訓練を行っていますが、
今回のように津波到来まで時間に余裕がある時は
また別の対応の必要性も感じました。
マニュアルは用意してあっても、
その時々の状況に応じて臨機応変に対応していく事が必要です。
今回の避難についても反省点・課題を分析し対策を講じ、
安心・安全に、少しでも落ち着いて対応し、利用者・職員の
命を守っていければと思います。
(記 鈴木)