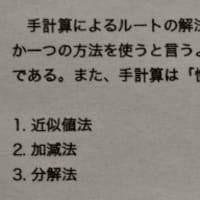<アメリカオニアザミは要注意外来生物>
この春、我が家のミニ・ロックガーデンの頂上付近に、アメリカオニアザミがロゼット広げているのを見つけた。昨夏遅くに風で運ばれた種子が着床、ロゼットを形成したのを見逃したのだ。忙しさに紛れて7月中旬まで放置していたところ、草丈が 60 ㌢まで伸び出蕾したので、溶接作業用の厚手の革手袋をはめてようやく引き抜いた。最近、街中の空き地で増殖し、生育域を拡大している。いったん生えると根絶が難しい厄介者なので、環境保全の面から市民に注意を喚起したい。
学名 Cirsium kamtchaticum
種名 チシマアザミ
分類 キク科アザミ属
日本では北海道にのみ分布、草地や明るい林内に自生する多年草。草丈1〜2メートルと大型で、茎上に多数の淡紅紫色筒状花から成る、径約4センチの頭花を下向きに1個つける。花冠の基部は7裂球状鐘形の総苞に包まれ、総苞片は披針形あるいは線径で後ろに反り返る。
学名 Cirsium vulgare
種名 アメリカオニアザミ(セイヨウオニアザミ)
分類 キク科アザミ属
ヨーロッパ原産の2年草で、畑地・牧草地・空き地・道端などに生育。日本には、北アメリカからの輸入穀物や牧草に混入して持ち込まれた。 1960 年代に北海道で初めて確認されて以後、日本各地に分布が広がっている。
分枝した茎の先に、紅紫色の多数の筒状花から成る、径3〜5センチの頭上花を上向きに1ないし数個つける。花冠の基部は球状に膨らむ大きな総苞に包まれる。植物体中に鋭い刺があり、茎に翼があることで、他のアザミ類と区別できる。在来種の生育を阻害するため、外来生物法によって「要注意外来生物」に指定されている。