5時半 お札は6時半から 寂しくなったな
何年か前はもう甘酒をいただく人で賑わって

出直して







懐かしい

今日は富士山が見えない

その次は 「出羽三山供養塚
市原には『羽黒神社、月山神社、湯殿神社』の石碑が頂に建立された塚は多い。
これは『出羽三山信仰』に基づく『供養塚』と言われ、『三山信仰』とは山形県
月山、羽黒山、湯殿山の出羽三山へのお詣りである。『供養塚』は、新行人(初めて三山を登拝した行人(ぎょうにん)三山を登拝した人)がお山で頂いた小さな木製の梵天(腰梵天、ぼっけなどと言う)を自分の身代わりとして葬儀を行ない、その梵天を埋葬する塚です。
私は仙台なので身近にお山に行った人のお話をよく聞いていた。遠くお山を眺めていて身近で有難いと感じていた。
市原市は、三山から遠隔の地でありながら強く信仰が根をおろした特異な地方とされており、市内全域に多くの供養塚が築かれており、姉崎地区にh12基の供養塚が作られています。神社にもある。

辰巳

菊間






次に島野・千種地域の延命寺です駐車場の関係で隣の鷲神社で停めて行く。
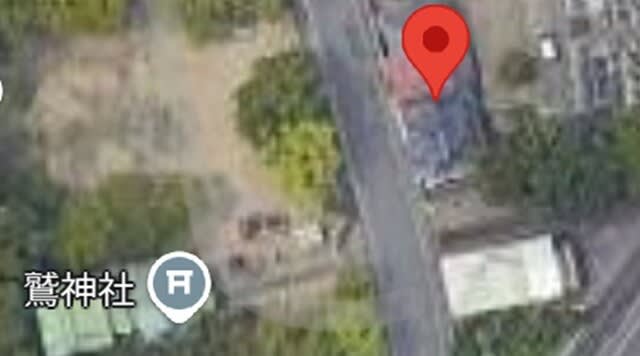
千葉県市原市の延命寺は、新義真言宗のお寺です。他に大厩古市などにも命寺がありますが、ここから奥州参り出発しました。ここで石造大日如来像を見学します。

鷲神社
隣の鷲神社に興味がわき覗いてみた
祭神の天日鷲命はお酉様として知られ、氏子は鳥を大切にし、鶏や鶏卵を食べない人もいたといいます。11月初酉の日から3日間が大祭で、境内に続く今津の宿通りでは酉の市が開かれ、東京からも商人が来て農具古器物などを売ったほか、味噌作りに適した今津産の塩も取引されました。境内には芝居小屋が設けられ、大勢の観客が押しかけて、近郷屈指の祭事として賑わいました。
御祭神
天日鷲命(あまのひわしのみこと)
御配祀 日本武尊(やまとたけるのみこと)
江戸時代以降、産業振興、商業繁栄の神として人々の崇敬最も篤く、十一月初酉日より三日間「酉の市」が開かれ近郊近在より、数多くの崇敬者が参詣し賑々しく例祭が斎行された。
五穀豊穣 家内安全 産業振興 商売繁盛
想像 賑わっただろうな。