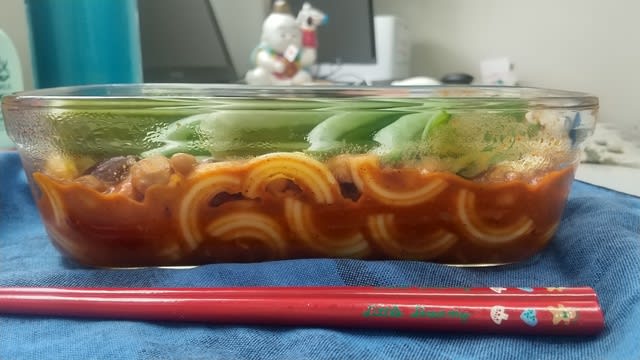先日のチェロの発表会で、ある門下生の一人がリハーサル室で缶酎ハイを飲んでいたので、ビックリしてしまいました。
彼女は昔なじみの生徒さんで、元気で明るい印象の方ですが、ちょっとそそっかしいところがあり、過去にも発表会当日に楽譜を忘れてきてしまったなんていうことがありました。
ひきつった笑いを浮かべながら、「安定剤よ~」と言ってお酒をグビグビ飲んでいたので、緊張しやすい面もあるのでしょう。
だからといって、お酒を心の安定剤として利用するのはよくありません。
「ぐっすり眠るため」と言って、寝酒を習慣にしている人を時折みかけますが、お酒は抗不安薬でも睡眠薬でもありません。
そういう間違った認識でお酒を飲んでいると、アルコール依存症に発展する危険性があります。
そういえば彼女は喫煙者でもありました。
ある研究では、過剰な飲酒、喫煙、アルコール依存症、ニコチン依存症、起床してから最初に喫煙するまでの時間は相互に関連しており、早死にしやすい要因であることが示されました。
(18~64歳のドイツ北部在住の一般集団よりランダムに抽出された人たちを対象にした研究)
この研究では、アルコール依存症歴のある人の約3割は、現在タバコも吸っていました。
アルコール依存症歴があり、現在起床してから30分以内に最初の喫煙を行う人は、アルコール消費量の少ない非喫煙者と比較し、5.28倍も早期死亡しやすいことも示されています。
なるべく長く健康な状態で人生を全うするには、タバコを吸わず、お酒はほどほどにしておいたほうがいいことは明らかです。