穂村と塚本の類似
戦後、前衛短歌で登場した塚本邦雄と現代の歌人、穂村弘。その時代背景をはぎ取り、歌意の本質や構造面で特定の二首を重ねて透かし見てみると、ある類似性が見えてくる。
サバンナの象のうんこよ聞いてくれだるいせつないこわいさみしい
穂村弘『シンジケート』
日本脱出したし 皇帝ペンギンも皇帝ペンギン飼育係りも
塚本邦雄『日本人霊歌』
両者の著名な歌を挙げてみた。現代から遡って見通したいので穂村作品を先に置く。穂村の歌は「自己のやるせない気持ちを聞いてくれるのは遠いサバンナに落ちている象の糞くらいしかないのだ」という若者のやり場のない孤独の叫びである。「聞いてくれ」は哀願で、しかもその相手は人ではなくただの象の糞なのだ。下の句の形容詞の連続は一見くどくて流し読みしそうになるが、これぐらい重ねないことにはやるせない孤独と焦燥感は表せ得ない。
一方、塚本の「皇帝ペンギン」は天皇という説が多いが、戦後の日本の状況へのアイロニーともされている。天皇も国民も日本から逃れ出たいという望みは強いけれども、でもやはり行き場はどこにもなく、逃げ出すのはどうしようもなく不可能だ。
両者の本質は非常に似かよっている。時代やその背景からすればもとより異質だ。しかし、その底辺から沁み出てくるもの、あるいは奥に隠れているものを抽出しようとするとき、私は両者を貫くある共通性を思ってしまう。それは「切迫感」「逃避」「焦り」「苛立ち」、そして「諦め」であり、それらから導き出された魂の叫びである。望んでも結局どこにも行けず、思いを遂げられないやるせない叫びの本質は同じであり、時空を越えて読むものの心を打つ。もう何組か見てみよう。
夜明け前 誰も守らぬ信号が海の手前で瞬いている
穂村弘『手紙魔まみ、夏の引っ越し(ウサギ連れ)』
海底に夜ごとしづかに溶けゐつつあらむ。航空母艦も火夫も
塚本邦雄『水葬物語』
夜明け前の町の空気と海底の静寂、信号と航空母艦、そして火夫が、読後しばらく心のなかに揺らぎ続ける。信号も母艦も火夫も、誰にも見られていないし何の役にも立っていない。またたく光、海に溶け続けてゆく鉄、肉体…静かな景のなかに取り残され、人知れず無意味に存続し続けるものへの淡き思いが共通している。
いつかみたうなぎ屋の甕のたれなどを、永遠的なものの例として
穂村弘『手紙魔まみ、夏の引っ越し(ウサギ連れ)』
ダマスクス生れの火夫がひと夜ねてかへる港の百合科植物
塚本邦雄『水葬物語』
たれの甕、百合科植物…なんでもない物なのに、あとでなぜか思い返すような事物がある。二つの語は全くの別物だが、それらの持つ詩的な機能や色合いはしっとりと印象深く、その本質は非常に似通っている。
殺虫剤ばんばん浴びて死んだから魂の引取り手がないの
穂村弘『手紙魔まみ、夏の引っ越し(ウサギ連れ)』
少女死するまで炎天の繩跳びのみづからの圓驅けぬけられぬ
塚本邦雄『日本人靈歌』
落ち着ける場所が永遠に無い不安、未来の見えない運命の呪縛…二首を続けて読めば、魂の引き取り手のないゴキブリと少女の行く末を遮る繩の暗示が、共通のイメージとして強く重なりはしないか。
いずれの組も本質的にかなりの共通性を感じてしまう。違うのは新旧の大きな時間の開きだけだ。突飛な比較かもしれない、いささかこじつけめいているかもしれない。だが、それでもやはり私は現代の歌のなかに戦後の前衛短歌の遺伝子が今の時代にしっかりと脈打っているのを直感的に見た思いがする。
穂村は塚本邦雄や春日井建らの前衛作品が短歌との始めの出会いだったと語っている。どこまでも想像であるが、穂村は塚本の歌を血肉とするためにもこれらの歌を自己を通過させて今に蘇らせてみたのではないだろうかとまで思ってしまうのだ。
前衛第二世代の歌
塚本邦雄、岡井隆、寺山修司から始まり現代短歌に多大な影響を与えた前衛短歌運動であるが、とりわけ、多感な青年期にリアルタイムで前衛に出会った、今の七十歳前後の世代(塚本からすれば「子世代」つまり第二世代にあたる)の衝撃は相当に凄かったことだろう。
伊藤一彦は自著エッセイ集『月光の涅槃』のなかで若き日に出会った塚本邦雄に触れ、《学生時代に作歌をはじめて間もなく出会った塚本邦雄作品は衝撃だった。その前に寺山修司を読んでひきつけられていたが、彼の作品は愛誦していればよかった。だが塚本作品はそうではなかった》として彼のいくつかの作品に触れ、《塚本邦雄さんに読んでもらえる作品をと思って私はずっと作歌してきたように思う。だから、塚本さんに評論や手紙の中で批評の言葉をもらえた時は大いに励まされた。同時代に心から敬うことのできる歌人を持ち得た幸福を思う。》と結んでいる。同様の思いを持つ同世代の歌人は多い。
もろびとに青春一過さらさらにうねれる水の上の稲妻
伊藤一彦『火の橘』
君去りしけざむい朝 挽く豆のキリマンジャロに死すべくもなく
福島泰樹『転調哀傷歌』
湖にふりくらみつつたゆたえるひとりのこころ一漕の舟
三枝昂之『水の覇権』
母狩の山に雪降り母狩を見つつ老いゆく村の嫗は
小高賢『耳の伝説』
真昼間に感電死する工夫あれ かの汗の塩をも吾は愛さむ
大島史洋『藍を走るべし』
昭和十八年前後生まれの歌人で、前衛の影響を感じた歌を初期の歌集に探してみた。一首目、川の上に見た雷を見ての視野広き感慨。二句切れ、言葉の律動感は塚本的な前衛手法を意識したように見える。二首目、女に去られたひとりの朝の哀しみ、コーヒー豆の名からその場所へと飛躍する嘆き節的な流れがいい。三首目、実景ではなく景のイメージに徹した。不安と希望を重ねたような綯い交ぜな思いが伝わってくる。四首目、これも実景ではなく姨捨の伝説に思いを託した寓意的な構図の妙。五首目、工夫、感電死、そして下の句の着地はいかにも塚本風である。
視点、題材、寓意、抽象的表現その他のレトリック等、いずれも前衛の影響なしには生まれ出なかった表現手法だ。現在の個々の作風と明らかに違うのが興味深い。
前衛第三世代の歌
もちろん「前衛第三世代」などという呼称は無い。本論考での便宜上のことだ。私は昭和三十六年生まれ、穂村と同世代である。塚本からすれば第三世代、つまり「孫」となる。 第二世代と比べて、前衛との出会いはそれほどには衝撃的ではない。なぜなら、前衛を消化して表現した歌人の歌との出会いが短歌に接した最初だからだ。
個人的な思いだが、私は前衛短歌に出会ったとき、これのどこが「前衛」なのだろう?と思った。前衛とは、そもそも難解でおどろおどろしく、常軌を脱した奇抜な表現や理解しがたいものの総称なのではないのか。このような「ノーマル」をなぜに前衛と呼んだのかが不思議だった。後に、当時は「難解派」とか「シュール」とか様々に呼ばれていたらしいことを知り、従来と際だって毛色が違うという総称として呼び慣わされたものであることを理解した。
塚本の孫世代でその影響を色濃く受けた歌人は、先の穂村の他、加藤治郎、坂井修一、東直子等が挙げられる。
砕けてもぼくの体がわかるなら母よまっ青な絵具のチューブ
加藤治郎『サニー・サイド・アップ』
にぎやかに釜飯の鶏ゑゑゑゑゑゑゑゑゑひどい戦争だった
〃 『ハレアカラ』
工学も思へばなべて一行のボードレールにしかず、さりとて……
坂井修一『ラビュリントス』
WWWのかなたぐんぐん朝はきて無量大数の脳が脳呼ぶ
〃 『スピリチュアル』
そうですかきれいでしたかわたくしは小鳥を売ってくらしています
東直子『春原さんのリコーダー』
特急券を落としたのです(お荷物は?)ブリキで焼いたカステイラです
〃 『春原さんのリコーダー』
一首目、結句に無関係な事物をぶつけて一首の意を故意に混乱させている。二首目、「ゑ」の視覚的不気味さ。時事詠ともとれる。三首目、専門のコンピュータ工学への詩的な視点を著名な詩人の名に込めた。四首目、インターネットをどううたうかへの実験作。五首目、話の前後のよくわからないふわふわ感が心地よい。六首目、不思議な会話の飛躍のリズムとパーレンが効いている。
岡井隆から受け継いだ前衛精神を我が物とし、口語短歌への明確な使命を持ち今を疾走する加藤。塚本さながらに歴史上の人物を登場させたり、コンピュータの世界を独自に描く坂井…。物語的なほのかな余情世界を大切に守り続ける東。いずれも前衛的な感覚を巧みに現代に盛り込んでいる。
これらの歌を私はしっかり理解できるかと問われれば、明確にイエスとは答え難い。しかし極端な難解性や違和感は感じない。少なくとも情景や伝えたいものはわかるし、何よりも拒否感や抵抗感がない。それは知らずしらずの間に前衛の世界をことさら意識せず消化してきたからだ。塚本と穂村の間にいる様々なスタイルの無数の歌人たちが前衛と出会い、影響を受け作ってきた歌を、私は入門書として読んできたからだ。前衛は当初から私たち「孫」の前に用意されていたカリキュラムだったのだ。
第四世代のわからない歌
さて、戦後七十年ともなれば第三世代でさえももはや壮年期である。そうなると当然、第四世代、つまり「塚本の曾孫世代」がすでに活躍し始めている。
「水菜買いにきた」/三時間高速を飛ばしてこのへやに/みずな/かいに。
今橋愛『O脚の膝』
痣売りや石並べ屋が繁盛する火星がなつかしいね くわがた
雪舟えま『たんぽるぽる』
婦人用トイレ表示がきらいきらいあたしはケンカつよいつよい
飯田有子『林檎貫通式』
たすけて枝毛姉さんたすけて西川毛布のタグたすけて夜中になで回す顔
〃
あの青い電車にもしもぶつかればはね飛ばされたりするんだろうな
永井祐『日本のなかで楽しく暮らす』
作者の実年齢は無視し、あくまで第四世代的な歌としてあげてみた。共通して感じるのは「わからない」だ。もちろんわからないとされる歌は先の前衛短歌にも多く存在する。ただ、その質が前の第一~三世代と何か本質的に違う。
一首目、美味な水菜への執着心だろうか。「このへやに」と結句の「かいに」が話を難解にさせている。不思議なリズムの四行書きだ。二首目、いきなりの不可思議な商売、そして火星という突飛な場所へ飛ばされ、事態を把握しきれないままに、最後の「くわがた」でさらに遠くへ飛ばされてしまう。三首目、世界への拒絶と虚栄だろうか。かつてなかった独特な口語の調べである。四首目、最後まで全くの謎のままであるが、とにかく超特大級な「ヘルプ!」であることだけはわかる。五首目、ただの呟きのようでいて、何か残るものがある。どうにも軽く読み飛ばせないのは、したたかな定型の力を備えているからだろうか。
言葉の意味を探ろうとしても情景の形容へ切り込んでいっても無駄である。評する角度を変えて「なにを伝えたいのか」を恐る恐る踏み込んでゆくしかなく、最後にはそれでも強く弾かれてしまう危険もある。
基本的に多くを説明しようとしない。どれもがまるでツイッターに書き込まれた呟きのようだ。声量が少なく、口数少なく、なにかモノローグのように思える。ストレートにみせかけつつ周到に迂遠な表現をとる。ただし、詩的な感慨や残香的な印象の強さは従来の歌同様しっかりと機能している。決して奇異を衒って目立とうとしているのではない。定型からの逸脱加減も、いかにも前衛的である。
また、どうか分かって欲しい、届いて欲しいというような、歌を作るものが持っているはずの期待や願いが始めから枯れている。時代性や思想性は弱い。そしてその分、私性はかなり強い。読み手としては全身でその一首を体感的に受け止め、モヤモヤ感を未消化なまま転がし続け、その感覚のどこかに「理解」の足がかりを探り続けるしかない。
これらの歌を冒頭のように塚本の歌と重ね合わせて透かして見ることができるかどうか試みたが、どの歌も全くの徒労に終わった。類型が無いのだ。車で言えばパーツや設計思想が根幹的に違うし、なにより規格そのものが異質である。第一~三世代はなんとか同一規格の物差しで比較できるのだが、この「曾孫世代」はそれが不可能なのだ。
第三世代目あたりから言われてきた「微視的観念の小世界」や「大きな物語の終焉」とかでは説明しきれない新たな世界が広がっている。穂村は「棒立ちのポエジー」「歌の武装解除」と呼び、言い得て妙であるが、それでもとらえ切れない新たな感覚世界が広がりつつある。
おわりに
前衛短歌の現代までの流れを四つの世代に分け、第四世代の最前線の「わからない歌」を考察してみた。戦後からそれぞれの時代の風にはためきつつ七十年近く受け継がれてきた前衛短歌の遺伝子は、その名称こそ表に出てこないが、姿や質を変えて現代に脈々と受け継がれている。前衛短歌は歌の表現の幅を根定から大きく広げてくれた。短歌千四百年の伝統の最後尾に加わったその可能性への多岐な試みの集積が現代短歌であるとも言える。
現在、第四世代たちは先代たちが編み出した前衛という「奇策」を完全に消化し、奇策でもなんでもないものとしてごくさりげなく発信し始めている。この点、何十年も時を経た今だからこそ言えるわけだが、第三世代まではまださりげなさがなく、「どうだ!」という前衛取り込み的なポーズが歌のそこここに残存している。
しかし、第四世代にはそうしたポーズが全くない。自然な着こなし術を我が物とした彼らは「わからない」という意味を問いながら、どこまでも不思議なムードを漂わせつつ今後の現代短歌にその存在感をさらに強めていく予感がしてならない。
(2015現代短歌評論賞候補作)
=======================










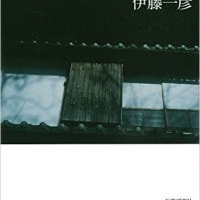
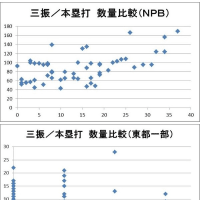






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます