「短歌研究」十月号、「2022現代短歌評論賞」を読む。受賞は桑原憂太朗「口語短歌による表現技法の進展~三つの様式化」、髙良真実「はじめに言葉ありき。よろずのもの、これに拠りて成る│短歌史における俗語革命の影」の二人。
今回の課題は「口語短歌の歴史的考察」「ジェンダーと短歌」「疫の時代の短歌」からの選択だったが、次席を含めてすべて口語の論考であった。他の候補作も口語に関するものがほとんどで、これだけでも口語への変わらぬ関心度を感じてしまう。
桑原はまず、現代口語短歌は「口語をいかにして定型になじませるか」の試行の連続であったと捉え、口語を旧来の韻詩へ「翻訳する意義」への疑問を挙げ、口語ならではの技法として「動詞の終止形」「終助詞」「モダリティ」を取り上げる。八十年代から現在の口語短歌の変遷を論考し「韻詩ならではの韻律や調べに目を瞑った」姿勢から「ざっくりとした定型意識」、そして「口語をなんとかして韻詩へ変換しよう」と現代短歌の新しい道への進化を述べ、過去完了助動詞の「た」や「る」の終止形についても考察する。
そして「終助詞の活用」として、加藤治郎の「マガジンをまるめて歩くいい日だぜ ときおりぽんと股で鳴らして」「たぶん口をとがらせてるね だまったきりひとさし指をまわしてね、ふん」の「ぜ」や「ね」等へ着目し、これらを「主体の性別や性格のキャラクターづけ」や「主体との関係性」まで表されるとして「口語ならではの豊かな表現を可能にした」と述べる。
興味深かったのは「モダリティの活用」という考察だ。モダリティとは、他者への発話の際の文末処理であり「カレーが食べたい」を独り言にした場合の「カレーにするか」「カレーでも食べるか」の「か」や「でも」を「モダリティ」と呼ぶのだという。つまり「お名前何とおっしゃいましたっけと言われ斉藤としては斉藤とする」という斉藤斎藤の歌では「っけ」で「敬語を使うような間柄なのにひどくぞんざいに扱われている主体の立場がこのモダリティによって分かる」と言うのである。
発話の語尾を「モダリティ」なる聞き慣れない語で切り込んだのが個性的で斬新だ。「口語は文語と比べてここが弱い」ではなく「口語は文語と比べてこんなことができる」という立ち位置がいい。口語の持つ特性の一つひとつをさらに細かく捉え直してみようという試みでもあろう。
もうひとつの受賞作、髙良の評論は、いわゆる「言文一致体」としての口語は現実の「発話」そのものではない、として発話体の試みで一定の評価を得ている千種創一の「永遠に会話体には追いつけないけれど口語は神々の亀」の歌意を読み解き、「話し言葉的な口語」は「あくまで発話の再現にすぎず、発話そのものではない」として、永井祐、松村正直等の言を引き、そこに横たわる問題点をじわりと紐解いていく。
興味を惹かれたのは、与謝野晶子が与謝野鉄幹の歌に「これなら自分にも作れそう」と感じたというエピソードを挙げ、これは現代人の多くが俵万智の歌に抱いた思いと同様ではないかという発見だ。晶子が鉄幹の歌に感じたのはいわゆる親近感的な感覚だろう。それは今で言う口語の特性に似ており、現代人が「サラダ記念日」の俵の歌に感じたことと似ているということだ。
続いて、明治期の言文一致運動、齋藤茂吉の反口語の姿勢、さらには口語短歌が社会に受け入れられた時期とテレビで育った世代が社会的に活躍するようになった時期の同期性への言及と、論点を自在に絡めつつ広げてゆく。
結論へのプロセスがやや集約されてない感じがしたが、幅広い資料を配置しつつの力強い書き方が評価されたのだろう。
両者とも、口語の持つ側面がより深く追求されていて読み応えあるものだった。「文語と口語」は現代短歌がずっと課せられている話題だが、つまりは自己の思いを、自分が一番使いこなせる言葉で自由にうたいたいというのが原初の思いであろう。
私は俵万智の遥か後方から、同じく文語混じりの口語で出発したのだが、文語助動詞を「文語からの借り物」と思ったことは一度も無い。古くからある時制の使い分けの表現を、過去形が「た」しかない口語世界にすんなり持ってきて活用しているまでのことで、違和感は全くない。言葉であれ色鉛筆であれ十二色セットより二十四色セットの方が微妙な色をたくさん出せるに決まっているではないか。また、ことさらに口語と文語を対立軸と捉えるのもどうなのだろう。もう「短歌語」で良いのではないかとさえ思ってしまう。
しかし、最前線の口語ネイティブ世代にはこうした感覚こそがナンセンスなのだ。ミックス口語の世界に安住せず、正に自分が普段使う真の口語だけで、時制を含めたかつてない新たな表現世界を開拓できないかと日々、懸命に試行錯誤している。
アヴォガドをざつくりと削ぐ(朝の第一報の前のことである)
枯れ枝にはためく白い木蓮はずっと前からレジ袋だった
千種創一「砂丘律」
文語助動詞を使わぬ純粋な口語だけで微妙な時制を表すにはどうすればいいかという執念の試みの成果だと私は感じる。
口語短歌は飛行機の歴史に喩えれば、まだライト兄弟が飛んだ直後ぐらいではあるまいか。当時、その一週間前のニューヨークタイムスは社説に「飛行機の研究など時間と金の浪費だ」と書いたという。長期的に眺めれば、口語短歌は表現の可能性へ向けてまだ飛び立ったばかりなのだ。
今回の課題は「口語短歌の歴史的考察」「ジェンダーと短歌」「疫の時代の短歌」からの選択だったが、次席を含めてすべて口語の論考であった。他の候補作も口語に関するものがほとんどで、これだけでも口語への変わらぬ関心度を感じてしまう。
桑原はまず、現代口語短歌は「口語をいかにして定型になじませるか」の試行の連続であったと捉え、口語を旧来の韻詩へ「翻訳する意義」への疑問を挙げ、口語ならではの技法として「動詞の終止形」「終助詞」「モダリティ」を取り上げる。八十年代から現在の口語短歌の変遷を論考し「韻詩ならではの韻律や調べに目を瞑った」姿勢から「ざっくりとした定型意識」、そして「口語をなんとかして韻詩へ変換しよう」と現代短歌の新しい道への進化を述べ、過去完了助動詞の「た」や「る」の終止形についても考察する。
そして「終助詞の活用」として、加藤治郎の「マガジンをまるめて歩くいい日だぜ ときおりぽんと股で鳴らして」「たぶん口をとがらせてるね だまったきりひとさし指をまわしてね、ふん」の「ぜ」や「ね」等へ着目し、これらを「主体の性別や性格のキャラクターづけ」や「主体との関係性」まで表されるとして「口語ならではの豊かな表現を可能にした」と述べる。
興味深かったのは「モダリティの活用」という考察だ。モダリティとは、他者への発話の際の文末処理であり「カレーが食べたい」を独り言にした場合の「カレーにするか」「カレーでも食べるか」の「か」や「でも」を「モダリティ」と呼ぶのだという。つまり「お名前何とおっしゃいましたっけと言われ斉藤としては斉藤とする」という斉藤斎藤の歌では「っけ」で「敬語を使うような間柄なのにひどくぞんざいに扱われている主体の立場がこのモダリティによって分かる」と言うのである。
発話の語尾を「モダリティ」なる聞き慣れない語で切り込んだのが個性的で斬新だ。「口語は文語と比べてここが弱い」ではなく「口語は文語と比べてこんなことができる」という立ち位置がいい。口語の持つ特性の一つひとつをさらに細かく捉え直してみようという試みでもあろう。
もうひとつの受賞作、髙良の評論は、いわゆる「言文一致体」としての口語は現実の「発話」そのものではない、として発話体の試みで一定の評価を得ている千種創一の「永遠に会話体には追いつけないけれど口語は神々の亀」の歌意を読み解き、「話し言葉的な口語」は「あくまで発話の再現にすぎず、発話そのものではない」として、永井祐、松村正直等の言を引き、そこに横たわる問題点をじわりと紐解いていく。
興味を惹かれたのは、与謝野晶子が与謝野鉄幹の歌に「これなら自分にも作れそう」と感じたというエピソードを挙げ、これは現代人の多くが俵万智の歌に抱いた思いと同様ではないかという発見だ。晶子が鉄幹の歌に感じたのはいわゆる親近感的な感覚だろう。それは今で言う口語の特性に似ており、現代人が「サラダ記念日」の俵の歌に感じたことと似ているということだ。
続いて、明治期の言文一致運動、齋藤茂吉の反口語の姿勢、さらには口語短歌が社会に受け入れられた時期とテレビで育った世代が社会的に活躍するようになった時期の同期性への言及と、論点を自在に絡めつつ広げてゆく。
結論へのプロセスがやや集約されてない感じがしたが、幅広い資料を配置しつつの力強い書き方が評価されたのだろう。
両者とも、口語の持つ側面がより深く追求されていて読み応えあるものだった。「文語と口語」は現代短歌がずっと課せられている話題だが、つまりは自己の思いを、自分が一番使いこなせる言葉で自由にうたいたいというのが原初の思いであろう。
私は俵万智の遥か後方から、同じく文語混じりの口語で出発したのだが、文語助動詞を「文語からの借り物」と思ったことは一度も無い。古くからある時制の使い分けの表現を、過去形が「た」しかない口語世界にすんなり持ってきて活用しているまでのことで、違和感は全くない。言葉であれ色鉛筆であれ十二色セットより二十四色セットの方が微妙な色をたくさん出せるに決まっているではないか。また、ことさらに口語と文語を対立軸と捉えるのもどうなのだろう。もう「短歌語」で良いのではないかとさえ思ってしまう。
しかし、最前線の口語ネイティブ世代にはこうした感覚こそがナンセンスなのだ。ミックス口語の世界に安住せず、正に自分が普段使う真の口語だけで、時制を含めたかつてない新たな表現世界を開拓できないかと日々、懸命に試行錯誤している。
アヴォガドをざつくりと削ぐ(朝の第一報の前のことである)
枯れ枝にはためく白い木蓮はずっと前からレジ袋だった
千種創一「砂丘律」
文語助動詞を使わぬ純粋な口語だけで微妙な時制を表すにはどうすればいいかという執念の試みの成果だと私は感じる。
口語短歌は飛行機の歴史に喩えれば、まだライト兄弟が飛んだ直後ぐらいではあるまいか。当時、その一週間前のニューヨークタイムスは社説に「飛行機の研究など時間と金の浪費だ」と書いたという。長期的に眺めれば、口語短歌は表現の可能性へ向けてまだ飛び立ったばかりなのだ。










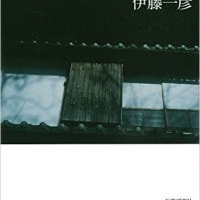
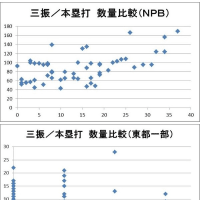






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます