『短歌研究』二〇二二年七月号・八月号の鯨井可菜子「短歌時評」を読む。同五月号「三〇〇人歌人新作作品集」において、ウクライナの首都名「キエフ」が、新しい呼称である「キーウ」にすべて変更されていたのだという。同八月号「「いち早く」の先に―もう一度「キーウ」について考える」から引用する。
原稿提出後に受けた連絡によると、もともと同特集に存在していた「キエフ」の語は、「編集部より作者の皆さんにお願いして了解いただいた上で」、校了の数日前に「キーウ」に変更されていたのだという(注1/三月二十日締切の同特集では、七月号で取り上げた澤村斉美作品以外はすべて「キエフ」だったとのことである。)。
編集長の國兼氏は、「日本政府の呼称変更の流れを汲んでのこと」で強く変更を迫ったわけではないとしつつ、「4月の情勢のなかで編集部から依頼があったなら「キーウ」への変更を断るということはできなかったかもしれませんと推測する(以上、カギカッコ内は五月二十日付メールを引用)。
まずは「えっ、これ、いいの?」と驚くのが自然だろう。しかしながら、流れを冷静に考えるうちに、少し思いが変わった。歌に使った言葉への干渉という側面は確かにあるものの、国際紛争という社会的な事情を汲んだ流動的なケースだし、何よりも決して勝手に変更したわけではないという編集部の思慮を強く感じるからだ。
ただ、他の対処としては、「キエフ」の歌稿はすべてそのまま掲載し、「編集部より」として「締切という編集上の諸事情のため元原稿の「キエフ」のままにした」と紙面のどこかに述べ置く手もあったのでは?と考えてしまった。呼称変更への対応が少しぐらい遅れても日本政府や社会はそこまで文句は言わないだろう。
もし私だったらどう応じただろうか。ちょっと戸惑いつつも、最後には「まぁ仕方ないか」と静かに承諾しただろうと思う。ただ、歌を創る者として、自分が選び取り表現した言葉が、何か抗いがたい大きな力でもって変えられるという事態はやはりどこか怖ろしい。当の歌人たちも同様に感じ取ったに違いない。
鯨井も「私自身、歌に読み込む言葉は、それまでに獲得して沈積していた言葉が〈自分の中から〉出てきたものだと思っている。「キエフ」と「キーウ」、音数は共に三音で、終わりの「フ」と「ウ」も同じウ段の響きであるが、それでもこの微差は、一首の韻律を左右する。定型の辻褄が合ったとしても、これは全く違う言葉なのである。」と述べている。
全く同感である。先の歌人たちは、「キエフ」の歌稿を送った時点では「キーウ」はまだ獲得も沈積もできていない言葉である。突然に降りてきた新語を後で端的にあてがわれても困ってしまう。音数が同じでよかったなどという悠長な思いにはまずなれない。
・妻を得てユトレヒトに今は住むといふユトレヒトにも雨降るらむか(大西民子)
・ひまはりのアンダルシアはとほけれどとほけれどアンダルシアのひまはり(永井陽子)
原稿提出後に受けた連絡によると、もともと同特集に存在していた「キエフ」の語は、「編集部より作者の皆さんにお願いして了解いただいた上で」、校了の数日前に「キーウ」に変更されていたのだという(注1/三月二十日締切の同特集では、七月号で取り上げた澤村斉美作品以外はすべて「キエフ」だったとのことである。)。
編集長の國兼氏は、「日本政府の呼称変更の流れを汲んでのこと」で強く変更を迫ったわけではないとしつつ、「4月の情勢のなかで編集部から依頼があったなら「キーウ」への変更を断るということはできなかったかもしれませんと推測する(以上、カギカッコ内は五月二十日付メールを引用)。
まずは「えっ、これ、いいの?」と驚くのが自然だろう。しかしながら、流れを冷静に考えるうちに、少し思いが変わった。歌に使った言葉への干渉という側面は確かにあるものの、国際紛争という社会的な事情を汲んだ流動的なケースだし、何よりも決して勝手に変更したわけではないという編集部の思慮を強く感じるからだ。
ただ、他の対処としては、「キエフ」の歌稿はすべてそのまま掲載し、「編集部より」として「締切という編集上の諸事情のため元原稿の「キエフ」のままにした」と紙面のどこかに述べ置く手もあったのでは?と考えてしまった。呼称変更への対応が少しぐらい遅れても日本政府や社会はそこまで文句は言わないだろう。
もし私だったらどう応じただろうか。ちょっと戸惑いつつも、最後には「まぁ仕方ないか」と静かに承諾しただろうと思う。ただ、歌を創る者として、自分が選び取り表現した言葉が、何か抗いがたい大きな力でもって変えられるという事態はやはりどこか怖ろしい。当の歌人たちも同様に感じ取ったに違いない。
鯨井も「私自身、歌に読み込む言葉は、それまでに獲得して沈積していた言葉が〈自分の中から〉出てきたものだと思っている。「キエフ」と「キーウ」、音数は共に三音で、終わりの「フ」と「ウ」も同じウ段の響きであるが、それでもこの微差は、一首の韻律を左右する。定型の辻褄が合ったとしても、これは全く違う言葉なのである。」と述べている。
全く同感である。先の歌人たちは、「キエフ」の歌稿を送った時点では「キーウ」はまだ獲得も沈積もできていない言葉である。突然に降りてきた新語を後で端的にあてがわれても困ってしまう。音数が同じでよかったなどという悠長な思いにはまずなれない。
・妻を得てユトレヒトに今は住むといふユトレヒトにも雨降るらむか(大西民子)
・ひまはりのアンダルシアはとほけれどとほけれどアンダルシアのひまはり(永井陽子)
音読するとさらに実感できるのだが、いずれも地名がとても印象的に響いてくる。ユトレヒトはオランダの都市。元の語にはもちろんそんな意味はないのだが短歌的には「ゆとり」や「人」という日本語が無意識のうちにどこかで淡く明滅する。アンダルシアはスペインの自治州。リフレインが調べの愛唱性をさらに増幅させている。既に完成され評価を受けているから、この先なにが起きても変わることはないが、これらに置き換わる地名は考えられない。「紫陽花、あじさい、アジサイ」「陽射し、日射し、日差し」「広島、ヒロシマ、Hiroshima」等、これらはそれぞれ別の言葉だ。伝えるものが違い、背負うイメージも違う。歌人はこれらを明確に使い分ける。事情はかなり異なるが「キエフ、キーウ」も似て非なるものだ。
この一件を機に「自己の歌の言葉を変えられる」状況について少し考えてみた。まずは「校正」が浮かぶ。これは誤字脱字や文法ミス等の基本的なチェック、訂正であり、結果が正しければ文句を言う立場にはない。主に編集者の仕事である。また「添削」というのもある。これは表現や言葉が、教える師によって時に大きく変えられてしまう。だから根底に双方の強い信頼関係がしっかり築かれてないとうまく成立しない。
今回の件に一番近いイメージは「校閲」ではないだろうか。校閲とは、例えば小説家が「その店は〇〇駅から歩いて五分のところにある」と書くとする。編集者は「あの店は駅から五分ではちょっと行けないですよ、実際、歩いてみましたが、十分でもぎりぎりでした」と細かな検証のやりとりをしながら正しい内容に変更する作業である。間違っているからといって勝手に変えるのではないし、小説家としては助手的な存在としてむしろありがたい関係である。今回の件と明確に違ったのは、こうした検討や考察のクッション的な余地がない言葉だったことだ。かなり特殊な状況下であったことを改めて思う。
ちなみに我がパソコンにはATOK(漢字変換ソフト)が入っていて、言葉の最新データがインターネットで更新される。試しに「キエフ」と入力すると「《地名変更「→キーウ」》」との情報を教えられ、そこから先は使用者の判断で確定となる。
「短歌往来」2022年10月号「評論月評/第一回」に加筆訂正。
【記事一覧へ】
【たけじゅんWeb】
「短歌往来」2022年10月号「評論月評/第一回」に加筆訂正。
【記事一覧へ】
【たけじゅんWeb】










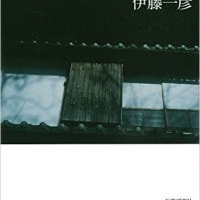
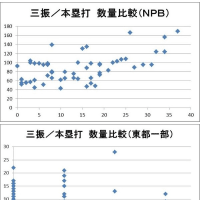






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます