「朝日歌壇ライブラリ」がネット上に公開されている。一九九五年五月から二〇二二年六月までの約五万首の作品が収められていて、言葉や作者名等で検索できる。試しに「マスク」で検索すると二二三件。コロナ禍としての「マスク」の初出は二〇二〇年二月。
・疑へばすべて罹患者(りかんしゃ)バスの中マスクがマスクを監視している(牛島正行)
この三首手前には、
・くまもんのマスクをつけてくしゃみする女性の座る春の地下鉄(夏目たかし)
と二〇一八年の歌があり、マスクが今のコロナ禍のような強い意味を背負っていないマスクのシーンを思った。
外出は眉だけ描いてマスクして 女半分捨てて爽快(片伯部りつ子)
頭から現在のコロナ禍の歌と思ってしまうが二〇一六年、これもコロナ禍以前のものだ。それを知って読み直すと本来の歌意が見えてくる。私たちは、マスクが普通にマスクであったこんな時代にはもう戻れない。
「スマートフォン」の初出は二〇一一年で、「スマホ」の初出が二〇一三年。略称がやがて抵抗感の無い言葉として受け入れられるまで二年ほどかかったのが想像できる。ちなみに「ケータイ」の初出は一九九七年で、最後の登場は今のところ二〇二二年四月だ。「携帯電話」が「携帯」、そして「ケータイ」と変わっていった年月を思う。
ひととき流行った「インスタ映え」の初出は二〇一七年。
インスタ映えするかどうかで新 メニュー決める店舗に行列できる (こやまはつみ)
いまや「それこそが目的じゃないか」と言えそうだが、当初はこれが発見そのものであった。現在では逆に「インスタ映え」しないリアルで自然な写真の方にトレンドが向いているという。言葉は変化し、進化し、消滅し、そしてときに深化する。
言葉で歌を抽出できるわけだから、題詠の際の作歌のヒントとしても活用できる。また、作者名でも検索できる。試しに「郷隼人」「美帆シボ」「公田耕一」等、かつて朝日歌壇で話題になった名を思いつくままに入れてみた。一人の作品を時系列でまとめて読め、新聞で朝日歌壇を読むときとはまた違った愉しみ方ができる。
いつの日か、こうしたデータベースが数多の歌集たちのスケールで実現すれば…と夢想する。やがてビッグデータとなれば、一つの言葉に対する歌人ごとの感覚の差異や「誰々の歌には〇〇という言葉が実はけっこう登場する」「真逆同士の歌人にあった共通性」等、これまで人の頭脳だけでは発見できなかった傾向や関連性が見えてくるだろう。
短歌は老若男女を問わず、歌われる世界が幅広い大衆の文芸である。何よりも作品サイズがコンパクトでかつ大量に流通しているため、数多くの作品を集めてビッグデータ的な手法で切り口を変え、多方面から自在に分析していけば世俗、政治、暮らし、社会問題、時代性等、様々な新しい側面が浮き出てくるはずだ。事象の記録や詳細はマスコミに任せておけばいい。我々は短歌という文芸を記録し、深く子細に考察してゆかねばならない。
また、このライブラリは「イメージ」での曖昧な言葉のAI検索もできる。たとえば「うきうき」「大丈夫」等を入れれば、その言葉が入ってなくても、似たテイストを持つ様々な歌を引っ張り出してくれる。
八月十九日の朝日新聞に「俵万智×AI 恋の歌会」というイベントの記事があった。投げかけた上の句に対してAIが瞬時に下の句を付けて百首を返し、それを俵が評したり、添削したりしたという。
俵とライブラリ開発者である浦川研究員との対談が興味深い。イベントの応募者からの「AIは短歌を鑑賞、評価したりできるのか」の質問に、浦川は「これまでどんな短歌がどう評されたかというデータをたくさん学習することでAIが歌の善し悪しを判別することもできるのでは」と答え、俵は「カラオケで高得点を出す人の歌は確かにうまいけれど、音が外れていても人を感動させる歌もある。AIにジャッジさせることで私たちは何を名歌と思うかということも試される気がする」と述べる。
私はいずれ「音が外れていても人を感動させる歌」の中にある極めて繊細な部分さえをもAIは学習していくだろうと思う。スタジオで広告モデルの撮影をする時、スタイリストは服装の最終チェックの際、自然に見えるようなシワをほんの少し故意に入れたりするのだが、この「シワ入れ」的な部分の研究開発こそがこれからのAIの課題であり、面目躍如ではないか。
俵は「短歌を作るのはAIができないことの最後のひとつであってほしい、それだけは人間の最後の砦だと思っていたが、AIに接して考えることは人間や短歌の本質を考えることにつながると感じた」と続ける。
私は将来の究極のAIは、この最後の砦の部分は、頭の悪い我々人間のために「しょうがないな…」と故意に残しておいてくれるのではないかとも考えたりしている。
「作者/AI」の歌集が出る日は案外近いのではないか。その歌を従来の歌集と同等に鑑賞すれば、今の優れた歌集を読むときと同じ感動が起きるはずだ。
だがしかし、その背後から立ち昇ってくるはずの「我」とはいったい何だろう?。「私性とAI」がっぷり四つの、短歌史上かつて無かった大きな難問が我々を待ち構えている。
・疑へばすべて罹患者(りかんしゃ)バスの中マスクがマスクを監視している(牛島正行)
この三首手前には、
・くまもんのマスクをつけてくしゃみする女性の座る春の地下鉄(夏目たかし)
と二〇一八年の歌があり、マスクが今のコロナ禍のような強い意味を背負っていないマスクのシーンを思った。
外出は眉だけ描いてマスクして 女半分捨てて爽快(片伯部りつ子)
頭から現在のコロナ禍の歌と思ってしまうが二〇一六年、これもコロナ禍以前のものだ。それを知って読み直すと本来の歌意が見えてくる。私たちは、マスクが普通にマスクであったこんな時代にはもう戻れない。
「スマートフォン」の初出は二〇一一年で、「スマホ」の初出が二〇一三年。略称がやがて抵抗感の無い言葉として受け入れられるまで二年ほどかかったのが想像できる。ちなみに「ケータイ」の初出は一九九七年で、最後の登場は今のところ二〇二二年四月だ。「携帯電話」が「携帯」、そして「ケータイ」と変わっていった年月を思う。
ひととき流行った「インスタ映え」の初出は二〇一七年。
インスタ映えするかどうかで新 メニュー決める店舗に行列できる (こやまはつみ)
いまや「それこそが目的じゃないか」と言えそうだが、当初はこれが発見そのものであった。現在では逆に「インスタ映え」しないリアルで自然な写真の方にトレンドが向いているという。言葉は変化し、進化し、消滅し、そしてときに深化する。
言葉で歌を抽出できるわけだから、題詠の際の作歌のヒントとしても活用できる。また、作者名でも検索できる。試しに「郷隼人」「美帆シボ」「公田耕一」等、かつて朝日歌壇で話題になった名を思いつくままに入れてみた。一人の作品を時系列でまとめて読め、新聞で朝日歌壇を読むときとはまた違った愉しみ方ができる。
いつの日か、こうしたデータベースが数多の歌集たちのスケールで実現すれば…と夢想する。やがてビッグデータとなれば、一つの言葉に対する歌人ごとの感覚の差異や「誰々の歌には〇〇という言葉が実はけっこう登場する」「真逆同士の歌人にあった共通性」等、これまで人の頭脳だけでは発見できなかった傾向や関連性が見えてくるだろう。
短歌は老若男女を問わず、歌われる世界が幅広い大衆の文芸である。何よりも作品サイズがコンパクトでかつ大量に流通しているため、数多くの作品を集めてビッグデータ的な手法で切り口を変え、多方面から自在に分析していけば世俗、政治、暮らし、社会問題、時代性等、様々な新しい側面が浮き出てくるはずだ。事象の記録や詳細はマスコミに任せておけばいい。我々は短歌という文芸を記録し、深く子細に考察してゆかねばならない。
また、このライブラリは「イメージ」での曖昧な言葉のAI検索もできる。たとえば「うきうき」「大丈夫」等を入れれば、その言葉が入ってなくても、似たテイストを持つ様々な歌を引っ張り出してくれる。
八月十九日の朝日新聞に「俵万智×AI 恋の歌会」というイベントの記事があった。投げかけた上の句に対してAIが瞬時に下の句を付けて百首を返し、それを俵が評したり、添削したりしたという。
俵とライブラリ開発者である浦川研究員との対談が興味深い。イベントの応募者からの「AIは短歌を鑑賞、評価したりできるのか」の質問に、浦川は「これまでどんな短歌がどう評されたかというデータをたくさん学習することでAIが歌の善し悪しを判別することもできるのでは」と答え、俵は「カラオケで高得点を出す人の歌は確かにうまいけれど、音が外れていても人を感動させる歌もある。AIにジャッジさせることで私たちは何を名歌と思うかということも試される気がする」と述べる。
私はいずれ「音が外れていても人を感動させる歌」の中にある極めて繊細な部分さえをもAIは学習していくだろうと思う。スタジオで広告モデルの撮影をする時、スタイリストは服装の最終チェックの際、自然に見えるようなシワをほんの少し故意に入れたりするのだが、この「シワ入れ」的な部分の研究開発こそがこれからのAIの課題であり、面目躍如ではないか。
俵は「短歌を作るのはAIができないことの最後のひとつであってほしい、それだけは人間の最後の砦だと思っていたが、AIに接して考えることは人間や短歌の本質を考えることにつながると感じた」と続ける。
私は将来の究極のAIは、この最後の砦の部分は、頭の悪い我々人間のために「しょうがないな…」と故意に残しておいてくれるのではないかとも考えたりしている。
「作者/AI」の歌集が出る日は案外近いのではないか。その歌を従来の歌集と同等に鑑賞すれば、今の優れた歌集を読むときと同じ感動が起きるはずだ。
だがしかし、その背後から立ち昇ってくるはずの「我」とはいったい何だろう?。「私性とAI」がっぷり四つの、短歌史上かつて無かった大きな難問が我々を待ち構えている。
短歌とAIについてかつて書いた評論があります。
「短歌往来」2022年11月号より










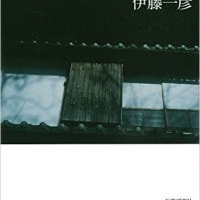
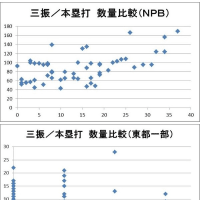







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます