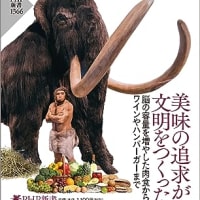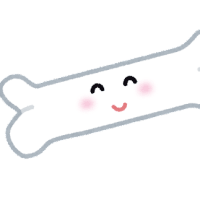タイユヴァンの料理書と中世のフランス料理-中世後期のヨーロッパの食(4)
「タイユヴァン(Taillevent)」はパリにあるレストランで、30年以上にわたってミシュランの3つ星を獲得している名店です。
この「タイユヴァン」という名前は14世紀のフランスで活躍した料理人ギヨーム・ティレル(1310~1395年)の別称で、「風を切る」という意味合いだそうです。風を切るように勢いのある料理を作ったということでしょうか。
タイユヴァンがフランス料理の名店の名前として使われる理由は、彼がフランス料理の基礎を築くという大きな足跡を残したからです。彼の偉大な業績の一つに『ル・ヴィアンディエ (le Viandier)』という料理書を書いたことがあげられます。これは、ローマ帝国以降のヨーロッパで最初の本格的な料理書と言われています。そして、1651年に料理人のラ・ヴァレンヌが『フランスの料理人 (le Cuisinier français)』という料理書を出すまでの長い間、フランス料理の手引き書となりました。
今回は『ル・ヴィアンディエ』を通して中世後期のヨーロッパの料理について見て行きたいと思います。

************
ギヨーム・ティレル(タイユヴァン)は少年の頃に料理の申し子と呼ばれたほどの早熟の天才だった。彼は1325年頃から宮廷の料理人として働き始め、やがてフィリップ6世やシャルル5世、シャルル6世など歴代のフランス国王の専属料理人として腕を振るった。
シャルル5世は本好きで知られており、タイユヴァンは彼から料理書を書くように命じられたと言われている。そうして出来上がったのが『ル・ヴィアンディエ (le Viandier)』である。Viandierとは本来は肉という意味だが、当時は料理という意味でも使用されており、ル・ヴィアンディエは「料理書」と訳すのが適当とされている。
本を書くと言っても印刷技術が進んでいなかった時代であり、タイユヴァンは手書きで料理のレシピなどを書き留めて行った。タイユヴァンの手稿は1373年から1380年にかけて書かれたものだと言われているが、数多くの料理人によって写本が繰り返されながら受け継がれて行った。そして1486年頃になって初めて活字本として印刷される。このため、多くの部分に他人の手が加えられていると推測されているのだ。とは言え、『ル・ヴィアンディエ』が14~15世紀のフランス料理の様子をつまびらかに伝えていることは間違いない。
ここで、『ル・ヴィアンディエ』のレシピを見る前に中世後期のヨーロッパの料理について概観してみよう。
中世後期は料理の世界に大きな変化が見られた時期である。その一つが味付けの変化だ。
中世の味付けは今よりもずっと酸味が効いていたと考えられている。ワインビネガーや未熟ブドウ果汁が料理の材料によく使用された。ここに大量の香辛料を加えた、酸っぱくて辛味のきいたものが中世の基本的な風味である。なお、香辛料はガレノスの「四体液説」で体のバランスを整えるのに有効であると考えられていたため、大量に使用されていたのだ。
中世後期になると、ここに甘味が加わるようになる。サトウキビが地中海西部地域で栽培されるようになり、ヨーロッパ全体に流通する砂糖の量が次第に増えて行ったことがこの理由の一つと考えられる。また、14世紀に砂糖の甘味が香辛料の辛さを和らげる効果があることが見つかったことも関係している。こうして、中世後期の料理は「酸っぱい」ものから「甘酸っぱい」ものへと変化して行った。
使用される香辛料にも変化が見られた。
ローマ帝国では香辛料の中でコショウが最もよく使用されていた。中世に入ってもコショウは人気であり、中世盛期でもよく使用されていた。しかし、中世後期になるとコショウの使用量が減少するのである。この理由に、ヴェネツィア商人などが行った地中海貿易によって大量のコショウが手に入るようになり、ありがたみが薄れてしまったことがあると考えられている。
コショウに代わって香辛料の王様の位置を占めたのがショウガである。ショウガは日本では生のまま使うが、欧米では乾燥させてパウダー状にしたものを使うのが一般的である。『ル・ヴィアンディエ』でも、ショウガパウダーが料理の香りづけによく使用されている。
また、それまでほとんど使用されていなかったバターが少しずつ使われるようになったことも中世後期の特徴だ。バターはもともと遊牧民が食べていたため、古代ローマでは野蛮人の食べ物とされ、整髪料や塗り薬として使われていた。それが中世後期になると主にヨーロッパ北部で食べられるようになったのである。
中世後期になると、上流階級の食事では、出される皿の数も増えて内容も豪華になった。例えば『ル・ヴィアンディエ』では、次のようなものが宴会のメニューとして記載されている。
第1サービス:去勢ニワトリのスープ、雌鳥の香草風味、新キャベツと猟獣肉
第2サービス:くじゃくのセロリ風味、去勢ニワトリのパテ、仔野ウサギのヴィネガー風味
第3サービス:甘味の山ウズラ、猟獣肉のパテ、ハトのエテュヴェ(蒸し煮)、ゼリー寄せと細切り肉
第4サービス:焼き菓子、クレーム・フリット(カスタードクリームに衣をつけて揚げたもの)、洋ナシのパテ、スイートアーモンド、クルミと洋ナシ
このように多種類の料理が出されるようになると、短時間で料理を作って皿に盛り、客に給仕することが難しくなったしまった。そこで各サービスの間に「アントルメ」と呼ばれる演じもので客を楽しませるようになった。
アントルメは現代では甘いデザートのことを言うが、中世では料理と料理の間の余興のことを指した(メは料理、アントルは間を意味する)。古代ローマで料理の間に各種の芸や音楽、劇を楽しんだのだが、これを真似て始められたとされている。アントルメでは、芸や音楽と同時に生きているように作ったツルやクジャクの料理なども出されたらしい。
それでは最後に、『ル・ヴィアンディエ』に記されているレシピをいくつか紹介しよう。
①イポクラス:タイユヴァンがヒポクラテスの処方から考案した香草や香辛料を加えたワインのこと。ルイ14世の時代まで、食前と食後に薬用酒としてよく飲まれていたという。
(作り方)ワイン1パント(930ml)に粉末のメース(ナツメグの種子のまわりの網目状の赤い皮の部分)3.8g、シナモン11.4g、丁子(クローブ)1.9g、砂糖180gを混ぜ、粉が沈んだら布でこして出来上がり。
②ガリマフレ:鶏肉もしくは羊肉を煮込んだ料理のこと。ガリマフレはフランスのピカルディ地方の方言で「がつがつ食う」という意味で、現代では「不味い料理」を意味する。
(作り方)骨ごとぶつ切りにした鶏肉をラードもしくはガチョウの脂で揚げ、ワイン、未熟ブドウ果汁、香辛料、ショウガパウダーで煮る。カムリーヌ(次参照)と塩をつけて食べる。
③カムリーヌ:香辛料と酸味の強い冷製ソースのこと。
(作り方)パンをキツネ色になるまで焼き、赤ワインにひたして裏ごしする。酢、シナモン、しょうが、丁子、メース、コショウを加えて裏ごしして出来上がり。
④中世のウナギの煮込み料理
(作り方)内臓を取ったウナギをゆがいて皮をむき、筒切り(背骨がついたまま輪切りすること)にする。これを鍋に入れ、輪切りにして揚げたタマネギ、ローストしたパン粉、マメのピュレ、水、ワインと一緒に沸騰させる。さらに、ショウガパウダー、シナモン、丁子、サフラン、未熟ブドウ果汁を加え煮込む。酸味を強くするのが美味しくいただくコツ。
⑤カモの白いドディーヌがけ:ドディーヌは中世で最も好まれたカモ料理用ソースの1つ。
(作り方)カモを下処理し、大串に刺してローストする。牛乳とショウガパウダーを少々入れた鍋をローストしているカモの下に置いて、脂と焼き汁を受け止める。その後、卵黄と塩を加えてよく混ぜ、布ごしする。好みで砂糖を加えて混ぜながら沸騰させる。肉に火が通ったら上からかけて出来上がり。
どれも美味しそうな感じがするが、現代人の舌にはなかなか合わないもののようだ。