シェーンベルクは「私は《12音技法》で作曲をしたのではない、12音技法で《作曲》をしたのだ」と残したが、この言葉は、作曲技法のアナリーゼの限界を示している。
学生がその技法をマスターし、シェーンベルク風の作品を易々と作って見せたところで、既にそれは亜流。
「技法」に興味が行くか、「中味」に興味が行くか、が理論家と芸術家との分岐点だろう。
では「中味」とは…?その人の生き方、信念―もしその人が作曲家にならなかったとしても、たとえば宗教家、画家、作家、政治家、一人の親…として同様の理念を貫き、同時代の人々(や家族)を感化させたであろう根源的な力。「感情に訴える…」「精神力」などと言われる―営みへの反映。
ただ、「感情」「精神」は、儚く脆い。その産物が軍国主義、世界大戦、原爆、テロ…だとすれば、確かに感情に流されるのは危険だ。それを踏まえた上での「感情の否定」は、そうでないただの「技巧主義」とはいずれ区別がつく。例えばフォルテが一切無い曲。絶対に盛り上がらない曲(現代音楽では、よくある)―それらの中にも本物と、偽者が。
正直に言うと、僕は技法を解き明かすことにも興味がある…パズルを解くようで。しかし、いったん種明かしが出来てしまったら同じ手法で作曲しても、不思議なことに殆ど間違いなく魂の抜け殻になってしまう。どうしてだろう?
むしろその源にあるもの―その技法をどうしても!生み出さずにはいられなかった心理的、社会的背景、葛藤。
技法の彼岸にあるもの―荘厳な教会に圧倒され、感化される時、教会の「建築技術」に感動するのではない。邂逅した瞬間、どうしようもなく感情を丸ごと突き動かされてしまう、存在自体が発散する力。
どうして?どうしても!どうしようもなく…技法がどんなに新しくなろうとも、この得体の知れない魅力こそ、作品が-classic-であることの証左だ。
![]()
作曲の能力を客観的に言うなら―敷衍(ふえん)―だろう。モチーフを練り上げる手段が、昔であればフーガ、ソナタ、ロンド、変奏曲など、すべて敷衍するための技術であり、曲がフーガとなるか、ソナタとなるか、ロンドとなるかは、着想したモチーフによって、生まれながらにして決まっているようなものだ。
ところで、遺伝子や細胞に思想はあるだろうか?否。思想と言えるほどの複雑な「表出されるパターン」は、個々の生命体レベルになって、初めて宿る。モチーフ自体に思想は無く、それを敷衍し、どう構成するかによって、音楽的な思想が形成されるのと同じく…「運命」の「ダダダダーン」それ自体は、シリアスな場面と言うよりは、現在、笑いを取るためにしばしば濫用される。
この敷衍が現代音楽には中々見られないように思う。同じ事を延々と、殆ど変化させずにただ続けるのは敷衍では無い。相容れることの無いモチーフを継ぎはぎし、新味を狙う、或いは古典的な構成法を嘲笑う、といった事は、サティが「パラード」で一度やれば、もう結構。
一方、一見何の脈絡も無いように見えて、実は一貫した発展の原理が巧妙に潜んでいる―ドビュッシーの「オンディーヌ」のような曲には興味をひく。
「変化させながら持続を作って、それで音楽と言えるかな?」ルクセンブルク国際作曲コンクールで入賞した拙作に対し、先生から頂いたお言葉。
爾来、色んな作品を聴けば聴くほど、フーガやソナタやロンドや変奏曲に匹敵する敷衍する力が、時代を超えて普遍的な作品になり得るための分岐点…との確信を深める。
(写真:西武柳沢駅前)![]()













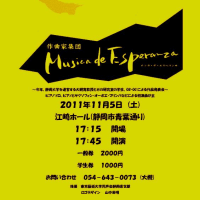



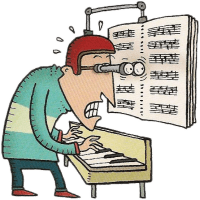

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます