昨日、今日と891Zを吹いてみた印象では、とにかくよく鳴る楽器です。もう「こんなに鳴っちゃっていいの?」ていう位よく鳴る。鳴りまくりです。マッチョな音がします。この楽器ならフルオーケストラにでも爆音のバンドサウンドにでも対等に張れそうな気がします。しかし、豪快に鳴らせる楽器だからといって、小回りが利かないということはなく、音量を抑えた演奏においては甘く柔らかい音色でレスポンスも素晴らしいです。美しいコンパクトなサウンドから豪快なサウンドまで表現できるキャパシティーの非常に大きな楽器ですね。新品時で既にこんなに鳴りまくっているのに、2~3年吹き込んだ後にはいったいどうなっちゃうんでしょうか。

マウスパイプがNYタイプ(ワイクリフ・ゴードン監修)とLAタイプ(アンディ・マーチン監修)の2本付いていますが、それぞれその監修に携わったプレーヤーの特徴がよく出ていて面白いですね。NYタイプは楽器全体を豊かな響きでたっぷり鳴らせる感覚ですし、LAタイプはpp~mfあたりの反応の良さ、音の粒立ちが素晴らしいです。どちらのタイプも非常に魅力的で、現時点まだどちらのタイプをメインで使おうか決めかねているところですが、吹奏の違和感はそれほど無いので、音楽ジャンル、編成によってマウスパイプを交換しても良さそうです。また今後マウスパイプのバリエーションが増えてくれると嬉しいところです。個人的にはスターリングシルバーパイプを作ってくれないかなぁ~なんて思ってますが。

今までにないユニークなデザインのバランサーです。
何となくバットマンのロゴに似ていると思いませんか?
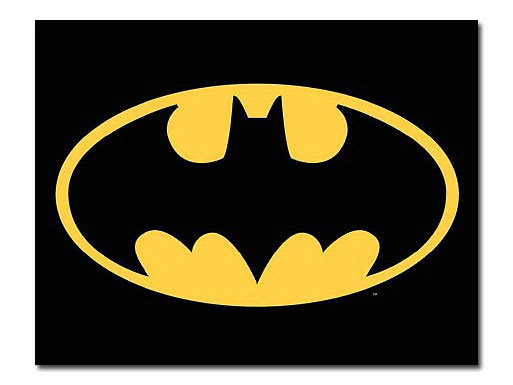
このバットマン・バランサー(勝手に命名)、重量バランスも考慮された上でのデザインなのでしょうか、程よい重さで音色も良いですね。試しにバランサーを外して吹いてみたのですが、やはりバランサーを装着した方が圧倒的に吹奏感、音色ともに良好です。697Zの場合はバランサー設計があまり良くなく、バランサーは外した方が良かったのですが、891Zではバランサーの材質、重量等かなり綿密に設計されていますね。ということは、このバットマン・バランサーを697Zに装着したら697Zの弱点も改善されるかもしれませんね。今度試してみよう。

昔からヤマハのケースはお気に入りなんですが、891Zの付属ケースいいですねぇ~。コンパクトかつ頑丈です。本当によく考えられてますわ。このストラップは重宝します。コンパクト&軽量でいえばゲッツェンのケースが一番なんですが、楽器保護の点に関してはヤマハの方が安心です。
当初、891Zを買ったら697Zは手放すつもりでいたのですが、891Zと697Zを吹き比べてみると明らかに違うキャラクターの楽器で、やはり697Zでなければ出せないニュアンス、音色はあるようです。位置づけ的にも891Zは697Zの後継機種(改良版)ではありませんしね。ジャンルを選ばずオールラウンドで使える891Zは、細管トロンボーンとして完成された楽器だと思うのですが、ジャンルは限定されてしまうけれども697Zのクリアーな美しい音色は捨て難いです。ソロ演奏に限定するのであれば、僕は697Zの方に魅力を感じます。オールラウンドで使える891Zはいわゆる ’道具’ としてとても優れているのだと思います。楽器を仕事の ’道具’ としてとらえた場合、やはり圧倒的に守備範囲の広い891Zの方に軍配が上がると思うのですが、いざ自分自身の音楽を表現するとなると、やはり697Zの方かなぁ~、と思ってしまいます。まぁ、まだ891Zに馴染んでいないので、これから使い込んでいってみないとわかりませんが。
いずれにしても、もし学生さんとかに楽器購入の相談を受けたら、間違いなく891Zがイチオシですね。誰が吹いても吹きやすいのが891Zです。ヤマハの場合、まず ’ハズレ’ というのは滅多にありませんし。でも891Zの登場でますます697Zの陰が薄くなってしまうのが個人的にはちょっとさみしい。。。697Zってホント銘器なんですよ。
最後に891Zに対するSwing Chipの貼付けについてですが、697Zではバランサーを外してマウスピースレシーバー部と主管の2箇所にSwing Chipを貼った方が音色、吹奏感ともにベストだったのですが、891Zで同じように試してみたらいまいち心地良くありませんでした。それなりに変化は楽しめるものの、891Z本来のポテンシャルを上手く引き出せないようです。891Zの場合は何か足したり引いたりしない方が良さそうです。それだけ完成された楽器ということですね。
891Zはヤマハ細管テナートロンボーンの完成形といってもいいでしょう。




















