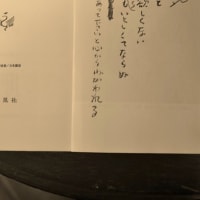やなぎごえが外の渡り廊下で波打った。蛍光灯のチカチカまたたく音は団地を神経質にさせ、百日紅の花を散らし、七階の手すりから白い足をひざうらまでつき出させ、ほどなくすうっとひき込ませた。
やけに頭は重たく身体が浮腫む。ベッドから起きあがることもままならず、唇をひらけば左の顎のつけねがぽくっと鳴った。シーツが湿っぽい。背中や腋にシャツからほつれた糸くずがくっついていた。
気象病、というものがあるらしい。気圧や気温、湿度の急激な変化に肉体が対応しきれず生じるものだという。あおむけで額を窓の外へ向けると、あやうげな蛍光灯が何度か明滅して、切れた。
そのひとからむかしのはなしを聴いてすこし揉めた。バラエティー番組の笑い声がダイニングから伝わる。最近のバラエティーは空々しくて観ていられないといつも言っているのに。なにかがどうしようもなく心身から欠けてゆく数時間、部屋に戻ってこないひとよりもわたしにはやなぎごえが近しかった。そういえば蝉の声を朝から聴かない。
ニトリの看板の照明が消えたあと、調子はずれであるにしろどこか媚を含んだ艶っぽさで、やなぎごえは下の中学校の校庭に植わる木々までも揺さぶるのだった。からだの底でこらえきれず焼く。夕飯、細胞、もう飛べない蝉……しんでいった。わたしはただ、ただ見ていた。傍観者だった。けむりが背ぼねへとのぼってくる。やなぎごえならわたしを遠くへ連れていってくれるだろうか。からだの内がわから熱のかたまりがこみあげた。
春と夏、四季の間には抽斗があり、そこに次へと持ってゆけないものを置いてゆく。人目を気にしながら、そっとちいさな箱にさかなの骨を入れてゆくひとのうしろ姿――。
「ダイちゃんなら、ぜんぶ捨ててくれるのに」
七階から百日紅の花が窓から入りこんで、口内に降り注いだ。
「ユカワさんの持っている家族との思い出すべてを憎みました。咳が出てしょうがないから処分して、そうユカワさんに言いました。それでもわたしの気持ちは収まらなかった。夏と秋の間には一緒に行った江ノ島の海を、冬と春の間には結婚の約束をそれぞれ抽斗に畳んで。時おりひろげては肩をふるわせました。大切にしていた本、写真、ユカワさんは概ね捨ててくれました。あなたの気がそれで済むのなら、そんなあきらめが顔に浮かんでいました」
喉がいがいがする。襖をあけ、テレビのつけっぱなしにされたダイニングへ踵をおろすと、そのひとはいなかった。常温の水に手を伸ばしかけたとき、不意に風が臀部にあたった。見ると扇風機が半ば閉まった隣室へと首を動かし、寝息をたてる母親の横顔を撫でていた。頭痛も眩暈もやまない。棘のあるはだかになって、声帯と胸のあたりを行き来する熱に目をうるませながら、やなぎごえを追い、ドアへ向かう足の甲に、ずしりと感じられるもの……。
「トウコちゃん、濡れているね。ギトギトだ、何を持っているの」
七階から髪の毛の束がばさり、ばさりと落ちてきて、うつぶせになったそのひとの背なかへ降り注いだ。
「アライさんは夏でした。すべてのしがらみから放たれたいのか、部屋では一糸まとわなかった。喫煙の習慣から声が低くてひどくかすれていた。私はアライさんの声がすきではなかった。ようやく約束の果たせそうだった海岸線で、ともだちのダイちゃんが猫をころした。私がどうして、ときくと、あれ、病気でもう生きられなかったんだ、そうダイちゃんは笑いました。アライさんも笑っていた。ダイちゃんが路上でパフォーマンスをしているところを撮影して、そのフィルムを持っていたのだけれど、あれはみんな秋のものだった。だから私とアライさんのベッドの間隔は、どんどん広がってゆきました。晩夏の恍惚はすでに遠く、しかし高く澄んだ声音でした」
火災警報器が鳴った。それでもそのひとはドアの前で突っ伏したままだった。何しているの。門番。だれの。きみの。ふうん、なんか火事みたいだよ、逃げなくてよいの。母は耳がとおいから、聴こえないんだ。そういえば、だれも外に出てきている様子、ないみたいだね。やなぎごえがきているからね。ねえ、
ドアを開けると、やなぎごえがあたりに満ちていた。
玄関をあがり靴箱の上コップに挿してあるアザミの花を眺めながらそのまま通された応接間で気流と気流が話しているのをみてあなたが邪魔なんですと叫び二階にあがって抽斗をしめると三階で鈴虫とダイちゃんが抽斗で鳴いていてうっとうしいのでしめ四階で猫がおいしい内臓の部分をえぐられて朽ちていたからしずかに抽斗へ運び五階ではユカワさんと知らないすっぱだかの女がうれしそうにこちらを見つめていたのでむかむかして煙草に火をつけてくゆらせながら六階へゆくちがうの、仕事道具でありかけがえのない本や家族の写真を捨ててほしかったんじゃない、自分の母親を罵られても顔色ひとつ変えないで静観をきめこんでだまっているユカワさんとそれでも春を待ちたかったのに。
荒れ狂っているなあ。そのひとと顔を見合わせた。どう。うん、太古のひとってこういう猛威を肌で感じていたんだなって。風邪をひかないようにね、もう家へ入ろう。明日も稽古があるし。夜にはうまいものを食べにゆこう、明日……もう今日か、秋らしくなっているよ、きっと。ねえ。ん? やなぎごえが、さかなの骨でなくてよかった。わすれられないえいようはさみしい。
花という花の香りを遠ざけたかった、思いだすのはそのほとんどが色鮮やかな姿だった。待ちすぎた芽吹きの頃、向けられたカメラに常に笑顔を定めて咲く花は隣に置いて、ふりかえる人の顔を数えるうち歩道に蝉の死骸が転がりはじめた。開けられない抽斗ばかり増えた。飲みくだせない花の名前がそのひとを無口にした。みどりごえが轟くのを知って、そのひとつをようやくとなえ、わたしに聴かせたのか。花から花へ渡るとき、枯れるようにと育てた花の名をそのとき目の前にいるひとにも教えていたのだろうか。「ハナニアラシノタトヘモアルゾ(※1)」捨てられないもので部屋は散らかっている。なぜならそれらがそのひとを作っているものだから。
テレビは早朝ニュースを放映しはじめた。消えていた蛍光灯が力なくパカパカとふたたび灯った。シャワーで流してもそのひとの背なかの毛髪はなかなか取りきれない。煙草のにおいが流れてきて鼻さきをかすめ、思わず咳が出た。それは七階からだった。
(※1)于武陵の詩「勧酒」(井伏鱒二訳)より
やけに頭は重たく身体が浮腫む。ベッドから起きあがることもままならず、唇をひらけば左の顎のつけねがぽくっと鳴った。シーツが湿っぽい。背中や腋にシャツからほつれた糸くずがくっついていた。
気象病、というものがあるらしい。気圧や気温、湿度の急激な変化に肉体が対応しきれず生じるものだという。あおむけで額を窓の外へ向けると、あやうげな蛍光灯が何度か明滅して、切れた。
そのひとからむかしのはなしを聴いてすこし揉めた。バラエティー番組の笑い声がダイニングから伝わる。最近のバラエティーは空々しくて観ていられないといつも言っているのに。なにかがどうしようもなく心身から欠けてゆく数時間、部屋に戻ってこないひとよりもわたしにはやなぎごえが近しかった。そういえば蝉の声を朝から聴かない。
ニトリの看板の照明が消えたあと、調子はずれであるにしろどこか媚を含んだ艶っぽさで、やなぎごえは下の中学校の校庭に植わる木々までも揺さぶるのだった。からだの底でこらえきれず焼く。夕飯、細胞、もう飛べない蝉……しんでいった。わたしはただ、ただ見ていた。傍観者だった。けむりが背ぼねへとのぼってくる。やなぎごえならわたしを遠くへ連れていってくれるだろうか。からだの内がわから熱のかたまりがこみあげた。
春と夏、四季の間には抽斗があり、そこに次へと持ってゆけないものを置いてゆく。人目を気にしながら、そっとちいさな箱にさかなの骨を入れてゆくひとのうしろ姿――。
「ダイちゃんなら、ぜんぶ捨ててくれるのに」
七階から百日紅の花が窓から入りこんで、口内に降り注いだ。
「ユカワさんの持っている家族との思い出すべてを憎みました。咳が出てしょうがないから処分して、そうユカワさんに言いました。それでもわたしの気持ちは収まらなかった。夏と秋の間には一緒に行った江ノ島の海を、冬と春の間には結婚の約束をそれぞれ抽斗に畳んで。時おりひろげては肩をふるわせました。大切にしていた本、写真、ユカワさんは概ね捨ててくれました。あなたの気がそれで済むのなら、そんなあきらめが顔に浮かんでいました」
喉がいがいがする。襖をあけ、テレビのつけっぱなしにされたダイニングへ踵をおろすと、そのひとはいなかった。常温の水に手を伸ばしかけたとき、不意に風が臀部にあたった。見ると扇風機が半ば閉まった隣室へと首を動かし、寝息をたてる母親の横顔を撫でていた。頭痛も眩暈もやまない。棘のあるはだかになって、声帯と胸のあたりを行き来する熱に目をうるませながら、やなぎごえを追い、ドアへ向かう足の甲に、ずしりと感じられるもの……。
「トウコちゃん、濡れているね。ギトギトだ、何を持っているの」
七階から髪の毛の束がばさり、ばさりと落ちてきて、うつぶせになったそのひとの背なかへ降り注いだ。
「アライさんは夏でした。すべてのしがらみから放たれたいのか、部屋では一糸まとわなかった。喫煙の習慣から声が低くてひどくかすれていた。私はアライさんの声がすきではなかった。ようやく約束の果たせそうだった海岸線で、ともだちのダイちゃんが猫をころした。私がどうして、ときくと、あれ、病気でもう生きられなかったんだ、そうダイちゃんは笑いました。アライさんも笑っていた。ダイちゃんが路上でパフォーマンスをしているところを撮影して、そのフィルムを持っていたのだけれど、あれはみんな秋のものだった。だから私とアライさんのベッドの間隔は、どんどん広がってゆきました。晩夏の恍惚はすでに遠く、しかし高く澄んだ声音でした」
火災警報器が鳴った。それでもそのひとはドアの前で突っ伏したままだった。何しているの。門番。だれの。きみの。ふうん、なんか火事みたいだよ、逃げなくてよいの。母は耳がとおいから、聴こえないんだ。そういえば、だれも外に出てきている様子、ないみたいだね。やなぎごえがきているからね。ねえ、
ドアを開けると、やなぎごえがあたりに満ちていた。
玄関をあがり靴箱の上コップに挿してあるアザミの花を眺めながらそのまま通された応接間で気流と気流が話しているのをみてあなたが邪魔なんですと叫び二階にあがって抽斗をしめると三階で鈴虫とダイちゃんが抽斗で鳴いていてうっとうしいのでしめ四階で猫がおいしい内臓の部分をえぐられて朽ちていたからしずかに抽斗へ運び五階ではユカワさんと知らないすっぱだかの女がうれしそうにこちらを見つめていたのでむかむかして煙草に火をつけてくゆらせながら六階へゆくちがうの、仕事道具でありかけがえのない本や家族の写真を捨ててほしかったんじゃない、自分の母親を罵られても顔色ひとつ変えないで静観をきめこんでだまっているユカワさんとそれでも春を待ちたかったのに。
荒れ狂っているなあ。そのひとと顔を見合わせた。どう。うん、太古のひとってこういう猛威を肌で感じていたんだなって。風邪をひかないようにね、もう家へ入ろう。明日も稽古があるし。夜にはうまいものを食べにゆこう、明日……もう今日か、秋らしくなっているよ、きっと。ねえ。ん? やなぎごえが、さかなの骨でなくてよかった。わすれられないえいようはさみしい。
花という花の香りを遠ざけたかった、思いだすのはそのほとんどが色鮮やかな姿だった。待ちすぎた芽吹きの頃、向けられたカメラに常に笑顔を定めて咲く花は隣に置いて、ふりかえる人の顔を数えるうち歩道に蝉の死骸が転がりはじめた。開けられない抽斗ばかり増えた。飲みくだせない花の名前がそのひとを無口にした。みどりごえが轟くのを知って、そのひとつをようやくとなえ、わたしに聴かせたのか。花から花へ渡るとき、枯れるようにと育てた花の名をそのとき目の前にいるひとにも教えていたのだろうか。「ハナニアラシノタトヘモアルゾ(※1)」捨てられないもので部屋は散らかっている。なぜならそれらがそのひとを作っているものだから。
テレビは早朝ニュースを放映しはじめた。消えていた蛍光灯が力なくパカパカとふたたび灯った。シャワーで流してもそのひとの背なかの毛髪はなかなか取りきれない。煙草のにおいが流れてきて鼻さきをかすめ、思わず咳が出た。それは七階からだった。
(※1)于武陵の詩「勧酒」(井伏鱒二訳)より