――― アメリカ人よ、International English を学べ ―――
私は貿易商社の化学品部で長らく輸入の仕事に携わったので、当時は、
アメリカの化学会社のExport Manager達とよく付き合った。
彼らは日頃はアメリカ本社のオフィスで執務しているが、
毎年2~3回、アジア各国に出張する。
一回の出張期間は2~3週間程度で、その間に、
日本、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポールなどを歴訪する。

(Export Manager と私。New Jersey 州にて)
彼らの話す英語は概して分かり易い。
というのも彼らは日本人はじめ東南アジア各国の、
英語を母国語としないビジネスパーソンと接し慣れているので、
どのように話せばよく通じるかを心得ている。
語彙や発音やスピードなどに注意を払っている。
もちろん高等教育を受けているから、クセのない標準的な英語を話す。
それに彼らとて商売が大事だから分かってもらえるように丁寧に話す必要がある。
聞くときも想像力をフルに働かせて理解に努める。
あるExport Manager が、2~3週間アジアに出張してアメリカに帰国すると、
家族から英語が少しおかいと指摘されることがあると言っていた。
しかし、私はそれでよいと思う。
我々が日本に住んでいて、たまに旅行や出張で海外に出かけるだけで
Nativeのような英語力を身につけるなんてことは到底無理である。
一方のExport Manager達はアジアの国々でも母国語で通じるのだから、
せめてこちら側のレベルまで歩み寄るくらいの努力と配慮はしてもらいたい。
これと対照をなすのがアメリカ国内の、例えばマクドナルドの店員である。
アメリカには東洋系アメリカ人も大勢いるから、
彼女たちは私を見てもガイジンとは思わない。
忙しいから早口でしゃべる、というか、
彼女たちにとっての普通の速さは私には早すぎるといった方が正しいだろう。
それに彼女たちの誰もがニュース・キャスターのような
標準的できれいな英語でしゃべるとは限らない。
私は ” Eat here or to go ? ” が聞き取れなくて困ったことがある。
何回聞き直しても相手は同じ速さ、同じリズムで同じ事を繰り返すばかり。
二回目は工夫して、Eat here?・・or ・・to go? のように区切って言うとか
Would you like to eat here or take out?
のような教科書的英語に言い直すとかしてくれれば助かるのだが、
相手にはそのような心遣いや発想は微塵もない。
私の後ろには何人かの客が順番を待って並んでいるから、余計に焦る。
普通、言葉が分からなくても常識が働くものだが、
日本でもマクドナルドには滅多に行かないので、
「店内でお召し上がりですか、それともお持ち帰りですか」
という質問そのものを全く想定していなかった。
一度この決まり文句を知ってしまえば、後はどうってことはないのだが。
このようにNativeとの日常会話は難しい。
外国語の出来る程度を表すのに、
ビジネス英語>日常会話>旅行英語>全く出来ない・・・
という難易度の順で示されることがある。
あるいは「日常会話程度しか出来ない」という表現もよく聞く。
しかし、私には日常会話が一番難しい。
それに引き換え、ビジネスの会話はある意味で簡単である。
端的に言えば、貿易業であれば、
商品の価格、品質、数量、包装、積み期、支払い条件を決めれば終わり。
決まるまでの過程で多少のやりとりがあるだけだ。
世界にはいろいろな英語がある。
シンガポールの人たちの英語は独特らしくてシングリッシュと呼ばれる。
イタリア人はImportant を「インポルタント」と発音する。
アクセントはイタリア風に、後ろから2番目の音節「タ」にある。
「ト」の発音はManifesto やMonsantoのようにto であってt ではない。
かと思えば、フランス人はHの発音ができない。ホテルはオテルになる。
イベット・ジローというシャンソン歌手が「セレソローサ」という曲の日本語歌詞を、
「桜のアナと、林檎のアナが~」と歌っていたのを年配の方々はご記憶だろう。
日本人は時に米(Rice)の代わりに、しらみ(Lice)を食べたりもする。
しかし、大切なことは、お国訛りがあっても、Nativeのように話せなくても、
言葉がどんどん出てきて、イイタイコトがきちんと伝わることである。
礼儀正しい言葉使いも大切だ。
体よく言えば、
アメリカ人やイギリス人の話す英語をLocal English とすれば、
我々が話す世界共通語としての英語はInternational English なのである。
実はこのことは、NHKテレビ「ニュースで英会話」出演の
日本在住のアメリカ人、Joseph Shaules 氏がそのエッセイ、
”Flabbergasted " の中で主張している。
ご興味のある方は、
http://cgi2.nhk.or.jp/e-news/essay/index.cgi?pn=091121_shaules
をご覧下さい。
アメリカ人よ、International English を学べ!

(人数は7人、国籍は米、英、伊、蘭、日の5カ国、
言語は1つ → International English )
That’s about it for today. (今日はこの辺で)
(続く)
私は貿易商社の化学品部で長らく輸入の仕事に携わったので、当時は、
アメリカの化学会社のExport Manager達とよく付き合った。
彼らは日頃はアメリカ本社のオフィスで執務しているが、
毎年2~3回、アジア各国に出張する。
一回の出張期間は2~3週間程度で、その間に、
日本、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポールなどを歴訪する。

(Export Manager と私。New Jersey 州にて)
彼らの話す英語は概して分かり易い。
というのも彼らは日本人はじめ東南アジア各国の、
英語を母国語としないビジネスパーソンと接し慣れているので、
どのように話せばよく通じるかを心得ている。
語彙や発音やスピードなどに注意を払っている。
もちろん高等教育を受けているから、クセのない標準的な英語を話す。
それに彼らとて商売が大事だから分かってもらえるように丁寧に話す必要がある。
聞くときも想像力をフルに働かせて理解に努める。
あるExport Manager が、2~3週間アジアに出張してアメリカに帰国すると、
家族から英語が少しおかいと指摘されることがあると言っていた。
しかし、私はそれでよいと思う。
我々が日本に住んでいて、たまに旅行や出張で海外に出かけるだけで
Nativeのような英語力を身につけるなんてことは到底無理である。
一方のExport Manager達はアジアの国々でも母国語で通じるのだから、
せめてこちら側のレベルまで歩み寄るくらいの努力と配慮はしてもらいたい。
これと対照をなすのがアメリカ国内の、例えばマクドナルドの店員である。
アメリカには東洋系アメリカ人も大勢いるから、
彼女たちは私を見てもガイジンとは思わない。
忙しいから早口でしゃべる、というか、
彼女たちにとっての普通の速さは私には早すぎるといった方が正しいだろう。
それに彼女たちの誰もがニュース・キャスターのような
標準的できれいな英語でしゃべるとは限らない。
私は ” Eat here or to go ? ” が聞き取れなくて困ったことがある。
何回聞き直しても相手は同じ速さ、同じリズムで同じ事を繰り返すばかり。
二回目は工夫して、Eat here?・・or ・・to go? のように区切って言うとか
Would you like to eat here or take out?
のような教科書的英語に言い直すとかしてくれれば助かるのだが、
相手にはそのような心遣いや発想は微塵もない。
私の後ろには何人かの客が順番を待って並んでいるから、余計に焦る。
普通、言葉が分からなくても常識が働くものだが、
日本でもマクドナルドには滅多に行かないので、
「店内でお召し上がりですか、それともお持ち帰りですか」
という質問そのものを全く想定していなかった。
一度この決まり文句を知ってしまえば、後はどうってことはないのだが。
このようにNativeとの日常会話は難しい。
外国語の出来る程度を表すのに、
ビジネス英語>日常会話>旅行英語>全く出来ない・・・
という難易度の順で示されることがある。
あるいは「日常会話程度しか出来ない」という表現もよく聞く。
しかし、私には日常会話が一番難しい。
それに引き換え、ビジネスの会話はある意味で簡単である。
端的に言えば、貿易業であれば、
商品の価格、品質、数量、包装、積み期、支払い条件を決めれば終わり。
決まるまでの過程で多少のやりとりがあるだけだ。
世界にはいろいろな英語がある。
シンガポールの人たちの英語は独特らしくてシングリッシュと呼ばれる。
イタリア人はImportant を「インポルタント」と発音する。
アクセントはイタリア風に、後ろから2番目の音節「タ」にある。
「ト」の発音はManifesto やMonsantoのようにto であってt ではない。
かと思えば、フランス人はHの発音ができない。ホテルはオテルになる。
イベット・ジローというシャンソン歌手が「セレソローサ」という曲の日本語歌詞を、
「桜のアナと、林檎のアナが~」と歌っていたのを年配の方々はご記憶だろう。
日本人は時に米(Rice)の代わりに、しらみ(Lice)を食べたりもする。
しかし、大切なことは、お国訛りがあっても、Nativeのように話せなくても、
言葉がどんどん出てきて、イイタイコトがきちんと伝わることである。
礼儀正しい言葉使いも大切だ。
体よく言えば、
アメリカ人やイギリス人の話す英語をLocal English とすれば、
我々が話す世界共通語としての英語はInternational English なのである。
実はこのことは、NHKテレビ「ニュースで英会話」出演の
日本在住のアメリカ人、Joseph Shaules 氏がそのエッセイ、
”Flabbergasted " の中で主張している。
ご興味のある方は、
http://cgi2.nhk.or.jp/e-news/essay/index.cgi?pn=091121_shaules
をご覧下さい。
アメリカ人よ、International English を学べ!

(人数は7人、国籍は米、英、伊、蘭、日の5カ国、
言語は1つ → International English )
That’s about it for today. (今日はこの辺で)
(続く)










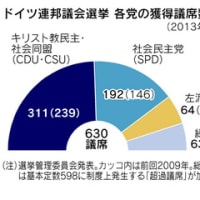









日常会話も難しいでしょうけど、やはりビジネス英語は大変だと思います。
商売上の条件がトントンと決まればいいでしょが、これが難航したときは大変です。条件の折り合いがなかなかつかないとき、日本では「そこを何とか」とかよく言いますがこれは英語でどう言えばいいのか。
「同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロセシング」(田村智子著 三修社2010)という本によると、これは
I understand the difficulty,but I'd still have to ask you this big favor.
というのだそうです。
英文を見ると、なるほど、と思いますが、これがすっと言えるひとはやはり上級者でしょう。
他にもいろいろな言い回しの英訳が書いてあります。
要は、意味を変えずに、英訳しやすい日本語に変換してから英語にしなさい、ということなのですが・・・。
写真は現役時代の、今となってはなつかしい写真のひとつです。
「そこを何とか~~」は通訳のプロが無理やり訳すと上のようになるのでしょうが、これで相手が同意するとは思えません。
ビジネスの英語は狭い土俵の上での話しなので、その意味で、イイタイコトさえ頭の中でまとまっていれば、たどたどしい英語でも何とか通じる。
飛行機のパイロットが管制塔と話す英語なども
多分限られた専門用語を知っていれば出来るのでは?
仕事の話が終わって、昼食しながら雑談する方が難しい。野球、映画、イラク戦争、家族のこと・・・話題の幅が広い。語彙も広い。アメリカ人が3~4人で、日本人は自分一人だと、彼らのペースになり易い。話題がいつ変わったのかも分からない。皆が笑っているときにひとり黙っているのもおかしいが、意味も分からず笑うのもおかしいし、困ってしまう。
そういう意味で、日常会話>ビジネス英語>旅行会話>全く出来ない・・・になります。私の場合は。