幼いころに、親に十分に認めてもらえなかった体験を持っている人はずいぶん沢山いるようです。
ボクのクラスにも大勢います。
認めてもらえないのは、とても悲しいし寂しいものですよね。
多くの場合は、親の持つ価値観をうまく受け入れられないことから、起きてしまう悲劇です。
親は、自分なりに良かれと思ったことを子どもに言うのですが、子どもは子どもで自分なりの価値観を持つのですから、葛藤は続きます。
特に子供のほうは、結局親に従うことになるのですから、不平や不満は募ります。
親にも親の苦悩はあるのですが、どうやら種類は違いますね。
子供にとっては理不尽なものもあるでしょう。
世間一般の常識として、親の価値観を押し付けられるのもたまりませんよね。
でも、それが親っていうものだし、子どもっていうものなんですけどね。
『あいつがおれでおれがあいつで』という児童文学を読んだことがあります。
大林宣彦監督の映画「転校生」が、それです。
自分の体が、異性の体と入れ替わってしまうという奇想天外な物語。
でも、この原作者である山下恒さんは、どうやら、多くの作品を「自分らしさ」というテーマにしているみたいです。
この『ぼくがぼくであること』の主人公、秀一は4人兄弟の3番目。
秀一以外は、みんな優秀で、秀一だけが劣等生。
この「自分だけ違う」という感覚を家族の中で味わうのは、とても繊細な問題です。

秀一は学校ではいつも叱られて、廊下に立たされます。
(今どきの子供は、立たされるなんてことあるのでしょうか?)
そんな学校での様子は、妹のマユミによって母親に逐一報告されます。
そして、毎日のように、家でもみっちりと母親に絞られるのです。
そんな毎日が繰り返され、ある日気まぐれに「家出してやる」なんて口にしたもんですから、またもや妹のマユミによって家族や近所中に知られることになってしまいます。
どうせ出来っこない、と言われるのが嫌で、止まっている軽トラックの荷台に乗り込み、車まかせに家出することになってしまいます。
ボクにも経験があります。
小学校5年生くらいの頃でした。
原因はわかりませんが、母親と大喧嘩をしたんです。
ボクは泣きながら炬燵の周りをぐるぐると母親から逃げていたのをよく覚えています。
そして、「家出してやる!」と、大見えを切って、家を飛び出しました。
でも、飛び出してみたものの、外はなんだか全然ボクを受け入れてはもらえないような感じがして、結局近所をうろうろするばかりでした。
そのうち、兄貴がボクを見つけて、家に連れ帰られてしまいました。
ほっとしたのも事実ですが、なんだかみじめで情けなかったなぁ、あのとき。
その点秀一は立派?です。
まぁ、物語だからってこともありますが、家出を実行したんですからね。
秀一は、山間の見知らぬ村にたどりつきます。
運のいいことに、気難しいおじいさんと孫の夏代が住んでいる家に転がり込むことができるのですが・・・・・・。
両親のいない夏代、その理由を隠し続けるおじいさん。
物語は意外な展開をしていきます。
そんなひと夏を終え、秀一は家に帰るのですが、当然、家では大騒ぎです。
しまいには、優等生だった兄弟たちも、父親も、母親の価値観との違いで家族の心がばらばらになっていってしまいます。
そして、最後には、とんでもないことが起きるのですが、秀一は自ら母親と向き合うことを決意します。
ぼくがぼくであること
生涯のテーマですね。
わがままという意味ではないし、自分勝手とも違う。
ぼくがぼくであること。
こんな物語を、小学生のころに読んでおきたかったなぁ。
ボクのクラスにも大勢います。
認めてもらえないのは、とても悲しいし寂しいものですよね。
多くの場合は、親の持つ価値観をうまく受け入れられないことから、起きてしまう悲劇です。
親は、自分なりに良かれと思ったことを子どもに言うのですが、子どもは子どもで自分なりの価値観を持つのですから、葛藤は続きます。
特に子供のほうは、結局親に従うことになるのですから、不平や不満は募ります。
親にも親の苦悩はあるのですが、どうやら種類は違いますね。
子供にとっては理不尽なものもあるでしょう。
世間一般の常識として、親の価値観を押し付けられるのもたまりませんよね。
でも、それが親っていうものだし、子どもっていうものなんですけどね。
『あいつがおれでおれがあいつで』という児童文学を読んだことがあります。
大林宣彦監督の映画「転校生」が、それです。
自分の体が、異性の体と入れ替わってしまうという奇想天外な物語。
でも、この原作者である山下恒さんは、どうやら、多くの作品を「自分らしさ」というテーマにしているみたいです。
この『ぼくがぼくであること』の主人公、秀一は4人兄弟の3番目。
秀一以外は、みんな優秀で、秀一だけが劣等生。
この「自分だけ違う」という感覚を家族の中で味わうのは、とても繊細な問題です。

秀一は学校ではいつも叱られて、廊下に立たされます。
(今どきの子供は、立たされるなんてことあるのでしょうか?)
そんな学校での様子は、妹のマユミによって母親に逐一報告されます。
そして、毎日のように、家でもみっちりと母親に絞られるのです。
そんな毎日が繰り返され、ある日気まぐれに「家出してやる」なんて口にしたもんですから、またもや妹のマユミによって家族や近所中に知られることになってしまいます。
どうせ出来っこない、と言われるのが嫌で、止まっている軽トラックの荷台に乗り込み、車まかせに家出することになってしまいます。
ボクにも経験があります。
小学校5年生くらいの頃でした。
原因はわかりませんが、母親と大喧嘩をしたんです。
ボクは泣きながら炬燵の周りをぐるぐると母親から逃げていたのをよく覚えています。
そして、「家出してやる!」と、大見えを切って、家を飛び出しました。
でも、飛び出してみたものの、外はなんだか全然ボクを受け入れてはもらえないような感じがして、結局近所をうろうろするばかりでした。
そのうち、兄貴がボクを見つけて、家に連れ帰られてしまいました。
ほっとしたのも事実ですが、なんだかみじめで情けなかったなぁ、あのとき。
その点秀一は立派?です。
まぁ、物語だからってこともありますが、家出を実行したんですからね。
秀一は、山間の見知らぬ村にたどりつきます。
運のいいことに、気難しいおじいさんと孫の夏代が住んでいる家に転がり込むことができるのですが・・・・・・。
両親のいない夏代、その理由を隠し続けるおじいさん。
物語は意外な展開をしていきます。
そんなひと夏を終え、秀一は家に帰るのですが、当然、家では大騒ぎです。
しまいには、優等生だった兄弟たちも、父親も、母親の価値観との違いで家族の心がばらばらになっていってしまいます。
そして、最後には、とんでもないことが起きるのですが、秀一は自ら母親と向き合うことを決意します。
ぼくがぼくであること
生涯のテーマですね。
わがままという意味ではないし、自分勝手とも違う。
ぼくがぼくであること。
こんな物語を、小学生のころに読んでおきたかったなぁ。













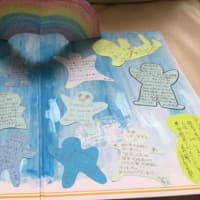



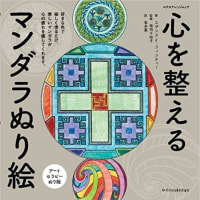
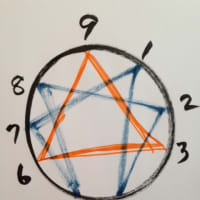

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます