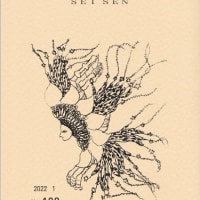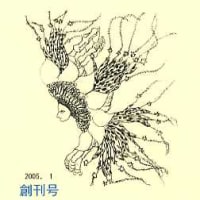第2号より「評伝 春日井 建」(岡嶋憲治)が連載中です。
初回の一部を御紹介します。
評伝 春日井 建 連載(一) 岡 嶋 憲 治
第一章『未青年』まで
第一節 幼年時代
(一)出生
歌人春日井建は一九三八(昭和十三)年十二月二十日、父春日井、母政子の長男
として愛知県丹羽郡(現江南市)布袋町大字小折三九五六番地の一に生まれた。父
は一八九六(明治二十九)年名古屋市東区に父佐藤深三郎、母かなの次男として生ま
れ、愛知五中から神宮皇學館に進み、皇學館在学中に「潮音」の創刊に参加、太田水
穂に師事した。一九一九年「覇王樹」創刊同人となり、一九二二(大正十一)年、創
立された名古屋短歌会(のちに中部短歌会と改称)が発行していた「短歌」に第三号
から出稿、一九五五年には浅野保のあとを襲って中部短歌会の主幹をつとめた。ま
た、母政子は一九〇七(明治四十)年東京浅草の生まれ、上野高等女学校卒業後、義
兄で彫刻家の毛利教武を介して知りあった「青垣」の大亦観風画伯の勧めにより作歌
を始め、大熊長次郎に師事した。一九三三年「短歌」同人となり、毛利政子名にて同
誌に短歌・随筆を寄せた。一九三六年春日井と結婚。ともに最初の配偶者とは死
別、は二度目の妻とも離別し、三度目の結婚であった。翌三七年長女佐紀子誕生、
そして明くる年の末に長男の建が誕生する。四〇年に次男の郁、四四年には次女の久
仁子が誕生、建は二男二女の第二子にあたる。
建が生まれた布袋町の家は、北側を木曽川が流れる濃尾平野のほぼ中央、名鉄犬山
線布袋駅のすぐ西側に位置していた。妹の森久仁子によれば、「赤い屋根の西洋館
風」の家で、太い根を張ったいちじくの大木が青々と茂る屋敷だったらしい(角川
「短歌」二〇〇四年九月号)。後年、建はこのいちじくの木をくり返し歌い、また散
文にも書いた。当時は江南市にあった滝実業(現滝学園)に国語教諭として奉職
し、鳥居政子との結婚を機に名古屋市千種区(現昭和区)の曙町から布袋に移ってき
たばかりであった。夫婦が新生活を始めた布袋の家には、の先妻である春日井とき
(現尾西市富田出身、一九二七年死去)が生んだ長女四七子と次女須美子、およびと
きの両親である春日井藤十郎・あやをの四人が同居していた。嫁いだばかりの政子に
とっては、義父母の世話のほかに、二人の姉妹の母親の役割が待っていたことにな
る。この時、三十九歳、政子は二十九歳であった。建が生まれたのはその翌々年の
十二月である。時代は前の年に日本が中国と始めた戦争が、政府の不拡大方針にもか
かわらず長期化し、泥沼化の様相を呈し始めていた。この年の四月、第一次近衛文麿
内閣は「支那事変」を背景に、政府が随時国民の権利と財産を制限できる国家総動員
法を公布した。
建が生まれた年の「短歌」一月号を見ると、「南京入城」と題するの歌十数首が
掲載されている。「軍帽にかがやく朝をゆく兵の軒昂としてきびしかりけり」とか、
「今日の日にあぐる兵らが勝鬨(かちどき)を耳には聞きて泣きにけむかも」といった歌
が並んでいる。同年九月号には「勤労団即時」が掲載され、生徒たちを率いて開墾に
従事したことが歌われているので、江南の片田舎にも戦争の足音が着実に忍び寄って
いたのだろう。しかし夫婦の生活には事件らしい事件もなく、幼いいのちの加わった
この年の春も平穏のうちに暮れようとしていた。
なれなれて夫にわが言ふくづれたる言葉はときにさびしく思ふ(政子)
湯あみしてわかやぐ妻は春の夜の添乳けうとく寝入りたらしも()
結婚後二年ほどが経過し、新生活への馴致とそのかすかな寂しさが寡黙に歌われてい
る。互いに見つめ合う夫婦の日常の目は穏やかで愛情に満ちているが、家族を多くか
かえた生活は決して楽なものではなかっただろう。しかも歳晩にはもうひとり家族が
加わろうとしている。ことに乳飲み子のほかに十代の娘を二人もつことになった政子
は、毎日の生活に追われて、おそらく息つく暇もなかったことだろう。建の生まれる
直前の政子の歌に次のような作がある。
いはけなき汝はも姉ぞ今の間にたつぷりと飲め母吾が乳を
乳房ほる吾子背負ひ来てせんなけれ桑畑はすでに月夜こほろぎ
冬には乳離れを強いられるわが子に、今のうちにたっぷりと母乳を飲んでおけと
言っているのである。桑畑に出て良夜の月を仰ぐこの若い母親には、一見、生活して
いくのうえでの迷いや不安は何もないように見える。しかし彼女には、馴染んでゆく
夫との生活にふっと寂しさを覚えたりする内省的なところがあった。普通なら生活の
内に紛れてしまう折々の「詩心」を、この若やいだ「妻」は決して手放すことがな
かったのである。もちろん夫の文学的影響はあっただろう。しかし後年、建が短歌
という形式を自己表現のひとつとして選んだ背景には、父の存在は言うに及ばず、
少女のころから文学に親しんでいたこの母の存在を抜きには語れない。象徴的に言え
ば、そもそも建にはその出生の時から短歌という詩形が、乳幼児の蒙古斑のように身
体に刻印されていたのだ。「父も母も短歌を作っていた」という事実を強調しすぎる
ことは、あるいはこの卓絶した歌人の本質を見誤らせることになるかもしれない。し
かし建の伝記を試みようとする者なら、おそらく誰もがや政子によってこの歌人の
出生が歌い留められているのではないかと考えるだろう。
(後略)
(第2号、2005年3月1日発行)
初回の一部を御紹介します。
評伝 春日井 建 連載(一) 岡 嶋 憲 治
第一章『未青年』まで
第一節 幼年時代
(一)出生
歌人春日井建は一九三八(昭和十三)年十二月二十日、父春日井、母政子の長男
として愛知県丹羽郡(現江南市)布袋町大字小折三九五六番地の一に生まれた。父
は一八九六(明治二十九)年名古屋市東区に父佐藤深三郎、母かなの次男として生ま
れ、愛知五中から神宮皇學館に進み、皇學館在学中に「潮音」の創刊に参加、太田水
穂に師事した。一九一九年「覇王樹」創刊同人となり、一九二二(大正十一)年、創
立された名古屋短歌会(のちに中部短歌会と改称)が発行していた「短歌」に第三号
から出稿、一九五五年には浅野保のあとを襲って中部短歌会の主幹をつとめた。ま
た、母政子は一九〇七(明治四十)年東京浅草の生まれ、上野高等女学校卒業後、義
兄で彫刻家の毛利教武を介して知りあった「青垣」の大亦観風画伯の勧めにより作歌
を始め、大熊長次郎に師事した。一九三三年「短歌」同人となり、毛利政子名にて同
誌に短歌・随筆を寄せた。一九三六年春日井と結婚。ともに最初の配偶者とは死
別、は二度目の妻とも離別し、三度目の結婚であった。翌三七年長女佐紀子誕生、
そして明くる年の末に長男の建が誕生する。四〇年に次男の郁、四四年には次女の久
仁子が誕生、建は二男二女の第二子にあたる。
建が生まれた布袋町の家は、北側を木曽川が流れる濃尾平野のほぼ中央、名鉄犬山
線布袋駅のすぐ西側に位置していた。妹の森久仁子によれば、「赤い屋根の西洋館
風」の家で、太い根を張ったいちじくの大木が青々と茂る屋敷だったらしい(角川
「短歌」二〇〇四年九月号)。後年、建はこのいちじくの木をくり返し歌い、また散
文にも書いた。当時は江南市にあった滝実業(現滝学園)に国語教諭として奉職
し、鳥居政子との結婚を機に名古屋市千種区(現昭和区)の曙町から布袋に移ってき
たばかりであった。夫婦が新生活を始めた布袋の家には、の先妻である春日井とき
(現尾西市富田出身、一九二七年死去)が生んだ長女四七子と次女須美子、およびと
きの両親である春日井藤十郎・あやをの四人が同居していた。嫁いだばかりの政子に
とっては、義父母の世話のほかに、二人の姉妹の母親の役割が待っていたことにな
る。この時、三十九歳、政子は二十九歳であった。建が生まれたのはその翌々年の
十二月である。時代は前の年に日本が中国と始めた戦争が、政府の不拡大方針にもか
かわらず長期化し、泥沼化の様相を呈し始めていた。この年の四月、第一次近衛文麿
内閣は「支那事変」を背景に、政府が随時国民の権利と財産を制限できる国家総動員
法を公布した。
建が生まれた年の「短歌」一月号を見ると、「南京入城」と題するの歌十数首が
掲載されている。「軍帽にかがやく朝をゆく兵の軒昂としてきびしかりけり」とか、
「今日の日にあぐる兵らが勝鬨(かちどき)を耳には聞きて泣きにけむかも」といった歌
が並んでいる。同年九月号には「勤労団即時」が掲載され、生徒たちを率いて開墾に
従事したことが歌われているので、江南の片田舎にも戦争の足音が着実に忍び寄って
いたのだろう。しかし夫婦の生活には事件らしい事件もなく、幼いいのちの加わった
この年の春も平穏のうちに暮れようとしていた。
なれなれて夫にわが言ふくづれたる言葉はときにさびしく思ふ(政子)
湯あみしてわかやぐ妻は春の夜の添乳けうとく寝入りたらしも()
結婚後二年ほどが経過し、新生活への馴致とそのかすかな寂しさが寡黙に歌われてい
る。互いに見つめ合う夫婦の日常の目は穏やかで愛情に満ちているが、家族を多くか
かえた生活は決して楽なものではなかっただろう。しかも歳晩にはもうひとり家族が
加わろうとしている。ことに乳飲み子のほかに十代の娘を二人もつことになった政子
は、毎日の生活に追われて、おそらく息つく暇もなかったことだろう。建の生まれる
直前の政子の歌に次のような作がある。
いはけなき汝はも姉ぞ今の間にたつぷりと飲め母吾が乳を
乳房ほる吾子背負ひ来てせんなけれ桑畑はすでに月夜こほろぎ
冬には乳離れを強いられるわが子に、今のうちにたっぷりと母乳を飲んでおけと
言っているのである。桑畑に出て良夜の月を仰ぐこの若い母親には、一見、生活して
いくのうえでの迷いや不安は何もないように見える。しかし彼女には、馴染んでゆく
夫との生活にふっと寂しさを覚えたりする内省的なところがあった。普通なら生活の
内に紛れてしまう折々の「詩心」を、この若やいだ「妻」は決して手放すことがな
かったのである。もちろん夫の文学的影響はあっただろう。しかし後年、建が短歌
という形式を自己表現のひとつとして選んだ背景には、父の存在は言うに及ばず、
少女のころから文学に親しんでいたこの母の存在を抜きには語れない。象徴的に言え
ば、そもそも建にはその出生の時から短歌という詩形が、乳幼児の蒙古斑のように身
体に刻印されていたのだ。「父も母も短歌を作っていた」という事実を強調しすぎる
ことは、あるいはこの卓絶した歌人の本質を見誤らせることになるかもしれない。し
かし建の伝記を試みようとする者なら、おそらく誰もがや政子によってこの歌人の
出生が歌い留められているのではないかと考えるだろう。
(後略)
(第2号、2005年3月1日発行)