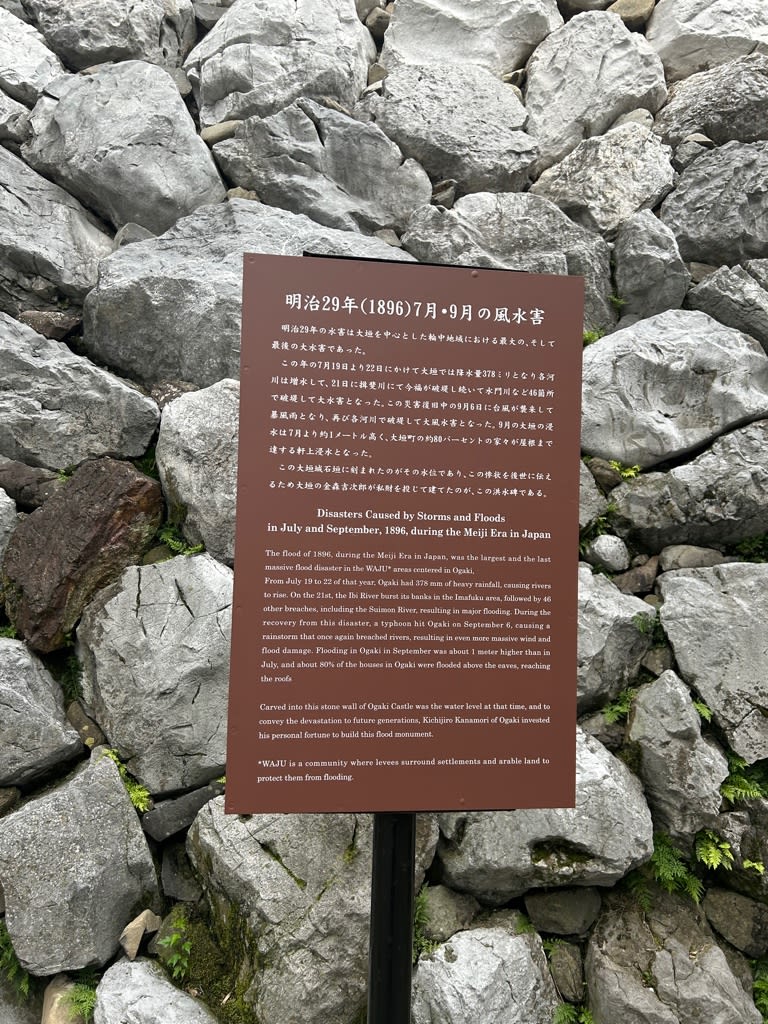2024年07月27日

東京駅前から江戸城に続く、片側4車線の永代通り。

ここが江戸城のメインゲートとなる、大手門。

江戸城の内堀。

平川門は三の丸の正門となっており、大奥に通じる門だったことから、お局門とも呼ばれていたそうです。

北の丸方面から見た、本丸方面の石垣。

清々しい朝とのコラボレーション。

九段下から日本武道館に抜けるには、田安門を通過します。


主郭を囲む堀と比べて防御力がやや劣る堀かなと思ったが、田安門を抜けると巨大な枡形と巨大な渡櫓門。


巨大な渡櫓門の上部は破損のため大正期末期あたりに撤去されたものを、昭和に復旧。

休日の土曜日。
暑い日が続いているので、早朝に散歩も兼ねて江戸城にやってきました。
江戸城は日本で最大の巨大城郭でした。
東京の中心部ということもあり、現在残っている遺構はだいぶ縮小されましたが、それでも圧巻の城郭を至る所で感じることができます。
今日は竹橋方面へ内堀周りを散歩したいと思います。
7時頃に東京駅に到着。

東京駅前から江戸城に続く、片側4車線の永代通り。
現在は日本の中枢なので、見上げるほどの高層ビルが立ち並びます。

ここが江戸城のメインゲートとなる、大手門。
巨大な櫓門が見えます。
大手門から東皇居に入れますが、今日は早朝の為まだ開城していません。
この大手門の石垣は改修の際に伊達政宗が担当したといわれています。

江戸城の内堀。
皇居ランでも使われる内堀周りは約5.5Km。
九段下や、武道館方面まで歩いたらさらに長い距離を誇ります。
やはり日本最大の城郭はスケールが大きいです。

江戸城は高低差があり、大手町駅や東京駅方面にある大手門側は下にあるので、やや石垣も高さは控えめ。

竹橋方面にあるのは平川門。

江戸城は高低差があり、大手町駅や東京駅方面にある大手門側は下にあるので、やや石垣も高さは控えめ。

竹橋方面にあるのは平川門。
こちらも伊達政宗を含めた大名によって造られました。

平川門は三の丸の正門となっており、大奥に通じる門だったことから、お局門とも呼ばれていたそうです。
時間が早いため、こちらもまだ開門していないので外観だけ。

竹橋付近では、他では見ることができないロケーションを拝むことができます。

竹橋付近では、他では見ることができないロケーションを拝むことができます。
水堀と立派な石垣。
そして、その上を通る首都高速道路。
貴重な遺構の上に堂々と高速を通すとは、独創的すぎます。
城好きな方なら目を疑う光景。

北の丸方面から見た、本丸方面の石垣。
こちらは高低差のある江戸城の上の方にあるため、石垣が大手門側よりはるかに高くなっています。


土塀も何も残ってはおりませんが、石垣だけでも十分見惚れてしまうほどの、素晴らしい石垣群を見ることができます。

清々しい朝とのコラボレーション。
大都会の中で見る、美しい三連の高石垣。

北桔橋門と石垣。

北桔橋門と石垣。
江戸城本丸と北の丸を繋ぐ門であり、天守直結の門のため、鉄壁の強固な作りになっているように思えます。

九段下から日本武道館に抜けるには、田安門を通過します。
今ある江戸城の中では最古の建築物であり、重要文化財です。

石垣は綺麗な切込接で、門自体は高麗門。

石垣は綺麗な切込接で、門自体は高麗門。
田安門は寛永13年1636年頃に建てられた門とされています。

田安門の橋から見た堀。
この一帯は内堀ではなく、ダムのような役割を果たした場所なので、石垣ではなく土塁と腰巻きと鉢巻の石垣なのでしょうか。

主郭を囲む堀と比べて防御力がやや劣る堀かなと思ったが、田安門を抜けると巨大な枡形と巨大な渡櫓門。
江戸城のメインゲートではないのに、この迫力。
抜かりの無い防御力。

枡形の石垣も切込接。
江戸城は10年以上の期間で築城されたので、石垣一つとっても場所によって技術が違います。

枡形の石垣で貴重な彫印を発見!

石垣を積んだ職人や担当した武将などが石垣に刻印をすることはよくあることですが、天下の江戸城でこんなに間近に見れるのは貴重。


枡形の石垣で貴重な彫印を発見!

石垣を積んだ職人や担当した武将などが石垣に刻印をすることはよくあることですが、天下の江戸城でこんなに間近に見れるのは貴重。

もう一つ発見!
400年以上の時を超えて、現代に伝わる職人からのメッセージです。
400年以上の時を超えて、現代に伝わる職人からのメッセージです。

巨大な渡櫓門の上部は破損のため大正期末期あたりに撤去されたものを、昭和に復旧。
今はなかなか復元するにも難しい時代となってしまったので、昭和に復元したのはありがたい話。

近くで見ると、上を見上げるほど高いのでより迫力が伝わります。


近くで見ると、上を見上げるほど高いのでより迫力が伝わります。

格式と迫力と守備における実用性。
天守を見るのも素晴らしいのですが、やはり個人的には城門も外すことができない。

裏からは横架材も見え、日本の木造建築の技術を堪能することができます。

裏からは横架材も見え、日本の木造建築の技術を堪能することができます。
これを眺めるだけでも、飽きることがありません。
いつか内部も見てみたい。

裏からのショット。
シンプルにかっこいい。
今では武道館に向かう人やランナーなど多くの方がこの門をくぐります。
今日は朝から二時間ほど歩き、九段下駅より帰宅。
江戸城の外堀外周は14kmの巨大城郭な為、一度で全てをコンプリートするのは難しいので、少しずつ魅力を感じていきたいと思います。
近いうちに、半蔵門から江戸城を周ってみたいと思います。