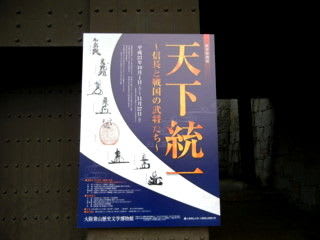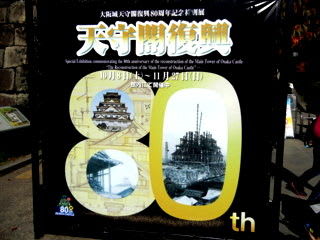岡山城
今回は岡山にやって来ました。

林原美術館 企画展「戦国の雄 池田家」
期間:10月30日)~12月25日
「戦国から江戸時代にかけて活躍し、池田家の築いた武将にまつわる文書・武具・所用の品々を展示し、池田家の系譜を振り返ります。」

池田恒興 肖像画
池田輝政 肖像画
池田利隆 肖像画
池田家の礎を築いた3代の其々の肖像画、現在は恒興が鳥取県立博物館の所蔵で他の2人は林原美術館所蔵となっていますが、もとは3幅1セットで作られたものだそうで今回約350年ぶり一堂に集まったとの事。
池田恒興所用 黒塗黒糸威桶側胴具足
立物のないシンプルな頭形兜。胴は横板矧二枚胴。
恒興は織田信長の家臣であるが母(養徳院)が信長の乳母であり、恒興は信長の乳兄弟という立場であった。
信長の死後は柴田勝家・羽柴秀吉・丹羽長秀と共に四宿老となるが1584年小牧・長久手の戦いで戦死。
伽羅・袴裂
小牧・長久手の戦いで戦死した際に池田恒興が所持していた香木(伽羅)と着用していた小袴の一部(袴裂)と伝わるもの。
池田輝政所用 黒塗黒糸威頭形兜
恒興の兜に似てシンプルであるが、こちらは元々は前立があったようだ。
輝政は恒興の次男であるが、兄も小牧・長久手の戦いで戦死した為に輝政が家督を相続している。
豊臣秀吉の下では大垣・岐阜・吉田城主を務め、関ヶ原合戦後に播磨姫路52万石に加増のうえ転封。
現在見られる姫路城は輝政時代に築城された。
池田利隆所用 陣羽織
背に日輪が付いているが派手な印象ではない。
利隆は輝政の嫡男。関ヶ原合戦、大坂の陣に参戦するが1616年33歳の若さで亡くなっている。
跡は子の光政が継いだものの幼少を理由に鳥取に減転封(42万石→32万石)されている。
池田忠雄追悼歌 池田光政筆
1632年岡山藩主・池田忠雄が亡くなると幕府は家督を継いだ光仲が幼少であり要地岡山を治め難いとし鳥取藩主であった池田光政との国替えを命じた。
この追悼歌は光政が岡山に入る直前に記したもので、幼くして父を亡くしていた光政が叔父である忠雄を父のように慕い、亡くなった事を悲しんでいる様子がうかがえる。
こうして岡山藩池田家が確立されたのですが、どうも岡山での池田家は地味な感じで宇喜多家のが著名なような・・・
姫路城に関しても池田輝政のイメージがあまり無いような感じですが、どうしたもんでしょう・・・