受験生のための『世界史B』 もくじ
↑ここから各項目に入れます。
ヨーロッパ史の時代区分は、古代―中世―近世―近代という順で並んでいます。
「近代」はいつから始まるのか。
この問いはとても難しい問いです。ポピュラーな2社の教科書(山川出版社と、東京書籍)でもその見解は分かれているように感じます。
いろいろ考えたのですが、この場では「どこから近代が始まるのか」よりも、「具体的に何があったのか」のほうが重要だという考えに至り、近世と近代の境目を意図的にあいまいにして書いていこうと思います。
そのへんの区分は、史学史研究者にでも任せることとしましょう←
この項目は「近代ヨーロッパ」という大きなくくりになっていますが、「近代」を最初に始めた(なんか変な言い方ですね)のはヨーロッパでした。ヨーロッパから生まれた「近代」は、いろいろな経路で全世界に波及します。それは、「暗黒の中世」(と、歴史家は言います)を経たヨーロッパがその外部に向けて影響力を行使し、勢力を盛り返していくプロセスでもありました。
さて、血沸き肉躍る「近代ヨーロッパ」のお話を、「スパイス・エイジ」から始めてみましょう。
[想像してごらん、コショウのない世界を]
「ヨーロッパ人はコショウとか、香辛料を欲しがった」
というのは、ちょっと有名な話なんじゃないでしょうか。知らなかった人は、今知ったから大丈夫。
イオンでも平和堂でもどこでもいいんですが、スーパーに行く機会があったら香辛料のコーナーに立ち寄ってみてください。
S&B社から出ている、すごい種類の香辛料が目に入るはずです。
コショウはもちろん、ナツメグ、クローヴなど。
ヨーロッパ人は、香辛料を喉から手が出るほど欲しがりました。それはなぜか?
肉が腐るからですよ。
考えてみてください。15世紀、16世紀ごろの世界には、冷蔵庫なんてありません。
そんなもん、肉なんて速攻で腐るに決まってるじゃん!
でも、食料事情もそんなに豊かじゃないから、腐ってもガマンして食べるしかないんです!!!
そのために、コショウやらなんやらよくわからん粉をいっぱいかけて、臭いをごまかしたんですね。
いやあ……。
おなかいたかったやろな……。
僕も大学1年生のころに食あたりになったことがありますが、あのときは本当に命の危険を感じました(on便座)。
みなさんも気をつけてくださいね。
そんな感じで、香辛料が欲しかったヨーロッパの人々は、香辛料の産地であるアジアを目指します。
その手段は、もちろん船でした。
[ポルトガルの進出]
みなさん、イスラーム世界のところでやった「レコンキスタ」って覚えてますか。
イベリア半島のイスラーム教徒がキリスト教徒に駆逐されたんでしたね。
そのときに成立した国が、ポルトガルだったことはお話しました。
ポルトガルは、「航海王子」の異名をとるエンリケのもとで積極的な海洋進出を進めます。
ところが、これがめちゃくちゃ大変だった。
世界地図を見ながら読んでほしいんですが、当時、アジアへ行くにはアフリカの西岸を通って大陸を迂回し、アラビア半島の南を通る道しかないと思われていました。
でもね、大西洋(ヨーロッパの西側~アフリカの西側の海)って、ものスゴく荒れるんですよ。
誰もがインド航路の開拓に失敗する中ようやく、
バルトロメウ=ディアスという人がアフリカの南端に到達することに成功します(え!? まだ行ってなかったの!?)。
歓喜に打ち震えたディアスはそこを喜望峰と名づけましたとさ(ほんとかどうか知りませんが)。
次いで、ヴァスコ=ダ=ガマが喜望峰を回り、イスラーム(ムスリム)商人の案内のもとに、とうとうインドへの足がかりを得ることに成功しました。
ん!? イスラーム商人?
そうです。
当時のアジアの貿易はイスラーム教徒が独占していたんですね。
ポルトガルはインドのゴアに拠点を得ます(1510年)。
そこを中心にして、イスラーム(ムスリム)商人によって行われていた香辛料貿易に首を突っ込みました。
難しく言うと、既存のアジア市場に参加したということです。
1549年には、ポルトガル人宣教師のひとりが日本の種子島に漂着。これには香辛料貿易ではないとある世界史上のできごとが関わっているのですが、それはまだあとの話。
あ、みなさんこの宣教師の名前知ってます?
フランシスコ=ザビエルっすよ!
こんな縁もあって、ポルトガルは17世紀ごろまで日本と長崎で貿易をします。
そのほか、インドよりさらに東、マラッカをポルトガルは抑え、香辛料の主産地であるモルッカ諸島(ややこしい)をも支配しようとしました。
ここで大事なのは、ポルトガルの商業者は香辛料の現物を欲しがったわけではない、ということです。
何が欲しかったのかというと、香辛料を自国に持ち帰って市場に売ったときに得られるお金がほしかったわけです。
これによって、ポルトガルの首都リスボンは大いに発展します。
<ポルトガルの航路>

このように、まずはポルトガルが香辛料貿易の先陣を切るわけですが。
これを見てムキー! ってなってたのが、同じイベリア半島のスペインでした。
◎今日のポイント
・喜望峰に到達したポルトガル人の名前は?
・インド航路開拓に成功したポルトガル人の名前は?
・ポルトガルが手に入れて貿易の拠点としたインドの都市は?
↑ここから各項目に入れます。
ヨーロッパ史の時代区分は、古代―中世―近世―近代という順で並んでいます。
「近代」はいつから始まるのか。
この問いはとても難しい問いです。ポピュラーな2社の教科書(山川出版社と、東京書籍)でもその見解は分かれているように感じます。
いろいろ考えたのですが、この場では「どこから近代が始まるのか」よりも、「具体的に何があったのか」のほうが重要だという考えに至り、近世と近代の境目を意図的にあいまいにして書いていこうと思います。
そのへんの区分は、史学史研究者にでも任せることとしましょう←
この項目は「近代ヨーロッパ」という大きなくくりになっていますが、「近代」を最初に始めた(なんか変な言い方ですね)のはヨーロッパでした。ヨーロッパから生まれた「近代」は、いろいろな経路で全世界に波及します。それは、「暗黒の中世」(と、歴史家は言います)を経たヨーロッパがその外部に向けて影響力を行使し、勢力を盛り返していくプロセスでもありました。
さて、血沸き肉躍る「近代ヨーロッパ」のお話を、「スパイス・エイジ」から始めてみましょう。
[想像してごらん、コショウのない世界を]
「ヨーロッパ人はコショウとか、香辛料を欲しがった」
というのは、ちょっと有名な話なんじゃないでしょうか。知らなかった人は、今知ったから大丈夫。
イオンでも平和堂でもどこでもいいんですが、スーパーに行く機会があったら香辛料のコーナーに立ち寄ってみてください。
S&B社から出ている、すごい種類の香辛料が目に入るはずです。
コショウはもちろん、ナツメグ、クローヴなど。
ヨーロッパ人は、香辛料を喉から手が出るほど欲しがりました。それはなぜか?
肉が腐るからですよ。
考えてみてください。15世紀、16世紀ごろの世界には、冷蔵庫なんてありません。
そんなもん、肉なんて速攻で腐るに決まってるじゃん!
でも、食料事情もそんなに豊かじゃないから、腐ってもガマンして食べるしかないんです!!!
そのために、コショウやらなんやらよくわからん粉をいっぱいかけて、臭いをごまかしたんですね。
いやあ……。
おなかいたかったやろな……。
僕も大学1年生のころに食あたりになったことがありますが、あのときは本当に命の危険を感じました(on便座)。
みなさんも気をつけてくださいね。
そんな感じで、香辛料が欲しかったヨーロッパの人々は、香辛料の産地であるアジアを目指します。
その手段は、もちろん船でした。
[ポルトガルの進出]
みなさん、イスラーム世界のところでやった「レコンキスタ」って覚えてますか。
イベリア半島のイスラーム教徒がキリスト教徒に駆逐されたんでしたね。
そのときに成立した国が、ポルトガルだったことはお話しました。
ポルトガルは、「航海王子」の異名をとるエンリケのもとで積極的な海洋進出を進めます。
ところが、これがめちゃくちゃ大変だった。
世界地図を見ながら読んでほしいんですが、当時、アジアへ行くにはアフリカの西岸を通って大陸を迂回し、アラビア半島の南を通る道しかないと思われていました。
でもね、大西洋(ヨーロッパの西側~アフリカの西側の海)って、ものスゴく荒れるんですよ。
誰もがインド航路の開拓に失敗する中ようやく、
バルトロメウ=ディアスという人がアフリカの南端に到達することに成功します(え!? まだ行ってなかったの!?)。
歓喜に打ち震えたディアスはそこを喜望峰と名づけましたとさ(ほんとかどうか知りませんが)。
次いで、ヴァスコ=ダ=ガマが喜望峰を回り、イスラーム(ムスリム)商人の案内のもとに、とうとうインドへの足がかりを得ることに成功しました。
ん!? イスラーム商人?
そうです。
当時のアジアの貿易はイスラーム教徒が独占していたんですね。
ポルトガルはインドのゴアに拠点を得ます(1510年)。
そこを中心にして、イスラーム(ムスリム)商人によって行われていた香辛料貿易に首を突っ込みました。
難しく言うと、既存のアジア市場に参加したということです。
1549年には、ポルトガル人宣教師のひとりが日本の種子島に漂着。これには香辛料貿易ではないとある世界史上のできごとが関わっているのですが、それはまだあとの話。
あ、みなさんこの宣教師の名前知ってます?
フランシスコ=ザビエルっすよ!
こんな縁もあって、ポルトガルは17世紀ごろまで日本と長崎で貿易をします。
そのほか、インドよりさらに東、マラッカをポルトガルは抑え、香辛料の主産地であるモルッカ諸島(ややこしい)をも支配しようとしました。
ここで大事なのは、ポルトガルの商業者は香辛料の現物を欲しがったわけではない、ということです。
何が欲しかったのかというと、香辛料を自国に持ち帰って市場に売ったときに得られるお金がほしかったわけです。
これによって、ポルトガルの首都リスボンは大いに発展します。
<ポルトガルの航路>

このように、まずはポルトガルが香辛料貿易の先陣を切るわけですが。
これを見てムキー! ってなってたのが、同じイベリア半島のスペインでした。
◎今日のポイント
・喜望峰に到達したポルトガル人の名前は?
・インド航路開拓に成功したポルトガル人の名前は?
・ポルトガルが手に入れて貿易の拠点としたインドの都市は?










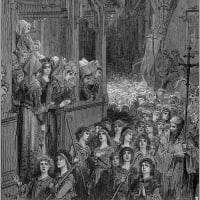


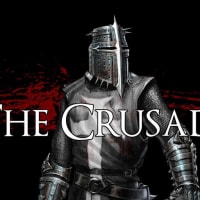

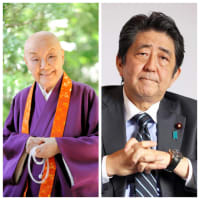
![受験生のための『世界史B』―東アジア世界[(8)前漢の文化と崩壊]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/13/88/e6ff55c7a4d5157036f0bf5482be41b3.jpg)
![受験生のための『世界史B』―中世ヨーロッパ[(3)大帝は焼き肉がお好き]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5a/60/34ff4463e0f35516b385e3c0579be51f.jpg)
![受験生のための『世界史B』―中世ヨーロッパ[(2)あなたは朝シャン派? それとも夜シャン派?]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/59/9c/5fb553a8ca637bc77dae8ab10e798673.jpg)
![受験生のための『世界史B』―中世ヨーロッパ[(1)ヤァ! ヤァ! ヤァ! ゲルマン人がやってきた!]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0c/77/06e8d5c1a63490a28fc419c8cc13b104.jpg)
今後も楽しみにしています!
えーっと、僕はそのように理解しています。
ただ、もしかしたら別の見解があるかもしれませんので、興味があれば調べてみてください。
そして、僕に教えてください←
夏休み中は更新のペースを上げようと思うので、ご期待ください。
最初の記事を読んで感動しました。
僕もうちの学校で近年出てない100点を取って定年が近い先生を喜ばせてあげたいと思っております。
(…せめてなんとか9割は…)
現在学校ではナポレオン流刑(東書)まで授業が終わっています。センター試験は近現代からの出題が多い上ややこしい部分が多いと聞くのでやはり今から時間をかけてやっておくべきでしょうか?少し助言いただけたら嬉しいです。
(授業では時間上、戦後史はやらないそうです)
すごいっすね。100点取ると確かに喜ばれるかもしれませんね。
おれが先生だったら、って考えると、授業の後に質問しに行ったり、オススメの本を訊いたりするのもいいと思います。だいたいの先生は、自分の授業に生徒が興味をもってくれるのが何よりもうれしいんじゃないかな。
そうですねぇ……。
確かに近現代史からの出題は多いですし、教科書をパラパラめくってみても量の違いは圧倒的ですよね笑
僕個人としては、今授業でやっているところの学習に集中するのもいいかと思います。が、予習として教科書を先に読み進めておくのは大いに役立つと思います。
戦後史をやらないっていうのはちょっとシビアかも。
僕が大学生になりたてのころに読んだ、
青木裕司『知識ゼロからの現代史入門』(2002, 幻冬舎)
は、多少記述は偏っているかもしれませんが、受験生が読んでも近現代史の勉強になるし、何よりもおもしろいです。勉強の息抜きに読んでみると、意外に力がつくかもしれません。
早速本屋行って見ます
政経の部分も勉強できるかもですね
だいぶ前の本なので、本屋さんにはないかもしれません。
読みたければ、ネットを駆使することになるかも。
それにしても近現代はかなりごちゃごちゃしてますね
どこの国も革命と専制への逆戻りの繰り返しという…
配点も高いししっかりやっていかなければ…
親切に教えて頂いて感謝です
とぅき…り…れす は入力が面倒なので変更
ウィーン体制ぐらいまではそんな感じですが、時代の流れというのは誰か個人の力によって変えられるものではありませんので、そのうち専制的な国家は廃れていきます。安心してください。
それに代わって成立する「民主的な」国家も、だんだんと問題点を露呈してくるんですけどね。
近代ヨーロッパ史をもっとやっていただきたいです!
また、近代ヨーロッパ史のだいたいの動きがつかめません。
近代ヨーロッパ史よろしくお願いします!!