「受験生のための『世界史B』」 もくじ
↑ここから各項目に入れます。
さて、ここからがギリシアの本領発揮です。
カタカナ地獄です。
今回は長くなりそうなので前置きはナシで。笑
[自然哲学]
イオニア地方って、覚えてますか。
そうです、ペルシア戦争のときにアケメネス朝に反抗した地方ですよね。
あそこに、すごくヒマな人たちがいました。
毎日、広場に集まっては、こんなことをゆっています。
「……おれさ、やっぱ、すべての物体って"水"からできてると思うんだよね」
「いや、そこはあえて"火"じゃね?」
「そういう考え方もあるけど、"数"じゃねぇかな?」
「じゃあ間を取って"空気"とかは?」
「いや、おれはやっぱ"水"だと思うんだよね」
「うん、でもそこはあえて"炎"じゃね?」
「そういう考え方もあるけど、"数"じゃねぇかな?」
「うん、でもむしろ間を取って"大気"では?」
このように、その人たちは万物の根源(=アルケー)が何であるかを延々と議論していたのです。
当時、私たちが今親しんでいるような「科学」というものは存在しませんでした。
「調査」や「実験」といった、何かを調べる際に決して忘れてはいけない過程の確立をみるには、実は中世まで待たなければなりません。
人々は、何かについて調べたいと思ったときは、とりあえず勘で推測したり、もしくは当時信仰されていた「神」を引き合いに出したりして説明するしかなかったのです。
地道に「万物の根源」を推測し、議論し続ける者たちを、やがて人々は「知を愛する者」=「フィロソフィア」=「哲学者」と呼ぶようになりました。
万物の根源を追い求めた人たちを、とくに自然哲学者といいます。
では、代表的な自然哲学者を紹介しましょう!
・タレス「万物の根源は、水だよ、水」
・ピタゴラス「いやいや、数さ。数がモノを言うんだよ」
・デモクリトス「ちがう! 万物はそれ以上分割できない原子からできている!」
……はい。
デモクリトス、スゴいですね。
「正解」ですから(笑)
でも、ほかのふたりがまちがってるからダメとかそういうんではなくて(みんなちがってみんないい)、ここから人間の「叡智」は始まったんだよ、ということです。
[ソクラテスの登場]
さて、自然哲学者がせっせと議論を重ねていたころ、ヘンな輩が登場してきました。
詭弁を操る、ソフィストと呼ばれる人間たちです。
詭弁て、わかりますか?
たとえば。。。
「宇宙人は存在するんだぜ」
「なんでそんなことがわかるんだよ!」
「だって宇宙人がいないという証拠がないから」
「アインシュタインは子どものころ劣等生だった。だから、今劣等生であるおれは実は頭がいい」
といったものです。
議論の相手を説得するために、実はまちがっている論理を用いて議論することを「詭弁」というのです。
詭弁が得意だったソフィストたちの代表は、プロタゴラス。
「万物の尺度は人間」という言葉で有名です。
世の中のやってよいことと悪いことというのは、それぞれの人間の感覚によっていくらでも変わる。
だから、世の中に真理などないと、こう主張したわけです。
そしてギリシアの人々は、彼らを「知者」と呼んで尊敬していたんですね。
小学生のころ、詭弁を使うガキ大将、いませんでしたか?
すごく頭がよく見えたはずです(笑)
で、そんな折。
アテネでのほほんと暮らしていたひとりの男がいました。
彼の名はソクラテス。
怖い奥さんがいることで定評のあった彼は、ある日とことこと近くにあるデルフォイの神殿まで出かけました。
そしてそこで、とんでもないことを巫女さん(神の代理)に言われます。
「ソクラテス、お前めっちゃ頭いいよ」
巫女さんにそんなコトを言われてしまったソクラテスは、萌えました。
「え、ちょ……!
おま、おれめっちゃ頭いいとか……!(//∇//)」
でも、考えてみてください。
ソクラテスはどこにでもいるような平凡な男です。
ちょっと筋肉がムキムキでカオが豚に似ていましたが、まあ、それくらいです。←
どう考えても自分が頭がいいなんて……。
自然哲学者みたいにアルケーを探求しているわけでもないしね。
巫女さん、ウソついたんじゃないの?
巫女さん、ツンデレなんじゃないの?
かくして彼は、「本当に自分は頭がいいのか」を調べる旅に出ます。
ヒマです。
ソクラテスは、当時「知者」と呼ばれていたソフィストに会いました。
プロタゴラスとも対談してます。
彼らと話をするにつれて、始めは半信半疑であったソクラテスは、確信を深めていきました。
重大なことに気がついたのです。
「こいつら、わかってるフリしてるけどほんとは何も知らねぇ……!」
そうです、ソフィストたちは詭弁によって表面上の議論には勝てても、自分たちが議論していることの本質についてはまったく無知であり、しかも自分たちの無知を自覚していなかったのです。
ソクラテスは、膝を打ちました。
「なるへそ!
わかったようなフリをしているソフィストたちなんかより、
自分が無知であることを自覚しているおれのほうが、
"ちょっとだけ"頭がいいってことか!」
いわゆる、「無知の知」です。
もちろん、これはソクラテスひとりに限ったことではありません。
人間だれだって無知です。
でも、その無知を自覚して謙虚に行こうぜ。
彼はそんな結論に達したのでした。
↑ここから各項目に入れます。
さて、ここからがギリシアの本領発揮です。
カタカナ地獄です。
今回は長くなりそうなので前置きはナシで。笑
[自然哲学]
イオニア地方って、覚えてますか。
そうです、ペルシア戦争のときにアケメネス朝に反抗した地方ですよね。
あそこに、すごくヒマな人たちがいました。
毎日、広場に集まっては、こんなことをゆっています。
「……おれさ、やっぱ、すべての物体って"水"からできてると思うんだよね」
「いや、そこはあえて"火"じゃね?」
「そういう考え方もあるけど、"数"じゃねぇかな?」
「じゃあ間を取って"空気"とかは?」
「いや、おれはやっぱ"水"だと思うんだよね」
「うん、でもそこはあえて"炎"じゃね?」
「そういう考え方もあるけど、"数"じゃねぇかな?」
「うん、でもむしろ間を取って"大気"では?」
このように、その人たちは万物の根源(=アルケー)が何であるかを延々と議論していたのです。
当時、私たちが今親しんでいるような「科学」というものは存在しませんでした。
「調査」や「実験」といった、何かを調べる際に決して忘れてはいけない過程の確立をみるには、実は中世まで待たなければなりません。
人々は、何かについて調べたいと思ったときは、とりあえず勘で推測したり、もしくは当時信仰されていた「神」を引き合いに出したりして説明するしかなかったのです。
地道に「万物の根源」を推測し、議論し続ける者たちを、やがて人々は「知を愛する者」=「フィロソフィア」=「哲学者」と呼ぶようになりました。
万物の根源を追い求めた人たちを、とくに自然哲学者といいます。
では、代表的な自然哲学者を紹介しましょう!
・タレス「万物の根源は、水だよ、水」
・ピタゴラス「いやいや、数さ。数がモノを言うんだよ」
・デモクリトス「ちがう! 万物はそれ以上分割できない原子からできている!」
……はい。
デモクリトス、スゴいですね。
「正解」ですから(笑)
でも、ほかのふたりがまちがってるからダメとかそういうんではなくて(みんなちがってみんないい)、ここから人間の「叡智」は始まったんだよ、ということです。
[ソクラテスの登場]
さて、自然哲学者がせっせと議論を重ねていたころ、ヘンな輩が登場してきました。
詭弁を操る、ソフィストと呼ばれる人間たちです。
詭弁て、わかりますか?
たとえば。。。
「宇宙人は存在するんだぜ」
「なんでそんなことがわかるんだよ!」
「だって宇宙人がいないという証拠がないから」
「アインシュタインは子どものころ劣等生だった。だから、今劣等生であるおれは実は頭がいい」
といったものです。
議論の相手を説得するために、実はまちがっている論理を用いて議論することを「詭弁」というのです。
詭弁が得意だったソフィストたちの代表は、プロタゴラス。
「万物の尺度は人間」という言葉で有名です。
世の中のやってよいことと悪いことというのは、それぞれの人間の感覚によっていくらでも変わる。
だから、世の中に真理などないと、こう主張したわけです。
そしてギリシアの人々は、彼らを「知者」と呼んで尊敬していたんですね。
小学生のころ、詭弁を使うガキ大将、いませんでしたか?
すごく頭がよく見えたはずです(笑)
で、そんな折。
アテネでのほほんと暮らしていたひとりの男がいました。
彼の名はソクラテス。
怖い奥さんがいることで定評のあった彼は、ある日とことこと近くにあるデルフォイの神殿まで出かけました。
そしてそこで、とんでもないことを巫女さん(神の代理)に言われます。
「ソクラテス、お前めっちゃ頭いいよ」
巫女さんにそんなコトを言われてしまったソクラテスは、萌えました。
「え、ちょ……!
おま、おれめっちゃ頭いいとか……!(//∇//)」
でも、考えてみてください。
ソクラテスはどこにでもいるような平凡な男です。
ちょっと筋肉がムキムキでカオが豚に似ていましたが、まあ、それくらいです。←
どう考えても自分が頭がいいなんて……。
自然哲学者みたいにアルケーを探求しているわけでもないしね。
巫女さん、ウソついたんじゃないの?
巫女さん、ツンデレなんじゃないの?
かくして彼は、「本当に自分は頭がいいのか」を調べる旅に出ます。
ヒマです。
ソクラテスは、当時「知者」と呼ばれていたソフィストに会いました。
プロタゴラスとも対談してます。
彼らと話をするにつれて、始めは半信半疑であったソクラテスは、確信を深めていきました。
重大なことに気がついたのです。
「こいつら、わかってるフリしてるけどほんとは何も知らねぇ……!」
そうです、ソフィストたちは詭弁によって表面上の議論には勝てても、自分たちが議論していることの本質についてはまったく無知であり、しかも自分たちの無知を自覚していなかったのです。
ソクラテスは、膝を打ちました。
「なるへそ!
わかったようなフリをしているソフィストたちなんかより、
自分が無知であることを自覚しているおれのほうが、
"ちょっとだけ"頭がいいってことか!」
いわゆる、「無知の知」です。
もちろん、これはソクラテスひとりに限ったことではありません。
人間だれだって無知です。
でも、その無知を自覚して謙虚に行こうぜ。
彼はそんな結論に達したのでした。










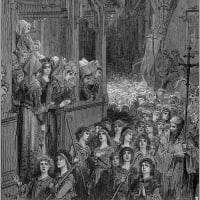


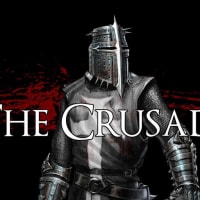

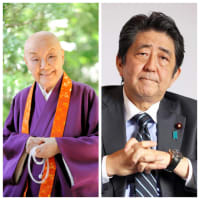
![受験生のための『世界史B』―東アジア世界[(8)前漢の文化と崩壊]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/13/88/e6ff55c7a4d5157036f0bf5482be41b3.jpg)
![受験生のための『世界史B』―中世ヨーロッパ[(3)大帝は焼き肉がお好き]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5a/60/34ff4463e0f35516b385e3c0579be51f.jpg)
![受験生のための『世界史B』―中世ヨーロッパ[(2)あなたは朝シャン派? それとも夜シャン派?]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/59/9c/5fb553a8ca637bc77dae8ab10e798673.jpg)
![受験生のための『世界史B』―中世ヨーロッパ[(1)ヤァ! ヤァ! ヤァ! ゲルマン人がやってきた!]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0c/77/06e8d5c1a63490a28fc419c8cc13b104.jpg)
参考書を開けば学ぶべきことがたくさんある私は何をやってるんだろうか(汗)
今回の記事に考えさせられてしまいました(-_-;)勉強しよっと。
そして!記事とは関係ないのですが!!
一緒にBECKを見に行った友達が「ギターがかっこいい着信音が欲しい!!」と言って、ショックオブザライトニングをダウンロードしていました!!!メールが来たら「かむいーんかむあーうと♪」です。感動!!
と思っていたのでナイスタイミングです。笑
うん、でもまあ、人間て参考書に書いてあるようなことはいやがって、誰に訊いてもわからないようなことを自分で勝手に調べたりしたくなる生き物な気もしますね。
なるほど。
あの曲はオアシスにしては珍しいギターの使い方してますね。
ドラムソロもカッコいいですが。
かにーかまーつなー♪笑
大分前の記事なのでこのコメントはとどかないでしょうか…
初めて世界史でこんなに笑いました(^m^)
明日、テスト頑張ります!! ありがとうございました。
閲覧ありがとうございます。
いま読み返してみましたが、この記事は自分でもちょっとお気に入りかもしれません(笑)
テストがんばれ!
ほんとにありがとうございます。
お返事くれたらうれしいです!!