立山三山、ようやく完結編。毎度毎度、長々しいお話で。
[ 2015年9月末の山行レポートです ]
これまでのレポート(1)→ (2)→
(2)→ (3)→
(3)→ (4)→
(4)→
一ノ越山荘の山小屋レポート→ (作成中)
(作成中)
雷鳥沢ヒュッテの山小屋レポート→ (作成中)
(作成中)
一日目:立山駅[ケーブルカー]→美女平[バス]→室堂ターミナル→浄土山(北峰・南峰)→一ノ越山荘[宿泊]
二日目:一ノ越山荘→雄山→大汝山→富士ノ折立→真砂岳→別山(南峰・北峰)→別山乗越→雷鳥沢ヒュッテ[宿泊]
三日目:雷鳥沢ヒュッテ→ミクリガ池→室堂ターミナル[バス]→弥陀ヶ原[バス]→美女平[ケーブルカー]→立山駅
三 日 目
雷鳥沢ヒュッテに宿泊した翌日の朝。
朝風呂であたたまったあと、朝食を自炊して食べてから6時過ぎに小屋を出立しました。
[雷鳥沢キャンプ場と立山]

今日の朝は昨日と違って、いい天気です。よかったー
室堂周辺は東の立山に太陽を隔たれているので、日の出時間を過ぎてもまだ日陰。
雷鳥沢から室堂平までは、緩やかな上りが続きます。
きれいに整備された階段状の道を、ゆっくりゆっくり登りました。
有毒ガスで立ち入り禁止区域になっている地獄谷を通過し、血の池を通って、
みくりが池経由で室堂ターミナル駅を目指しました。
[血の池]

池塘が点在した湿地帯。『火口跡が池になったもので、酸化鉄が多く含まれているため赤い色をしている』とな。光の関係で今はその赤さがわかりにくいけど、たしかにちょっと茶褐色に見えます。
ここは晴れた日に太陽の光を浴びたら、もっときれいな色彩を見せてくれるんだろうな。
ゆっくり歩いてる間に、遅いご来光の時間がやってまいりました。

時刻はちょうど7時。
なんとまるで狙ったかのように、立山の上から昇る朝日です。すてきすぎる...

[みくりが池と立山・浄土山]

[朝のみくりが池]

室堂平から西の方角に日本海と街が見えます。あれはどの辺なのかなぁ
きっと向こうからも、室堂が見えてるんですね。
[立山とチングルマの草紅葉]

夏のお花の季節に、またここに来よう。その時はどんな色を見せてくれるのかな...
室堂バスターミナルから始発の便に乗りました。
(すでに結構並んでる人がいたので、シーズン中は平日でものんびりしてると出遅れるかもです)
弥陀ヶ原や天狗平で下りられる弥陀ヶ原・天狗平途中下車専用の便に間違えないように乗車して、弥陀ヶ原ホテルの前にある「弥陀ヶ原バス停」で降りました。
[弥陀ヶ原バス停]

昨晩は弥陀ヶ原周辺で宿泊した人、同じ行程の人などがたくさんいました。この辺で散策して高原ホテルで宿泊する観光旅行もよさそうだ、高齢になって山に登れなくなった頃にのんびりやってみたい、などと、健康で長生きできるという前提で夢を描いてみたりする。
[弥陀ヶ原散策マップの案内板]

プカプカはバス停を起点に外回りコースを"9"の字型に周回しました。
一昨日から今日までを同じ行程で歩いてきたという、重そうなカメラ機材を抱えたおじさんと、雷鳥沢を出発した頃から抜きつ抜かれつ、何かと顔を合わす機会があり、ちょこちょこと会話していたのですが、この弥陀ヶ原までの行程も同じだったため、いつしかなんか親しみをおぼえた我々は、会うたびに「おっ(^o^)」て感じに。
広々した湿原ですね~ 尾瀬を思わせるような思わせないような…
笹が多いので、湿原は少しずつ土化しはじめているのがわかります。



似たような写真ばっかりだけど、大好きな池塘がたくさん点在してます。
空を映して輝く水面もあれば、奥深さを感じる澄んだ水面もあったりして。
池塘を見ていると、いろんな妄想がふくらんでしまう。
別の次元や宇宙につながる窓に見える。
この窓はどこへつながっているのかな。
今見えている空はどこの空?
この向こうにはどんな世界が広がっているのかしら。
すっかり黄金色の湿原も、夏はさわやかな緑色をしてたんですよね。
大好きな田んぼを思わせる、緑の湿原。
ぜひぜひ、見てみたい!きっとお花もたくさん咲いてるんだろうなぁ
想像するだけでうっとりだわい

秋枯れているようで、まだ少しお花の名残も見られました。
[イワショウブの蒴果(チシマゼキショウ科)]


秋の湿原でおなじみですね。この赤い果実が花のようできれいなんですよねー
外回りコースでは南側のルートで樹林帯を通るんですが、そっちには秋の花がまだ咲き残ってました。
今回出会ったお花や果実(種)はこんな感じです。
アキノキリンソウ(キク科)/ワタスゲ(カヤツリグサ科)

ワレモコウ(バラ科)/ゴマナ(キク科)
オヤマリンドウ(リンドウ科)花は上部にのみついていたのでエゾリンドウではなくオヤマリンドウかな/タテヤマウツボグサ(シソ科)

ナナカマドの果実(バラ科)/シシウドかミヤマシシウドの果実(セリ科)
大日連峰の尾根
とってもすてき。いつかあそこを歩きたい。
外回りコースを進んでいくとT字路に突き当たりました。
その先にどこまでもどこまでも遠くつづく広い湿原ですが、
弥陀ヶ原はほんの一部しか人が歩けないようになっています。
2012年からラムサール条約に登録されたそうです。
美しい自然を守るためなんだから、これでいいんだよね。
人が踏み入れない場所に思いをはせる楽しみもあります。
富山湾も見えました。
このT字路には案内板があって、そこから右に分けて行くと一の谷・天狗平に行けるらしい。
天狗平と弥陀ヶ原の間には沢が通っているから、一度谷まで下りて登り直すため、結構険しいと教えてもらっていたので、どんな感じか様子を見てみることにしました。
案内板には「この先上級者向け登山道」と書いてあります。
確かに進んで見ると道の様子がガラリと変わって、足元はごろついた岩の隙間がひどくぬかるんで、靴底が滑りやすくなって難儀します。木道を気楽に歩く延長ではなく、ここから先は"登山道"でした。
沢に向かって下りるにつれて木の背丈も高くなって、湿原風景を楽しむ感じでもなくなってしまったので、沢に着いてからまた来た道を引き返しました。
さっきまでよく顔を合わせていたおじさんと、ここでもまた再会。
よく立山の紅葉を撮りにくるそうですが、彼が言うことには一昨日前の方が黄葉が鮮やかできれいだった、2日経過した間の朝晩の冷え込みで、黄葉が茶褐色に変色したため、色の鮮度が少し落ちたそうです。
確かに、初日のバスの中から見えていた「明るい黄色」が、さっきからなかなか見つからなかったんだな。言われてみると黄葉の樹木は葉が縮れてるのが目立ちました。
紅葉・黄葉って一日二日で急激に変化すること、よくありますよね。
でも赤い葉っぱは今がまさに見頃とばかりにきれいでした。
葉っぱがみずみずしいまま赤くなっていて、シミや縮れがないのは雷鳥沢ルートの紅葉と同じです。
立山ってライブカメラで確認する限りでは晴れの日が多い気がするので、日照時間が長い分、紅葉によい条件が続くのかなー、なんて仮説…


おいしそうな紅葉ですなぁ
[南側の樹林帯の様子]

ここを通っている間は湿原も眺められず、山も見えず、また木道が一本で狭いため相互通行のたびに道を譲り合う駆け引きが発生して、(アジア系の観光者風の人は大抵、道を譲ろうとしないで堂々直行してくる。なぜじゃ)なんか面倒でした。
これなら周回ではなく湿原をピストンした方が楽しそう。
O字型に周回すると最後まで樹林帯がつづくので、途中で湿原コースに戻ったため、"9字型"になった次第です。
ほらこっちの方が開放的^^
少し時間の余裕があったので、弥陀ヶ原バス停のすぐ前にある弥陀ヶ原ホテルでお茶をすることにしました。
コーヒーとアップルパイのケーキセットを注文し、眺めのいい席で外を眺めながら、まったり
この三日間の充実した行程を振り返って満足でした。
[弥陀ヶ原ホテルのケーキセット]

こういう文明的(?)なもののありがたみを心底感じるのも、
山で質素なごはん(自炊)ばかり食べて過ごしたからなんですな。
山を下りると無償に油もの(コロッケとか)が食べたくなったり、
タンパク質がほしくなって牛乳を飲んだりします。
アイスとかいいっすねぇ
バスに乗って、ケーブルカーに乗り換えて、ようやく車まで戻ることができました。
立山駅内の売店にアジアンのおサレかわいいニット帽がたくさん売られていたので、
アジアン好きのプカプカはついついそこでお買い物 。
。
次の山にはこれをかぶっていこう。
帰り道、高速道路にはすぐに乗らずにしばらく下道を走っていきました。
日暮れ前にようやく乗った高速のSAから眺めたきれいな夕焼け空。
さっきまでいた場所からも、昨日いた稜線からも、この空が見えているんだろうか。
いつか、あの向こう側へ。
(おしまい)
これまでのレポート(1)→ (2)→
(2)→ (3)→
(3)→ (4)→
(4)→
一ノ越山荘の山小屋レポート→ (作成中)
(作成中)
雷鳥沢ヒュッテの山小屋レポート→ (作成中)
(作成中)

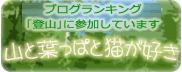







![北アルプス展望の山歩き*(旧)白馬ハイランドスキー場 [2015年12月]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/27/6c/39aa46e3e9e4b00d4c70c9d1b5fca2b3.jpg)
![一切経山(後編)コバイケイソウまつり[2013年7月]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/55/61/d9115fcbba1ad99fbd06984b16342aff.jpg)
![一切経山(前編)ふわふわ萌えの花めぐり[2013年7月]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/36/10/5e96c39af9ae603ca30e15b71e0e25f0.jpg)





