
庭の花梨(かりん)の木に
 つぼみ
つぼみ が登場しました。
が登場しました。
昨日、開花が始まったアーモンドの花の撮影をしたときに、花梨のつぼみに気づいたのです。
花梨の花は木瓜(ぼけ)より一回りほど大きい花なのですが、つぼみさんはまだまだ小さくて
開花までは、もうしばらく時間がかかりそうです。
 | |
 | |
 |
 |  |  |
先日、とんびさんがブログの記事の中で...
「つぼみの漢字には、蕾と莟があるけれど、一般的には蕾を使うことが多い。」と説明をしてくださっていて
なるほど、そう言われてみればそのとおり...と思いました。
とんびさんは、個人的には「莟」の文字がお好きだそうです。
蕾と莟には何か違いがあるのか、気になったので調べてみました。

「つぼみ」と読む漢字は「3つ」あるのだそうです。
「莟」は、まだ硬いつぼみ → 「蓓」は、ふっくらしてきたつぼみ → 「蕾」は、もう開花する寸前のつぼみ
ということですよ。
開花しそうなつぼみを表すのに「雷」の文字が入っているのは、落雷の衝撃でつぼみが開くことがあるから...
という説があるそうです。
もしかして和歌の世界などでは、きちんと使い分けをしているのでしょうか...
ちなみに、赤ちゃんに名前を付けるときに使える漢字は「蕾」だけだそうです。
私は「つぼみ」と、ひらがなで書くのが1番好きです。
もう1つ、封筒を閉じてから書く封字は、お相手の手許に届くまで途中で他の人に開封されていないという証
なのだそうですが、一般的には「〆」が使われています。「締」の略字とのこと。
何種類かある封字の中に、女性だけに使われていたという文字があるのです。
その文字が「蕾」と「莟」。
「つぼむ」という意味から手紙を閉じることに使われていたそうです。
ひらがなで「つぼみ」と書くこともあるそうで、その場合は縦書き限定で...だそうです。
女性から、そんな封字の書かれたお手紙が届いたら、男性はどきっとしてしまいそう
などと余計なことを考えてしまいましたよ。
私はもう長いこと、プライベートなお便りにはお花のシールを貼っています。
封字を記す習慣は、少なくとも私にはもうほとんどないですね。
「つぼみ」の漢字を調べてみたら...思いがけずに「封字」のお勉強ができてしまいました。
結婚式の招待状に「寿」のシールが貼ってあるのは、「〆」では「☓(ばつ)」のようにも見えてしまうから
なのだそうです。
同じ理由で、お祝い事や祝賀会の招待状には「賀」を使うそうです。

新型コロナウイルス禍の収束の日を、1日も早く迎えることができますように...

 花梨の花について:アーモンドはバラ科サクラ属、花梨はバラ科ボケ属だそうですよ。
花梨の花について:アーモンドはバラ科サクラ属、花梨はバラ科ボケ属だそうですよ。


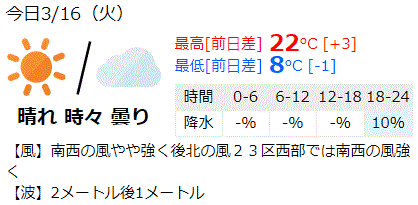


















何か良さそうなことを言われた時に、無難な返しとして『勉強になります』という常套句があります。
今回は心底から気持ちよく言わせていただきます。
「勉強になりました」。
しっかり区別して使いたいと思います。
自分のブログが先ほどようやく書けまして、そこにも『莟』を使いましたが、Passyさんのこの記事を先に読ませてもらっていたら、『蓓』とすべきだったかも知れません。
とんびさんのブログから、たくさんの刺激を頂いている私です。
椿の花の蜜を見つけたときも、沈丁花の小枝を活けた思い出の蜂蜜の器のことを語ったときも、
そして、花梨の愛らしいつぼみを見つけたときも...
ふと、とんびさんの言葉が胸をよぎりました。
我が家の花梨の莟さんが、蕾さんへと成長していく様子を眺めてみたいと思っています。
「莟」の文字を見ていると、♪芽が出てふくらんで♪の手遊びで、両手を合わせて花が膨らむ様子を表す子どもの手が目に浮かびます。
私の方こそ、いつも「勉強になります」