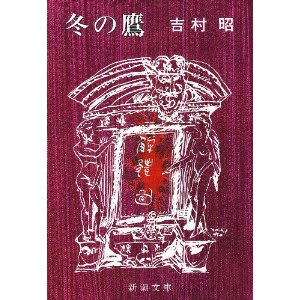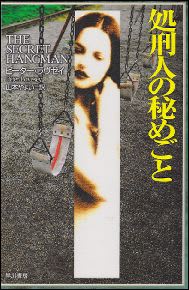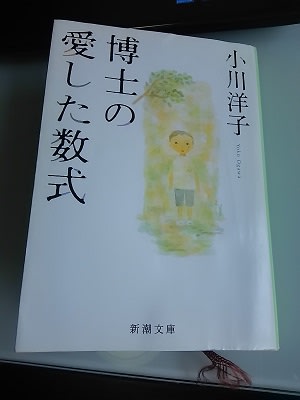
この本は、2004年の第1回「本屋大賞」受賞作で、当時図書館に予約すると、順番待ちが半年くらいだった。
たまたま友達が別の図書館で借りていて、期限までの3日間くらいの間に又借りのような形で貸してもらった。
とても面白くて、興味深くて、博士がいとしくて、夢中で読んだ。
それから12年経って、古本屋で93円で売っていた。93円!ありがたく購入して読み始めた。
ストーリーは知っているのだけれど、初めて読んだ時と同じようにぐいぐい引き込まれる。
事故で脳に障害を負い、記憶が80分しか持たない博士が、どう表現していいかわからないのだけれど、
圧倒的な力で胸を打つ感じ。
気の毒というか、切ないというか。
「君の靴のサイズはいくつかね」
「24です」
「ほお、実に潔い数字だ。4の階乗だ」
「カイジョウとは何でしょうか」
「1から4までの自然数を全部掛け合わせると24になる」
(つまり、1x2x3x4=24)
「君の電話番号は何番かね」
「576の1455です」
「5761455だって?素晴らしいじゃないか。1億までの間に存在する素数の個数にひとしいとは」
のような感じで話が始まる。
家政婦の主人公が「28の約数を足すと、28になる」という事を発見したと博士に報告すると、
それは、完全数というものだという。
28=1+2+4+7+14 という事。
1番小さな完全数は、6。 6=1+2+3
完全数は、6、28の次は496、次は8128、次は33550336、次は8589869056・・・・
我が家の春たんは、誕生日が2月28日。完全数だ。
春たんのママは、11月6日。完全数!
春たんのパパは、3月5日。完全数じゃない。しかし、しかしである。
読み進めていくと、今度は素数の話になる。素数は約数を持たない数である。
「この世で博士が最も愛したのは、素数だった」
2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53、・・・・・・
「17,19とか41,43とか、続きの奇数が二つとも素数のところがありますね」
「うん、なかなかいい指摘だね。双子素数だよ」
双子素数!春たんのパパの誕生日、3月5日の3と5は双子素数だった。素晴らしい。
春たん一家に知らせなければ。
とまあ、こんな具合に、読んでいる。
この後、楽しいだけではない展開になっていくのである。どんな内容だったかうっすらしか覚えていないのだが。










 吉村昭「アメリカ彦蔵」1999年10月
吉村昭「アメリカ彦蔵」1999年10月