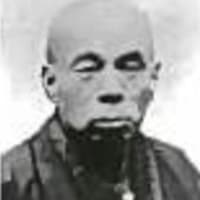藤﨑宗兵衛光重は近江国日野(現在の滋賀県現蒲生郡日野町)の出身の近江商人。
その類い稀なる商才と目利き力によって全国に名を馳せた“近江商人”の家に生まれ育った。
日野は近江の中でも「清酒」の製造販売を得意とした地域。彼らは日野商人と呼ばれ、活躍の場所を関東へと広げていった。
その一派である「十一屋」を屋号に、初代・宗兵衛が「藤﨑摠兵衛商店」を江戸五街道のひとつ、中山道に創業した。 設立したのは享保13年(1728年)のこと。 以来、醸造と行商を営みながら、中山道を中心に日本酒文化を広げることに尽力した。
創業者・藤﨑宗兵衛光重は、滋賀県猪田村(現蒲生郡日野町猫田)の出身。 その類い稀なる商才と目利き力によって全国に名を馳せた“近江商人”の家に生まれ、育った。
近江商人とひとくくりに称されることが多いが、実は、湖東、八幡、高島、日野などの地域ごとに、それぞれが得意とする商品が異なるものだった。
その類い稀なる商才と目利き力によって全国に名を馳せた“近江商人”の家に生まれ育った。
日野は近江の中でも「清酒」の製造販売を得意とした地域。彼らは日野商人と呼ばれ、活躍の場所を関東へと広げていった。
その一派である「十一屋」を屋号に、初代・宗兵衛が「藤﨑摠兵衛商店」を江戸五街道のひとつ、中山道に創業した。 設立したのは享保13年(1728年)のこと。 以来、醸造と行商を営みながら、中山道を中心に日本酒文化を広げることに尽力した。
創業者・藤﨑宗兵衛光重は、滋賀県猪田村(現蒲生郡日野町猫田)の出身。 その類い稀なる商才と目利き力によって全国に名を馳せた“近江商人”の家に生まれ、育った。
近江商人とひとくくりに称されることが多いが、実は、湖東、八幡、高島、日野などの地域ごとに、それぞれが得意とする商品が異なるものだった。
藤﨑家のあった日野地域の主力商品は「清酒」。日野商人は、卸・小売業に特化せず、北関東地方の街道沿いを中心に行商を重ねながら徐々に商店を設置。主に清酒の製造・販売を行った。
当時の日野地域には2つのグループがあり、
1つは村の中心部に分家別家関係の同族で形成された「日野屋」。もう1つは、西方にある北比都佐村(きたひつさむら)の「十一屋」。こちらは藤﨑家、田中家、北西家などの十一の地縁グループが共通の屋号を使用し、組織化された。
日野屋は埼玉県東部から栃木県にかけて商売を展開。対して、十一屋は群馬県から埼玉県北西部にかけての中山道沿いに進出。それぞれに経営手腕を発揮し、発展をしました。
近江商人の心得「三方よし」の精神と、十一屋・藤﨑摠兵衛が培ってきた「技で磨き 心で醸す」日本酒造りを現代に繋ぎ、藤﨑摠兵衛商店は群馬県長瀞に今日も存在している。また、藤﨑摠兵衛商店は仙台にも進出し成功している。加えて近江日野のトップバッターであった豪商中井源左衛門が取り入れていた腹式簿記も取り入れていた。
尚、仙台の「藤崎デパート」は文政2年(1819年)に、初代藤﨑三郎助が衣類卸商の父から独立し、太物商(木綿商)を創業とあり、藤﨑三郎助は記録は残っていないが近江日野の関係者ではないかと言われている。
藤﨑宗兵衛は関東に進出後、100年近く後のことであるが近江日野には藤崎性もあることから近江商人の末裔はほぼ間違いないのではないだろうか。中井源左衛門の仙台での活躍は後に続く者に影響を与えた。
当時の日野地域には2つのグループがあり、
1つは村の中心部に分家別家関係の同族で形成された「日野屋」。もう1つは、西方にある北比都佐村(きたひつさむら)の「十一屋」。こちらは藤﨑家、田中家、北西家などの十一の地縁グループが共通の屋号を使用し、組織化された。
日野屋は埼玉県東部から栃木県にかけて商売を展開。対して、十一屋は群馬県から埼玉県北西部にかけての中山道沿いに進出。それぞれに経営手腕を発揮し、発展をしました。
近江商人の心得「三方よし」の精神と、十一屋・藤﨑摠兵衛が培ってきた「技で磨き 心で醸す」日本酒造りを現代に繋ぎ、藤﨑摠兵衛商店は群馬県長瀞に今日も存在している。また、藤﨑摠兵衛商店は仙台にも進出し成功している。加えて近江日野のトップバッターであった豪商中井源左衛門が取り入れていた腹式簿記も取り入れていた。
尚、仙台の「藤崎デパート」は文政2年(1819年)に、初代藤﨑三郎助が衣類卸商の父から独立し、太物商(木綿商)を創業とあり、藤﨑三郎助は記録は残っていないが近江日野の関係者ではないかと言われている。
藤﨑宗兵衛は関東に進出後、100年近く後のことであるが近江日野には藤崎性もあることから近江商人の末裔はほぼ間違いないのではないだろうか。中井源左衛門の仙台での活躍は後に続く者に影響を与えた。
藤崎