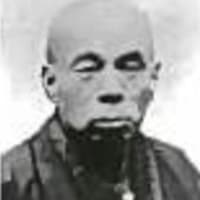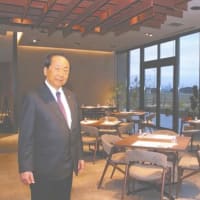浅井 亮政(あざい すけまさ)、延徳3年(1491年)ー天文11年(1542年)は、戦国時代の武将。北近江の国人領主。浅井氏の初代当主。浅井長政の祖父。
延徳3年(1491年)、北近江の国人である浅井氏の庶流蔵人家・浅井直種の子として誕生。幼年期は定かではないが、浅井氏嫡流で従兄弟浅井直政の娘蔵屋と結婚し、嫡流を継承している。

「亮政」が家督を継承した頃、浅井氏は北近江半国の守護・京極氏の被官であった。この時期の京極氏の当主は「高清」であったが、高清が家督を次男「高吉」に譲る意向を示したことで、お家騒動が発生した。
この時、亮政は近江国衆浅見貞則とともに、「高清」の長男「高延」を後継者に推し、高清と対立。浅見貞則と浅井亮政は主君高清、高吉、そして高吉を推す上坂信光を尾張へと追い出した。これ以後、京極氏は国人一揆が主導することになり亮政はその中心的役割を担ったが、浅見貞則が専横を極めたためこれを追い出し、ついには国人一揆の盟主となって京極家中における実権を掌握した。
こうして近江の江北(伊香、東浅井、坂田の三郡)における勢力を築いた「浅井亮政」であったが、亮政の勢力拡大と共に南近江の守護佐々木六角定頼と対立するようになる。
六角氏は近江源氏佐々木氏の嫡流であり、京極氏の本家筋にあたる存在で、この時期は足利将軍家を庇護して室町幕府へ関与するなど、勢力を強めていた。もともと近江守護職であった六角氏との対立は、亮政にとって不利であり、度々侵攻を許すことになったが、配下となった国人層を掌握してこうした侵攻をかろうじてしのいだ。
また一方で、亮政によって傀儡化した京極氏であったが、亮政の専横に不満を募らせた京極高延が父・高清と和解し、上坂氏をはじめとする反亮政派の国人衆らとともに亮政と対立するようになった。これに対し亮政は、佐々木六角氏との対立もある中、更に京極氏と争う余力はなかったため、天文3年(1534年)に京極父子と和解している。
しかし、天文10年(1541年)、再び「京極高延」が亮政に反旗を翻した。亮政は京極氏との対立を解決しないまま、翌天文11年(1542年)1月6日に死去した。享年52。
死後、嫡男「久政」と婿養子の田屋明政が家督継承を巡って争うようになり、明政が京極高延と結んで久政を攻めたため、「久政」は六角氏へ臣従している。
子孫
亮政は5男5女を儲けており、また婿養子として一族の田屋明政がいる。家督を相続したのは長男久政である。男系子孫は孫・長政が織田信長に滅ぼされたことにより絶えている。しかし、久政の娘マリアが京極高吉に嫁いだため、亮政が終生争った京極氏として女系子孫が現代に伝わっている。また、亮政の曾孫にあたる「江」の子孫は彼女の子にあたる3代将軍「徳川家光」の曾孫・徳川家継まで江戸幕府の将軍職を世襲し、浅井の血を残した。このため、現代の皇室も末裔にあたる(浅井長政#末裔あるいは崇源院#系譜を参照のこと)。
男子
浅井久政 - 生母尼子馨庵
浅井高政 - 生母尼子馨庵
浅井政弘 - 新四郎、生母蔵屋
浅井秀政 - 長頼、生母不詳
山城守 - 名・生母不詳、
婿養子:田屋明政 - 亮政の娘海津殿を妻とする。
女子
海津殿 - 田屋明政室。生母蔵屋
松市御料 - 三田村定頼室
実名不詳 - 浅井忠種室、生母尼子馨庵
千代鶴 - 六角宗能室
近江の方 - 斎藤義龍室
※『六角佐々木氏系図略』・「浅井過去帳」より