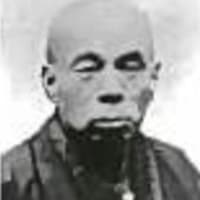昌安見久尼(しょうあんけんきゅうに、天文7年(1538年) - 天正13年(1585年))は、戦国時代の女性。名は阿久(あく)であり、昌安見久尼は戒名。
人物
浅井長政の父浅井久政の長女であるが、庶子のため祖父・浅井亮政の養女となった。生母は浅井亮政の侍女と伝わるが定かではない。浅井久政と正室井口殿(小野殿)が嫁ぐ前のことである。兄弟姉妹に浅井長政、京極マリアら多数。
母と共に平野郷の「実宰院」(当時は実西庵)(長浜市平塚町)に移り住み、母の死後庵主となる。
寺伝によれば、彼女は身長5尺8寸(176cm)・体重28貫(105kg)の大女であったため、嫁入りをあきらめて、天文11年(1542年)に出家し、小谷城の南4kmの平塚村に庵を建てて移住し、実西庵の開基者となったとされる。
しかし、一方でこの実西庵の出来事は、阿久の母は浅井亮政の侍女であり、阿古(小野殿・井口殿)、後の浅井久政の正室の実家である有力者井口氏に対する配慮だったとも言われ、阿久6歳の時のことである。
豊臣の治世になっても秀吉によって実西庵に庵料として50石の田畑を与えられ、三霊殿を創営して浅井三代を祀ったという。江戸時代に入っても秀吉の与えた50石は徳川秀忠の御朱印状で認められている。このような配慮は浅井家3姉妹に繋がる寺院であったためだろうか。
実宰院に伝わる位牌によれば、天正13年(1585年)47歳で没している。長浜市「実宰院」本堂には江戸時代中期に作られた昌安見久尼の木造が安置されている。
逸話
実宰院境内にある花一輪に2個ずつ実をつけるという双子の梅は、阿久が出家するときに弟の長政が贈ったものと伝えられている。
小谷落城(小谷城の戦い)時の浅井三姉妹(茶々・初・江(お督))について、通説ではお市の方と共に織田軍が身柄を引き取ったとされるが、長政は落城に先立って4人を実西庵に逃がし、阿久に養育を依頼したとの伝承がある。
その後、実西庵にやって来た織田軍の残党狩りに対して、阿久はとっさに自身の法衣の中に浅井三姉妹を匿ったと伝えられている。この逸話を裏付ける史料はないものの、実宰院に伝わる慶長2年(1597年)5月1日付けの豊臣家奉行連署状が実西庵と豊臣秀吉に深い繋がりがあったことを示しており、秀吉から庵料を与えられたことと併せて、茶々との関係を暗示していると言われている。
しかし、浅井三姉妹を保護したのは小谷落城落城時ではなく、茶々たちの居場所が不明な時期、柴田勝家の越前北ノ庄落城落城後ではないかとの説も有力である。
<Wikipedia、「近江戦国の女たち」引用>