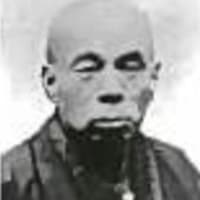「近江商人」と「三方よし」精神
近江商人の出身地は、湖西(高島)、近江八幡、日野、湖東(五個荘、豊郷、湖北など、現在の滋賀県である。近江商人が歴史に登場するのは、売買や貨幣の普及が盛んになる鎌倉時代に遡るとされている。
近江商人の出身地は、湖西(高島)、近江八幡、日野、湖東(五個荘、豊郷等)、湖北など、現在の滋賀県である。近江商人が歴史に登場するのは、売買や貨幣の普及が盛んになる鎌倉時代に遡るとされている。近江商人が活躍を開始し、成功したの江戸期からであろう。
しかし、近江商人として本格的に活動する前の戦国時代の湖東地方には「山越商人」や「五箇商人」、「四本商人」などの「小幡商人」、その後の「本座商人」などが存在した。封建制の時代、ギルドなど権利集団の争いあった記録が残っている。これらについては、別途改めて取り上げたいと思う。
特に江戸時代から昭和にかけ、全国で活躍したのが近江商人。 今日の高島屋・西武グループ・伊藤忠商事・住友財閥・ワコール・トヨタ自動車・日本生命など錚々たる企業が近江商人が関わっている。
その近江商人が大事にしていたのが、「三方よし」と表現される理念だ。 その企業理念が今、改めて注目されている。

滋賀県は近江、古くから東西南北の交通の結節点でもありながら、近江商人=行商というイメージが強い。全国を「天秤棒」一本で行商した開拓者精神が旺盛だったようだ。
しかし、単に「とにかく儲ければよい」いうのではなく、社会的に認められる正当な商売を信条とし、巧妙な計算や企てをよしとせず、世の中の過不足を補填することを一番としていたようだ。焼き畑農業的な短期間で儲け、その後が続かないような商売ではなく、長期的・継続的な商売こそが、長い目で安定して儲けていくことができるといった観点だろうか。 彼らは、行商先で出かけて商品を売った帰りに、その土地の産物を購入して持ち帰り、それを加工してまた販売するという、「ノコギリ商法」という方法で巨万の富を得る商人もいた。元々交通の要所、結節点にあるのもポイントだったが、近江商人は、倹約を旨とし、自分の利益だけでなく社会への貢献を重視する「三方よし」の考え方を実践した。
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/e/65362eefe278f07311548e0d3e459cd4
1, 商売は世のため、人のための奉公にして、利益はその当然の報酬である。
2, 店の大小より場所の良否、場所の良否よりも品の如何が重要である。
3, 売る前のお世辞より売った後の奉公。お客の信用を得ることが商売繁盛となる。
4, 売上が少ないのは資金の少なさの問題ではなく、そもそも信用が足りていない証拠。
5, 無理に売るな!お客の好むものも売るな!客のためになるものを売れ!
6, お客のためになる良い商品を売ることは善行。そして良い商品を宣伝して、多く売る事はさらに良いこと!
7, 紙一枚でも景品はお客を喜ばせる。あげるもののない時は笑顔を景品にせよ。
8, 定価を守れ!安易な値下げで売ることはしない
9, 今日の損益を常に考えよ、今日の損益を明らかにしないでは、寝につかぬ習慣にせよ!
10, 商売には好況、不況はない。どんな状況でも世の中からニーズはなくならない!
中でも近江商人の経営哲学は「三方良し」=「売り手よし」「買い手よし」「世間よしである。「三方良し」は今日でも多くの実業家の経営理念になっている。
色々な説があるが、初代創業者伊藤忠兵衛(現伊藤忠商事)が、近江商人の先達に対する尊敬の思いを込めて発した『商売は菩薩の業(行)、商売道の尊さは、売り買い何れをも益し、世の不足をうずめ、御仏の心にかなうもの』とされている。
「三方よし」の思想は、近江商人企業である「伊藤忠商事などの企業の経営理念として採用されている。伊藤忠商事は、2020年4月1日に経営理念を「豊かさを担う責任」から「三方よし」に改めた。
今日においても伊藤忠だけではなく、多くの近江商人にル ーツを持つ会社では、この哲学を大切にしていると言われている。 「三方良し」は、近江商人だけではない。「渋沢栄一」は「一個人のみ大富豪になっても、社会の多数が貧困に陥るような事業であったならば、その幸福は継続されない」と説いている。
また、京セラ創業者の「故稲盛和夫」は、「より良い仕事をしていくためには、自分だけのことを考えて判断するのではなく、まわりの人のことを考え、思いやりに満ちた「利他の心」に立って判断をすべきです。」と説いている。
まず事業の目的は社会にとって良きものでなければならない。社会が必要とするものを生み出し、社会の発展に寄与するものでなければならない。即ち事業には社会的意義がなければならないということである。
商売(事業)は、その時だけの儲けを目指すのでは、持続性がない。売って利益を得るのは当然だが買った人が良かったと喜んでいただかなければ、次はない。WIN&WINの関係は重要だが、これをもう一歩踏み込んだのが「世間よし」である。
近江商人の発祥地
近江商人の発祥の地の1つは、滋賀県東部に位置する東近江市内の「五個荘金堂地区」と言われている。「五個荘商人」の町、現、東近江市の五個荘金堂地区には、近江商人が築いた邸宅や白壁と舟板塀の蔵、優雅な庭園など、近江商人の歴史と文化を感じられる景観が残っている。この地区は国の「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されており、近江商人の歴史を学ぶことができる「近江商人博物館」もある。もう少し狭い範囲で言えば五個荘の「小幡商人」が五個荘商人の先駆けも果たしている。
五個荘:
東近江市立近江商人博物館
東近江市五個荘竜田町583
電話:0748-48-7101
https://e-omi-muse.com/omishounin/about10.html

湖東:
(財)近江商人郷土館
東近江市小田苅町473
電話:0749-45-0002
https://old.shoai.ne.jp/shiga/chiiki/0812/chiik0812.htm
江戸時代に活躍した近江商人の代表的な豪商の一人で、総合繊維商社の創業者とされる「小林吟右衛門(ぎんえもん)」の邸宅。実際に住んでいた屋敷を一般公開した資料館「近江商人郷土館」では、商売をするにあたって使われていた帳面や店の看板などが展示されている他に、当時の生活ぶりを知ることのできる生活館もあり。

豊郷:
(公財)伊藤忠兵衛記念館
滋賀県豊郷町大字八目128-1
電話:0749-35-2001
http://toyosatosaibikai.or.jp/
初代伊藤忠兵衛の生家、本宅。今なお伊藤忠、丸紅の新卒入社員が必ず訪れる聖地。

近江八幡:
近江八幡市立資料館(郷土資料館)
近江八幡市新町2丁目22
0748-32-7048
近江八幡市立資料館(歴史民俗資料館)
近江八幡市新町2丁目
0748-32-7048
https://www.omi8.com/omihachiman/local-history/goroku/

日野:
日野まちかど感応館(旧正野玄三薬店)
滋賀県蒲生郡日野町村井1284番地
https://omi-syonin.com/hino_syounin/

高島: 江戸時代に活躍した近江の豪商。高島市出身の豪商、「小野善助」が住んでいた屋敷があったとされる「小野組総本家屋敷跡」。 明治時代初期に日本の経済界で活躍した商人の総本家があった場所に、現在は屋敷の跡地と案内板が残っている。屋敷や暮らしぶりを想像して見るのも良いかもしれない。
- 小野組総本家屋敷跡(高島市勝野)