梅雨時のつめたい雨が身体にしみわたるようなある日、ふと、自分の生命を雨のなかに溶けこませてしまいたい衝動にかられ、実行した作家がいた。その名を太宰治という。病魔がいずれ自分自身をむしばみつくすだろうという暗い予感を先取りするかのように。
太宰治情死事件は、いずれ起こるであろうできごととして世間は受けとめていた。というのは、この作家の描く作品と人生には常に女にからむ自殺とか心中とかがちらついていたからである。
太宰の作品には私小説的小説(そこに描かれているものがすべて私生活の表出であるというわけではないが)が多い。それらに共通しているのは、自虐的ともいえる自己の告白である。
太宰治という作家には、自らの生い立ちの枷から逃げられないという意識がつねにつきまとっていた。その証拠に彼の作品のなかには幾度も幼少期の思い出が登場する。
遺書がわりに著したという処女作『思い出』という二十三歳の時に書かれた自伝小説のなかに次のような下りがある。
「叔母についての追憶はいろいろあるが、そのころの父母の思い出は生憎と一つも持ち合わせない。曾祖母、祖母、父、母、兄三人、姉四人、弟一人、それに叔母と叔母の娘四人の大家族だったはずであるが、叔母を除いて他の人たちのことは私も五六歳になるまでほとんど知らずにいたと言ってよい」
母親がわりの叔母の手によって育てられた太宰にとって、いわば自分は余計者であるという思いがぬぐいがたくまとわりついていた。小学校の頃、綴り方の時間に「父母が私を愛してくれない」と不平を書き綴る少年であったのである。
そうした子供であった太宰にとって、家族のなかで、とくに母は冷たく、遠い存在に感じられた。大家族という制度は子も母をもたがいに親しく温かい人間関係をもてない状態においたといえる。
母の愛情を欠いた生い立ちは、逆に母に甘えたいという思いと、甘えさせてもらえない「かつえの感覚」(鶴見俊輔)を増幅させて、その後の太宰の生き方に暗い影を投げかけることになる。
ここにある母親像は、まさにユングの説くグレートマザーを彷彿させる。生につながる温かさ、優しさを与えてくれる善母としての母親像と死につながる恐母としての母親像。この相矛盾するふたつながらの母親像に、作家太宰治は終生こだわらざるを得なかったのである。
母の愛の欠如と大家族の形式ばった欺瞞にみちた人間関係のなかで、この作家は傷つきやすい鋭利な感受性の持ち主となってゆく。 みずからを招かざる人間と意識し、その結果として、人間関係においても多面的ならざるを得ない、「十重二十重の仮面がへばりついている」人間であると認識する少年は、ある時、自分が作家になることを願望する。
すべてについて満足しきれない自分、いつも空虚なあがきのなかにいる自分の本質を創作という行為をつうじて見極めようと決意したのである。
* * *
作家になることによって企図しようとしたものが、どれほど実現されたかは定かではないが、最晩年の『人間失格』は、太宰が「幼少時から自分の身体中にためてきた毒素をやっとのことで吐き出した」(ドナルド・キーン)作品ともいえた。
その小説は、ひとりの男が遺した手記という形式をとっている。そこにフィクションが介在しているとはいえ、この作品を読む者にとって、その内容は、まさに太宰治その人の人生であることを知るのである。
その男は「人間を極度に恐れていながら、それでいて、人間をどうしても思いきれない人間」として描かれる。このような対人観をもつゆえに、「おもてでは、絶えず笑顔をつくりながらも、内心は必死の、それこそ千番に一番の兼ね合いとでもいうべき危機一髪の、油汗流してのサーヴィス」に心を尽くす態度で世間を泳ぎまわることになる。
それは、何でもいいから笑わせておけばいい。とにかく「彼ら人間たちの目障りになってはいけない、自分は無だ、風だ、空だ」という生き方に徹することを意味する。
男は、すでに「子供のころから、自分の家族の者たちに対してさえ、彼らがどんなに苦しく、またどんなことを考えて生きているか、まるでちっとも見当つかず、ただおそろしく、その気まずさに堪えることができず、すでに道化の上手になって」いるような人間であった。
ここには余計者的な存在者として、あらゆる執着から解き放たれ、流れゆく、みずからを生まれながらの異邦人と位置づける姿勢がみえる。
が、成功したかにみえたそうした道化の態度を見透かす人間がいるのを発見する。
それは女であった。女は自分の孤独の匂いを本質的にかぎつけては近づき、自分につけこむ存在だ、ということを知る。
「自分には、人間の女性のほうが、男性よりさらに数倍難解でした。自分の家族は女性のほうが男性より数が多く、また親戚にも、女の子がたくさんあり、また、れいの犯罪の女中(少年期、女中に犯されたと告白する)などもいまして、自分は幼い時から、女中とばかり遊んで育ったといっても過言ではないと思いますが、また、しかし、実に薄氷を踏む思いで、その女たちと附き合って来たのです」
女性に取り囲まれる環境で育ったゆえに、その人間関係の難しさを語る。「女は引き寄せ、つき放す、或いはまた、女は、人のいるところでは自分をさげすみ、邪慳にし、誰もいなくなると、ひしと抱きしめる」と、矛盾に満ちた女心について鋭い観察をする。
そして、女は「同じ人類のようなでありながら、男とはまた、まったく異なった生きもののような感じ」だとみなす。
この女性観は、太宰自身の、幼少期における母親との関係を暗示する。さらに、女たちに取り囲まれた大家族のなかでのナーバスな人間関係を反映していて興味をひく。
とはいえ、その一方で、「人間を恐れていながら、人間をどうしても思いきれない」その男(じつは太宰)は、大人になったのちも、幾人もの女性たちの間をわたり歩くことになる。
妻子のある身でありながら、愛人をもち、さらに別の女性と親しくなってゆく、という女性遍歴を重ねてゆく。ここには理想の女性を追い求めて遍歴をかさねる男の姿がみえる。 さらに、絶筆となった作品『グッドバイ』では、「多情なくせに、また女にへんに律義な一面を持っていて」、それがまた「女に好かれる所以でもある」男を登場させ、その男がかかわる女との別離百態を描く。
この作品もまた太宰の自画像に近いものであった。だが、そうした性向が、やがてこの作家自身を追いつめてゆくことになるのである。
* * *
最後の女性山崎富栄(30歳)と知り合ったのは、昭和二十二年二月。中央線三鷹駅前の屋台でのことであったという。
やがてふたりの仲は急速に深まり、女は太宰の執筆の仕事を手伝うようになる。
この頃から死の直前までに書き上げた作品に『斜陽』『ヴィヨンの妻』『人間失格』
『桜桃』『グッド・バイ』(未完)などがある。いずれも太宰の代表的な作品ばかりだ。 だが、結核を病む身体を鞭うっての執筆の連続は、太宰の命を、さらに切り刻んでゆく。この頃には、不眠症もひどくなり、しばしば喀血する事態になっている。
そうした状態のなか、ついにふたりは心中を決意する。六月十三日の夜、降りしきる雨のなかでの心中行であった。
ふたりが最後を過ごした富栄の部屋には、ふたりで撮った写真と質素な祭壇がつくられていた。そこには、入水を暗示する「池水は濁りににごり藤波の影もうつらず雨降りしきる」という太宰の筆になる伊藤左千夫の歌がそえられていた。
だが、この心中は、男と女が思い思っての果てのものではなかった。それは「ただひとりの男に対する恋情の完成だけを祈って、半狂乱で生きている女の姿にほだされた」(臼井吉見)男が、せっぱつまって女をともなった心中行であったといえる。
いかにもこの作家らしい死に方であった。それは「いつわり、おもいやり以外のなにをよりどころとして、この無意味な人生を生きのびようか」と考える作家太宰が最後になした人生の実践でもあった。
ふたりが入水したのは、玉川上水のむらさき橋と萬助橋との間である。現在、武蔵野市と三鷹市の市境にあるこの辺りは、玉川上水緑道として、きれいな遊歩道が整備されていて、格好の散歩道になっている。
遊歩道の連なる玉川上水のほとりは、コナラ、ミズキ、エゴノキなどの雑木がうっそうと繁り、季節になればアジサイやシャガの薄紫色の花が咲くといった場所である。
鉄柵の外からのぞき見る上水の流れは暗く深い。上水の役目を終えた流れには、今や鯉が泳ぎ、鴨が遊んでいる。
水死体は、『朝日新聞』の報じるところによると「十三日夜から七日目、太宰氏の誕生日に当たる十九日、午前六時五十分ごろ三鷹町牟礼五四六先玉川上水の新橋下(投身現場から一キロ半下流)の川底の棒クイに抱き合ったままでかかっているのを通行人が発見」した。
死体が発見された新橋は、むらさき橋の下流四つ目に架けられた橋である。互いの脇の下から女の腰ひもで離れないように堅く結び合い、家出の日の姿そのままの、太宰はワイシャツにズボン、山崎は黒のワンピース姿であった。
ふたりが失踪したその日の夜半から、それまで空梅雨模様であった天候が急変し、わびしい雨が降りつづいたという。失踪の翌日、現地を訪れた作家の石川淳は、当時の模様をつぎのように描写している。
「さみだれの空くもって日の影はどこにも無い。足もとを見れば、ただ白濁の水の、雨に水かさを増して、いきほひはげしく、小さい滝となり、深い渦となり、堤の草を噛んで流れつづけていた」(『太宰昇天』)
玉川上水は、むらさき橋の下流に架かる萬助橋から牟礼橋にかけて、幾つものカーブを描いて流れるようになる。格好の遊歩道になっている堤を歩いて行くと、「松本訓導殉難碑」の大きな碑が目に入る。
この碑は、大正八年、遠足のおり、この流れに落ちた児童を救おうとして遭難した小学校教師の慰霊碑である。こうした事故があったくらいだから危険な場所だったことが分かる。地元では「人食い川」と呼ばれた上水道であった。
上水の流れは新橋で大きく曲流し、水深も増す。右岸は小高い丘となり、左岸には谷が迫る。この一帯は、今でこそ住宅が建てこんでしまっているが、谷と丘が入り組んでいて、それだけに流れが複雑になっているところである。
ついでながら、この玉川上水は、江戸市民に飲料水を供給する目的で、承応三年(1654)に開削されたものだ。江戸のはるか西、羽村から多摩川の水を江戸市中に引き入れたものである。玉川兄弟が工事を指揮して、一年四カ月をかけて完工させている。
太宰はかつて、この玉川上水のほとりを親しく散策したことがあった。牧歌的な堤にたたずむマント姿の記念写真が残されている。五メートルにも満たない川幅の上水の流れを眺めて、太宰は何を思ったことだろうか。
* * *
太宰の一生を思う時、彼の人生観は「ただ人生は過ぎて行きます」(『人間失格』のなかで主人公の手記の末尾に記されている言葉)ということであったように思える。
絶筆となった『グッド・バイ』の連載にあたって、作者は「漢詩選の五言絶句の中に、人生是別離の一句があり、私の或る先輩は、これをサヨナラだけが人生ダ、と記した。まことに相逢った時のよろこびは、つかのまに消えるものだけれど別離の傷心は深く、私たちは常に惜別の情の中に生きているといっても過言ではあるまい」と語っている。
この拭いがたい流離感は、太宰の心に深く刻まれた過去の深い体験から派生したもののようである。それが太宰の生涯をつうじての生の基調であった。
そして、流離の果ての安住の地として心に描いたものが母胎への回帰であった。そこにこそ安らぎの場所がある、と思い描いたのである。
水の流れには、永遠と生のはかなさを暗示するものがある。つねに流れ、姿をかえ、そして呑みこむ水の流れ-それは、そのまま母のメタファにつうじる。
この作家は、水と一体になり、死ぬことでそこに還り、再生する、永遠に母なるものに身をゆだねた、と解釈できないか。
日本浪漫派の旗手、保田輿重郎は、かつて、あやしくも心もとなく流れてゆくこの作家について、「佳人水上を行くがごとし」と評した。その評価のように、太宰治という作家は、玉川上水の流れに、女とともに身を投じたのである。
ふたりの遺体が発見されたその日は、奇しくも太宰治、満三九歳の誕生日であったという。その後、六月一九日の命日は、「桜桃忌」と呼ばれるようになる。そして、墓は遺言にしたがって、三鷹の禅林寺にある森鴎外の墓と向かい合う場所に建てられたのである。
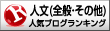
太宰治情死事件は、いずれ起こるであろうできごととして世間は受けとめていた。というのは、この作家の描く作品と人生には常に女にからむ自殺とか心中とかがちらついていたからである。
太宰の作品には私小説的小説(そこに描かれているものがすべて私生活の表出であるというわけではないが)が多い。それらに共通しているのは、自虐的ともいえる自己の告白である。
太宰治という作家には、自らの生い立ちの枷から逃げられないという意識がつねにつきまとっていた。その証拠に彼の作品のなかには幾度も幼少期の思い出が登場する。
遺書がわりに著したという処女作『思い出』という二十三歳の時に書かれた自伝小説のなかに次のような下りがある。
「叔母についての追憶はいろいろあるが、そのころの父母の思い出は生憎と一つも持ち合わせない。曾祖母、祖母、父、母、兄三人、姉四人、弟一人、それに叔母と叔母の娘四人の大家族だったはずであるが、叔母を除いて他の人たちのことは私も五六歳になるまでほとんど知らずにいたと言ってよい」
母親がわりの叔母の手によって育てられた太宰にとって、いわば自分は余計者であるという思いがぬぐいがたくまとわりついていた。小学校の頃、綴り方の時間に「父母が私を愛してくれない」と不平を書き綴る少年であったのである。
そうした子供であった太宰にとって、家族のなかで、とくに母は冷たく、遠い存在に感じられた。大家族という制度は子も母をもたがいに親しく温かい人間関係をもてない状態においたといえる。
母の愛情を欠いた生い立ちは、逆に母に甘えたいという思いと、甘えさせてもらえない「かつえの感覚」(鶴見俊輔)を増幅させて、その後の太宰の生き方に暗い影を投げかけることになる。
ここにある母親像は、まさにユングの説くグレートマザーを彷彿させる。生につながる温かさ、優しさを与えてくれる善母としての母親像と死につながる恐母としての母親像。この相矛盾するふたつながらの母親像に、作家太宰治は終生こだわらざるを得なかったのである。
母の愛の欠如と大家族の形式ばった欺瞞にみちた人間関係のなかで、この作家は傷つきやすい鋭利な感受性の持ち主となってゆく。 みずからを招かざる人間と意識し、その結果として、人間関係においても多面的ならざるを得ない、「十重二十重の仮面がへばりついている」人間であると認識する少年は、ある時、自分が作家になることを願望する。
すべてについて満足しきれない自分、いつも空虚なあがきのなかにいる自分の本質を創作という行為をつうじて見極めようと決意したのである。
* * *
作家になることによって企図しようとしたものが、どれほど実現されたかは定かではないが、最晩年の『人間失格』は、太宰が「幼少時から自分の身体中にためてきた毒素をやっとのことで吐き出した」(ドナルド・キーン)作品ともいえた。
その小説は、ひとりの男が遺した手記という形式をとっている。そこにフィクションが介在しているとはいえ、この作品を読む者にとって、その内容は、まさに太宰治その人の人生であることを知るのである。
その男は「人間を極度に恐れていながら、それでいて、人間をどうしても思いきれない人間」として描かれる。このような対人観をもつゆえに、「おもてでは、絶えず笑顔をつくりながらも、内心は必死の、それこそ千番に一番の兼ね合いとでもいうべき危機一髪の、油汗流してのサーヴィス」に心を尽くす態度で世間を泳ぎまわることになる。
それは、何でもいいから笑わせておけばいい。とにかく「彼ら人間たちの目障りになってはいけない、自分は無だ、風だ、空だ」という生き方に徹することを意味する。
男は、すでに「子供のころから、自分の家族の者たちに対してさえ、彼らがどんなに苦しく、またどんなことを考えて生きているか、まるでちっとも見当つかず、ただおそろしく、その気まずさに堪えることができず、すでに道化の上手になって」いるような人間であった。
ここには余計者的な存在者として、あらゆる執着から解き放たれ、流れゆく、みずからを生まれながらの異邦人と位置づける姿勢がみえる。
が、成功したかにみえたそうした道化の態度を見透かす人間がいるのを発見する。
それは女であった。女は自分の孤独の匂いを本質的にかぎつけては近づき、自分につけこむ存在だ、ということを知る。
「自分には、人間の女性のほうが、男性よりさらに数倍難解でした。自分の家族は女性のほうが男性より数が多く、また親戚にも、女の子がたくさんあり、また、れいの犯罪の女中(少年期、女中に犯されたと告白する)などもいまして、自分は幼い時から、女中とばかり遊んで育ったといっても過言ではないと思いますが、また、しかし、実に薄氷を踏む思いで、その女たちと附き合って来たのです」
女性に取り囲まれる環境で育ったゆえに、その人間関係の難しさを語る。「女は引き寄せ、つき放す、或いはまた、女は、人のいるところでは自分をさげすみ、邪慳にし、誰もいなくなると、ひしと抱きしめる」と、矛盾に満ちた女心について鋭い観察をする。
そして、女は「同じ人類のようなでありながら、男とはまた、まったく異なった生きもののような感じ」だとみなす。
この女性観は、太宰自身の、幼少期における母親との関係を暗示する。さらに、女たちに取り囲まれた大家族のなかでのナーバスな人間関係を反映していて興味をひく。
とはいえ、その一方で、「人間を恐れていながら、人間をどうしても思いきれない」その男(じつは太宰)は、大人になったのちも、幾人もの女性たちの間をわたり歩くことになる。
妻子のある身でありながら、愛人をもち、さらに別の女性と親しくなってゆく、という女性遍歴を重ねてゆく。ここには理想の女性を追い求めて遍歴をかさねる男の姿がみえる。 さらに、絶筆となった作品『グッドバイ』では、「多情なくせに、また女にへんに律義な一面を持っていて」、それがまた「女に好かれる所以でもある」男を登場させ、その男がかかわる女との別離百態を描く。
この作品もまた太宰の自画像に近いものであった。だが、そうした性向が、やがてこの作家自身を追いつめてゆくことになるのである。
* * *
最後の女性山崎富栄(30歳)と知り合ったのは、昭和二十二年二月。中央線三鷹駅前の屋台でのことであったという。
やがてふたりの仲は急速に深まり、女は太宰の執筆の仕事を手伝うようになる。
この頃から死の直前までに書き上げた作品に『斜陽』『ヴィヨンの妻』『人間失格』
『桜桃』『グッド・バイ』(未完)などがある。いずれも太宰の代表的な作品ばかりだ。 だが、結核を病む身体を鞭うっての執筆の連続は、太宰の命を、さらに切り刻んでゆく。この頃には、不眠症もひどくなり、しばしば喀血する事態になっている。
そうした状態のなか、ついにふたりは心中を決意する。六月十三日の夜、降りしきる雨のなかでの心中行であった。
ふたりが最後を過ごした富栄の部屋には、ふたりで撮った写真と質素な祭壇がつくられていた。そこには、入水を暗示する「池水は濁りににごり藤波の影もうつらず雨降りしきる」という太宰の筆になる伊藤左千夫の歌がそえられていた。
だが、この心中は、男と女が思い思っての果てのものではなかった。それは「ただひとりの男に対する恋情の完成だけを祈って、半狂乱で生きている女の姿にほだされた」(臼井吉見)男が、せっぱつまって女をともなった心中行であったといえる。
いかにもこの作家らしい死に方であった。それは「いつわり、おもいやり以外のなにをよりどころとして、この無意味な人生を生きのびようか」と考える作家太宰が最後になした人生の実践でもあった。
ふたりが入水したのは、玉川上水のむらさき橋と萬助橋との間である。現在、武蔵野市と三鷹市の市境にあるこの辺りは、玉川上水緑道として、きれいな遊歩道が整備されていて、格好の散歩道になっている。
遊歩道の連なる玉川上水のほとりは、コナラ、ミズキ、エゴノキなどの雑木がうっそうと繁り、季節になればアジサイやシャガの薄紫色の花が咲くといった場所である。
鉄柵の外からのぞき見る上水の流れは暗く深い。上水の役目を終えた流れには、今や鯉が泳ぎ、鴨が遊んでいる。
水死体は、『朝日新聞』の報じるところによると「十三日夜から七日目、太宰氏の誕生日に当たる十九日、午前六時五十分ごろ三鷹町牟礼五四六先玉川上水の新橋下(投身現場から一キロ半下流)の川底の棒クイに抱き合ったままでかかっているのを通行人が発見」した。
死体が発見された新橋は、むらさき橋の下流四つ目に架けられた橋である。互いの脇の下から女の腰ひもで離れないように堅く結び合い、家出の日の姿そのままの、太宰はワイシャツにズボン、山崎は黒のワンピース姿であった。
ふたりが失踪したその日の夜半から、それまで空梅雨模様であった天候が急変し、わびしい雨が降りつづいたという。失踪の翌日、現地を訪れた作家の石川淳は、当時の模様をつぎのように描写している。
「さみだれの空くもって日の影はどこにも無い。足もとを見れば、ただ白濁の水の、雨に水かさを増して、いきほひはげしく、小さい滝となり、深い渦となり、堤の草を噛んで流れつづけていた」(『太宰昇天』)
玉川上水は、むらさき橋の下流に架かる萬助橋から牟礼橋にかけて、幾つものカーブを描いて流れるようになる。格好の遊歩道になっている堤を歩いて行くと、「松本訓導殉難碑」の大きな碑が目に入る。
この碑は、大正八年、遠足のおり、この流れに落ちた児童を救おうとして遭難した小学校教師の慰霊碑である。こうした事故があったくらいだから危険な場所だったことが分かる。地元では「人食い川」と呼ばれた上水道であった。
上水の流れは新橋で大きく曲流し、水深も増す。右岸は小高い丘となり、左岸には谷が迫る。この一帯は、今でこそ住宅が建てこんでしまっているが、谷と丘が入り組んでいて、それだけに流れが複雑になっているところである。
ついでながら、この玉川上水は、江戸市民に飲料水を供給する目的で、承応三年(1654)に開削されたものだ。江戸のはるか西、羽村から多摩川の水を江戸市中に引き入れたものである。玉川兄弟が工事を指揮して、一年四カ月をかけて完工させている。
太宰はかつて、この玉川上水のほとりを親しく散策したことがあった。牧歌的な堤にたたずむマント姿の記念写真が残されている。五メートルにも満たない川幅の上水の流れを眺めて、太宰は何を思ったことだろうか。
* * *
太宰の一生を思う時、彼の人生観は「ただ人生は過ぎて行きます」(『人間失格』のなかで主人公の手記の末尾に記されている言葉)ということであったように思える。
絶筆となった『グッド・バイ』の連載にあたって、作者は「漢詩選の五言絶句の中に、人生是別離の一句があり、私の或る先輩は、これをサヨナラだけが人生ダ、と記した。まことに相逢った時のよろこびは、つかのまに消えるものだけれど別離の傷心は深く、私たちは常に惜別の情の中に生きているといっても過言ではあるまい」と語っている。
この拭いがたい流離感は、太宰の心に深く刻まれた過去の深い体験から派生したもののようである。それが太宰の生涯をつうじての生の基調であった。
そして、流離の果ての安住の地として心に描いたものが母胎への回帰であった。そこにこそ安らぎの場所がある、と思い描いたのである。
水の流れには、永遠と生のはかなさを暗示するものがある。つねに流れ、姿をかえ、そして呑みこむ水の流れ-それは、そのまま母のメタファにつうじる。
この作家は、水と一体になり、死ぬことでそこに還り、再生する、永遠に母なるものに身をゆだねた、と解釈できないか。
日本浪漫派の旗手、保田輿重郎は、かつて、あやしくも心もとなく流れてゆくこの作家について、「佳人水上を行くがごとし」と評した。その評価のように、太宰治という作家は、玉川上水の流れに、女とともに身を投じたのである。
ふたりの遺体が発見されたその日は、奇しくも太宰治、満三九歳の誕生日であったという。その後、六月一九日の命日は、「桜桃忌」と呼ばれるようになる。そして、墓は遺言にしたがって、三鷹の禅林寺にある森鴎外の墓と向かい合う場所に建てられたのである。









