山の奥の方からいまにもどよめきがわきあがってくるようである。森の陰から雲霞のように兵士が現れ出てくる気配がする。周囲を山々にかこまれた、のどかな田園風景がひろがる関ヶ原。かつて、その一帯で壮絶な攻防戦がおこなわれたのである。
それはこの国を二つに分ける天下分け目の戦いとなった。その後の日本の歴史の歩みを決定づけた出来事となった。
東海道本線でも数少ない各駅停車の列車の停車駅、関ヶ原の駅に降り立ち、地図を片手に歩き出せば、そこがすでに古戦場のただなかであることを知らされる。 私がまずはじめに訪れたのは、関ヶ原駅のすぐ裏手、つまり北側にある東の首塚と呼ばれる場所であった。東と称しているところを見ると西の首塚というものもあるのだろうと、地図をのぞけば、そこより西の方、中山道沿いに西の首塚なるものがあった。
まずは、「東の首塚」と記された石碑の立つ朱塗りの門をくぐる。あまり広くない境内には椎の大木がうっそうと繁り、蝉がかまびすしく鳴いている。焼きつくような夏の強い日差しもここには届かないようである。
寺とも神社ともつかない敷地内の奥にひとつの塚があり、近くに祠がひっそりと建っている。その塚は首級墳墓らしく、そばに立つ石碑がそのいわくを刻んでいる。が、風雪をへた石碑の文字はほとんど判読できないほどである。かろうじて読みくだしてみると、そこには東西両軍の戦没兵士たちを埋葬してあることが記されてあった。 かつて、ここには累々と首級が並べられたことであろう。戦死者の遺体が無造作に打ち棄てられていたにちがいない。ふいに凄惨な情景が頭に浮かびあがる。
ここはまた、東軍の先鋒隊であった松平忠吉、井伊直政両軍の陣営がおかれたところでもある。松平、井伊の両軍は、敵中突破して逃走した西軍の薩摩藩の島津惟新を追って、いっとき、この地に陣を敷いたのである。 東の首塚をあとにして、やや上り勾配の野良道をさらに北に進むと、西軍の本陣があった笹尾山に至る。
そこは、いわずと知れた西軍の総大将石田三成が布陣したところである。 関ヶ原の戦いをマクロ的に把握するには、この笹尾山を中心に布陣した西軍と、これを攻めあげる東軍の布陣の概要をまず頭に入れておく必要があろう。
そもそも関ヶ原は、東西4キロ、南北2キロほどのひろがりをもつ細長い盆地である。北方にそびえる伊吹山とそれにつらなる峰々が、南と東方向に向かってゆるやかなスロープをつくり、一方、南方からは鈴鹿山脈が触手をのばしている。
その盆地を貫通するように中山道が東西に走り、そして、その中央部から西北方向に北国往還が、また東南方向には伊勢街道が延びる。
この関ヶ原をめざして東軍は大垣方面から中山道を西進、そして、西軍はそれに追われるように大垣方面から西に退却し、関ヶ原に陣を構えたのである。
西軍は夜を徹して、鳴りをひそめるように進んだといい、対照的に、東軍は鬨の声をあげながら、全力で疾駆したのである。追う者と追われる者とのちがいであった。 そして、西軍は、笹尾山から南西につらなる山々を背に、石田三成、島津惟新、小西行長、宇喜多秀家、大谷吉継の各部隊が布陣、一方、徳川家康を総大将とする東軍は、家康のいる本陣・桃割山を中心に西面して二列縦隊で布陣した。 両者のこの布陣の仕方は、地形のうえでは、西軍が東軍をちょうど見下ろす格好になり、陣取りの形からすれば断然西軍有利ということになる。が、実際には、そのような結果にならなかった。
* * *
戦いがはじまったのは、慶長5年(1600)9月15日、午前8時頃であった。夜が明けたにもかかわらず、あたりには濃い霧がたちこめていた。それが一瞬途切れたのである。 霧が切れると、敵も味方も、あっと息を呑むような光景がそこにあらわれ出た。東西四キロほどの盆地に、数え切れないほどの軍勢が陣形をつくってひしめき、戦闘態勢をととのえていたのである。
色とりどりの軍旗がはためいている。風になびく長い旗竿、意匠をこらした馬印が薄日に輝やいている。そのおびただしい数に、両軍の将兵は、あらためて我が身を奮い立たせた。この時、関ヶ原には東西両軍あわせて、じつに十五万という軍団が集結していたのである。
霧の合間をぬうように、まず東軍の中堅にいた井伊直政、松平忠吉隊が前進した。それを目撃した同じく東軍の福島正則隊が、遅れてはならじと南側面から前に進み、前方にひかえる西軍の宇喜多秀家隊に向かっていった。 さらに、これらの動きを見守っていた東軍の黒田長政隊、西軍の小西行長隊が動きだした。
こうして、合戦の火ぶたは切って落とされたのである。 東軍が攻める目標としたのは、当然のことながら、笹尾山に陣をかまえる西軍の総大将、石田三成であった。笹尾山は北国街道沿いにある小高い山で、そこからは東軍の動きが一望である。
いま、その周辺は広々とした田園地帯である。当時も同じような風景がひろがっていたことだろう。東軍は、このゆるい勾配のある地形を笹尾山に向かって押し進んでいった。 こうして、東軍、西軍入り乱れての戦いがはじまったのであるが、はじめは、やや西軍有利という状態で推移していった。
上手から東軍の攻勢を迎えうつ形になる西軍の方が、とうぜんのことながら敵の動きを見通せる分だけ地の利に勝っていたといえる。東軍の本陣ははじめ、関ヶ原東方にある桃配山にあった。桃配山は壬申の乱の際に、天武天皇が将兵を激励して桃を配ったという伝説が残る山である。総大将、徳川家康はそこで総指揮をとっていた。
ところが、戦いがはじまると、戦局の掌握には、そこでは、あまりにも遠すぎることが分かった。今そこには家康の腰掛け岩と机石が残る。
家康が本陣をさらに西にある陣場野に移したのは午前11時頃である。その本陣跡は現在、公園になっていて、そこに土囲いされた土壇が残る。その土壇は家康が敵の武将を首実検したところであるという。いかにも首実験した場所にふさわしい雰囲気がただよう。 それにしても、いくつも無念の形相をした生首がそこにさらされていたかと思うと、思わず背筋が寒くなる。
じつは、その土壇と土囲いは、後年になって、この地の領主が幕府の命を受けて復元したものだという。幕府は、いわば、徳川政権誕生の重要な歴史的事蹟として、この地を史跡として保存しようと企図したのである。
* * *
開戦から一時間ほどたった頃、石田三成率いる六千余りの将兵たちは、東軍の集中攻撃の渦中にあった。
戦いに臨んで、すでに石田隊は笹尾山の前方にひろがる田の中に竹矢来の柵を二重にめぐらして防備をととのえていた。
石田隊は兵を三隊に分け、そのうちの二隊を島左近と蒲生郷舎が指揮して、竹矢来の前面と中ほどにそれぞれ布陣した。
そして、背後の笹尾山の山頂に三成が本陣を置いた。そこには五挺の大筒が備えられてもいた。島も蒲生も三成を真に慕う忠臣であった。士気は高かった。 笹尾山は小さな山である。そこを中心に、じつに六千余りもの将兵が立て籠もっていたのである。前方に田園がひらけているとはいえ、このせまい山域を中心に六千という数はかなりの数である。文字通り、人がひしめく状態であったにちがいない。本陣に身を置く石田三成の不安と焦燥が目に見えるようである。今そこには「関ヶ原古戦場、石田三成陣地」と記された記念碑が立っている。
この笹尾山の攻撃に、まず先鞭をつけたのは黒田長政の別動隊であった。別動隊は笹尾山の前面を守っていた島左近隊と衝突した。この別動隊は鉄砲隊を配備していた。島隊は銃火にさらされて壊滅。島左近自身も重傷を負って退却した。その間隙をぬうようにして、ここぞとばかりに、東軍の黒田長政の本隊、細川忠興、加藤嘉明などの諸隊が石田三成の本陣に斬りこんでいった。
笹尾山は混乱の渦の中にあった。石田三成みずからが陣頭指揮をした。重傷の島左近も槍を縦横にふりまわしながら戦ったが、東西入り乱れる兵士の中に、いつしか姿を消した。 この混乱にもかかわらず石田隊は持ちこたえていた。午前10時ころになっても、東西両軍の力の均衡は破られなかった。
そんななか、各所で白兵戦がくりひろげられていた。笹尾山の南方、天満山の麓に陣取った宇喜多秀家隊とそれを攻める福島正則隊が最初に衝突したのは、前述のように、午前8時ごろであったが、その後、両者、一進一退の攻防戦がつづいていた。
大馬印を押し立てて、六千あまりの兵を指揮するのは福島正則、それを迎え撃つ宇喜多秀家の一万七千の軍団。 今そこには、古戦場を記録する[関ヶ原古戦場」(字神田柴之内西田)の石碑が立っている。その場所は、背後に小丘が控える、水田のひろがる閑静な地である。そこが関ヶ原の開戦地であったとは到底思えない。
石碑のわきに立って瞑目すると、兵士たちの叫喚やどよめきが聞こえてきそうである。背後の山蔭から鬨の声があがるような気さえする。
この開戦地の碑がある場所から少し離れたところに宇喜多秀家の陣跡がある。そこは天満山と呼ばれる山の麓で、昼なお暗い、うっそうたる杉林につつまれた場所である。そこに天満神社がひっそりと建つが、合戦当時、いちばんの激戦地であったところとは思えない静けさに満ちている。
西軍の大谷吉継軍が陣を敷いていたのは、宇喜多秀家の陣のさらに後方であった。大谷軍は、目の前の松尾山にこもる小早川秀秋の万一の背信に備えるために、そこに布陣していたのである。これを東軍の藤堂高虎と京極高知軍とが攻撃した。
同じく西軍の小西行長軍は織田有楽、寺沢広高の軍勢と戦っていた。島津惟新の一千もみずからの陣を必死に死守していた。
* * *
すでに開戦から三時間という時がたっていた。笹尾山の石田三成は、そろそろ総攻撃開始を考えていた。陽はすでに頭上高くかかっている。霧もようやく消えて、青空が顔を出していた。
その時であった。笹尾山にひとすじの狼煙があがったのである。それは、かねてからの総攻撃開始の合図であった。総攻撃の狼煙を合図に、関ヶ原南方の松尾山に陣取る小早川秀秋軍と東方の南宮山麓にいる毛利秀元、吉川広家軍などが動く手はずになっていた。
この時、小早川軍一万五千有余、毛利らの軍勢二万八千あまり。 その合図とともに、西軍八万数千という総軍勢が戦闘に加わるはずであった。総大将石田三成もそれを期待していた。
ところが、狼煙があがったにもかかわらず、松尾山の小早川軍と南宮山の軍勢は動かなかった。なかでも、松尾山にいる小早川の去就は、かねてから懸念されていたことだった。不安が現実になったのである。それだけに三成の焦燥はたとえようもなかった。
この小早川の動きは、東軍の総大将徳川家康にとっても、かたずをのむ思いで見守るに値する関心事であった。 松尾山はちょうど東西両軍の動きを見下ろす位置にある山である。標高三百ほどの山頂に陣を張った小早川秀秋は、この時、何を考えていたのだろうか。
過ぎ去った過去のできごと、記憶、そのなかに渦巻く怨念、遺恨が、その時、秀秋の胸のうちにあらためてどす黒くよみがってきていた。
すでに秀秋は東軍にも通じていたのである。が、東西いずれの軍勢に加担するかについては、ぎりぎりまで逡巡していた。両軍から軍勢を動かすように迫るやつぎ早やの催促にもじっと動かなかった。それほどに東西両軍の勝敗のほどは定かではなかった。
ちょうど昼過ぎであっただろうか。ついに小早川秀秋は、号令を発したのである。その内容は、松尾山下に陣取る西軍の大谷吉継を攻撃するというものであった。松尾山に満を持していた一万五千ほどの軍勢は、いっせいに鬨の声をあげながら山を駆け降りて行った。
この小早川軍の動きが、結局、この戦いの成敗を決したのであった。小早川秀秋が東軍に加担するや、西軍のなかにあったいくつかの軍勢が同じように、裏切りをし、東軍に加わっていった。ここで一挙に、西軍の二万という勢力が東軍に寝返ったのである。
小早川軍の大谷軍攻撃を見届けたあと、徳川家康は東軍の一斉攻撃を命令した。時に午後一時。 小早川軍の攻撃にさらされた大谷軍は壊滅し、大谷吉継は自刃する。時を移さず、四千の小西行長軍、一万七千の宇喜多秀家軍も敗走する。行長、秀家の両将は伊吹山方面に姿をくらました。
同じ頃、南宮山付近に布陣していた毛利、吉川らの巨大な軍勢も退却していた。 そうしたなか、孤塁を守っていたのは笹尾山に布陣する石田三成軍であった。が、そこには東軍が雲霞のように迫っていた。
三成はいくどか自軍に攻撃命令を出すが、多勢に無勢、もはや敗退するほかなかった。やがて、西軍の総大将石田三成も北国街道を北に向けて退いていった。
最後に残ったのは、笹尾山の南方八百メートルほどに布陣していた島津惟新軍であった。島津軍は少数ながら鉄砲を使ってよく戦った。が、衆寡適せずであった。 あとは敗走するしかなかった。島津軍は敵中を突破し、北国街道を南下していった。窮鼠猫を噛むのたとえのような敗走であった。
* * *
天下分け目の戦いが終息したのは午後4時頃であった。その頃、空がにわかにかき曇り、やがて雨が沛然と降りはじめたという。 戦場のあちこちに数え切れないほどの戦死者の骸が無造作にころがっていた。旗さしものが散乱し、その中を、主を失った軍馬が悲しいいな鳴きをあげながら、所在なくあたりを駆けずりまわっていた。藤古川には死者の遺体があふれ、川が紅いに染まったという。
そういえば、松尾山から天満山に向かう途中に黒血川という名の川が流れている。関ヶ原の記憶を呼びもどさせるような川名である。 東軍が勝利の勝鬨をあげると、総大将徳川家康は、陣野場に置いた本陣で、討ち取られた西軍の武将たちの首実験を開始した。
それは恒例のものとはいえ、いまだかってないほどの、おびただしい数の首級であった。首実験したあと、それらの首級は、東西の首塚にねんごろに埋葬されたのである。 首実験を終えた家康は、その後、さらに西に移動し、天満山の西南、藤古川の台地上で、東軍諸将に引見した。年来の部下の者たちに交じって、この戦いの帰趨を決する役割を果たした小早川秀秋の顔もそこにあった。 ところで、戦い敗れた西軍の諸将は、どこに姿を消したのだろうか。
石田三成は笹尾山を逃れたあと、北国街道づたいに伊吹山中に姿を消した。小西行長も同じく伊吹山に逃げこんだ。宇喜多秀家は近江を目指して敗走した。
戦後、東軍による落ち武者狩りは執拗を極めた。それに百姓が手を貸した。山狩りはけもの道にまでおよび、落ち武者が探索された。
思えば関ヶ原の戦いからさかのぼること一千年ほど前、同じ地で、同じような天下分け目の戦いがおこなわれたのである。世に壬申の乱と呼ぶ。
その戦いは、藤古川をはさんでくりひろげられたと伝えられている。東軍の天武天皇と西軍の弘文天皇との争いは、結局、東軍勝利で終わった。
今はのどかな田園風景のなかにある古戦場。そこに点在する史跡のひとつひとつを訪ね歩きながら、私は、そこで命を落とした、数えきれない兵士たちのうめきのようなものを感じないではいなかった。
関ヶ原にはたしかに地の霊が埋めこまれているのである。
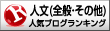
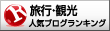
それはこの国を二つに分ける天下分け目の戦いとなった。その後の日本の歴史の歩みを決定づけた出来事となった。
東海道本線でも数少ない各駅停車の列車の停車駅、関ヶ原の駅に降り立ち、地図を片手に歩き出せば、そこがすでに古戦場のただなかであることを知らされる。 私がまずはじめに訪れたのは、関ヶ原駅のすぐ裏手、つまり北側にある東の首塚と呼ばれる場所であった。東と称しているところを見ると西の首塚というものもあるのだろうと、地図をのぞけば、そこより西の方、中山道沿いに西の首塚なるものがあった。
まずは、「東の首塚」と記された石碑の立つ朱塗りの門をくぐる。あまり広くない境内には椎の大木がうっそうと繁り、蝉がかまびすしく鳴いている。焼きつくような夏の強い日差しもここには届かないようである。
寺とも神社ともつかない敷地内の奥にひとつの塚があり、近くに祠がひっそりと建っている。その塚は首級墳墓らしく、そばに立つ石碑がそのいわくを刻んでいる。が、風雪をへた石碑の文字はほとんど判読できないほどである。かろうじて読みくだしてみると、そこには東西両軍の戦没兵士たちを埋葬してあることが記されてあった。 かつて、ここには累々と首級が並べられたことであろう。戦死者の遺体が無造作に打ち棄てられていたにちがいない。ふいに凄惨な情景が頭に浮かびあがる。
ここはまた、東軍の先鋒隊であった松平忠吉、井伊直政両軍の陣営がおかれたところでもある。松平、井伊の両軍は、敵中突破して逃走した西軍の薩摩藩の島津惟新を追って、いっとき、この地に陣を敷いたのである。 東の首塚をあとにして、やや上り勾配の野良道をさらに北に進むと、西軍の本陣があった笹尾山に至る。
そこは、いわずと知れた西軍の総大将石田三成が布陣したところである。 関ヶ原の戦いをマクロ的に把握するには、この笹尾山を中心に布陣した西軍と、これを攻めあげる東軍の布陣の概要をまず頭に入れておく必要があろう。
そもそも関ヶ原は、東西4キロ、南北2キロほどのひろがりをもつ細長い盆地である。北方にそびえる伊吹山とそれにつらなる峰々が、南と東方向に向かってゆるやかなスロープをつくり、一方、南方からは鈴鹿山脈が触手をのばしている。
その盆地を貫通するように中山道が東西に走り、そして、その中央部から西北方向に北国往還が、また東南方向には伊勢街道が延びる。
この関ヶ原をめざして東軍は大垣方面から中山道を西進、そして、西軍はそれに追われるように大垣方面から西に退却し、関ヶ原に陣を構えたのである。
西軍は夜を徹して、鳴りをひそめるように進んだといい、対照的に、東軍は鬨の声をあげながら、全力で疾駆したのである。追う者と追われる者とのちがいであった。 そして、西軍は、笹尾山から南西につらなる山々を背に、石田三成、島津惟新、小西行長、宇喜多秀家、大谷吉継の各部隊が布陣、一方、徳川家康を総大将とする東軍は、家康のいる本陣・桃割山を中心に西面して二列縦隊で布陣した。 両者のこの布陣の仕方は、地形のうえでは、西軍が東軍をちょうど見下ろす格好になり、陣取りの形からすれば断然西軍有利ということになる。が、実際には、そのような結果にならなかった。
* * *
戦いがはじまったのは、慶長5年(1600)9月15日、午前8時頃であった。夜が明けたにもかかわらず、あたりには濃い霧がたちこめていた。それが一瞬途切れたのである。 霧が切れると、敵も味方も、あっと息を呑むような光景がそこにあらわれ出た。東西四キロほどの盆地に、数え切れないほどの軍勢が陣形をつくってひしめき、戦闘態勢をととのえていたのである。
色とりどりの軍旗がはためいている。風になびく長い旗竿、意匠をこらした馬印が薄日に輝やいている。そのおびただしい数に、両軍の将兵は、あらためて我が身を奮い立たせた。この時、関ヶ原には東西両軍あわせて、じつに十五万という軍団が集結していたのである。
霧の合間をぬうように、まず東軍の中堅にいた井伊直政、松平忠吉隊が前進した。それを目撃した同じく東軍の福島正則隊が、遅れてはならじと南側面から前に進み、前方にひかえる西軍の宇喜多秀家隊に向かっていった。 さらに、これらの動きを見守っていた東軍の黒田長政隊、西軍の小西行長隊が動きだした。
こうして、合戦の火ぶたは切って落とされたのである。 東軍が攻める目標としたのは、当然のことながら、笹尾山に陣をかまえる西軍の総大将、石田三成であった。笹尾山は北国街道沿いにある小高い山で、そこからは東軍の動きが一望である。
いま、その周辺は広々とした田園地帯である。当時も同じような風景がひろがっていたことだろう。東軍は、このゆるい勾配のある地形を笹尾山に向かって押し進んでいった。 こうして、東軍、西軍入り乱れての戦いがはじまったのであるが、はじめは、やや西軍有利という状態で推移していった。
上手から東軍の攻勢を迎えうつ形になる西軍の方が、とうぜんのことながら敵の動きを見通せる分だけ地の利に勝っていたといえる。東軍の本陣ははじめ、関ヶ原東方にある桃配山にあった。桃配山は壬申の乱の際に、天武天皇が将兵を激励して桃を配ったという伝説が残る山である。総大将、徳川家康はそこで総指揮をとっていた。
ところが、戦いがはじまると、戦局の掌握には、そこでは、あまりにも遠すぎることが分かった。今そこには家康の腰掛け岩と机石が残る。
家康が本陣をさらに西にある陣場野に移したのは午前11時頃である。その本陣跡は現在、公園になっていて、そこに土囲いされた土壇が残る。その土壇は家康が敵の武将を首実検したところであるという。いかにも首実験した場所にふさわしい雰囲気がただよう。 それにしても、いくつも無念の形相をした生首がそこにさらされていたかと思うと、思わず背筋が寒くなる。
じつは、その土壇と土囲いは、後年になって、この地の領主が幕府の命を受けて復元したものだという。幕府は、いわば、徳川政権誕生の重要な歴史的事蹟として、この地を史跡として保存しようと企図したのである。
* * *
開戦から一時間ほどたった頃、石田三成率いる六千余りの将兵たちは、東軍の集中攻撃の渦中にあった。
戦いに臨んで、すでに石田隊は笹尾山の前方にひろがる田の中に竹矢来の柵を二重にめぐらして防備をととのえていた。
石田隊は兵を三隊に分け、そのうちの二隊を島左近と蒲生郷舎が指揮して、竹矢来の前面と中ほどにそれぞれ布陣した。
そして、背後の笹尾山の山頂に三成が本陣を置いた。そこには五挺の大筒が備えられてもいた。島も蒲生も三成を真に慕う忠臣であった。士気は高かった。 笹尾山は小さな山である。そこを中心に、じつに六千余りもの将兵が立て籠もっていたのである。前方に田園がひらけているとはいえ、このせまい山域を中心に六千という数はかなりの数である。文字通り、人がひしめく状態であったにちがいない。本陣に身を置く石田三成の不安と焦燥が目に見えるようである。今そこには「関ヶ原古戦場、石田三成陣地」と記された記念碑が立っている。
この笹尾山の攻撃に、まず先鞭をつけたのは黒田長政の別動隊であった。別動隊は笹尾山の前面を守っていた島左近隊と衝突した。この別動隊は鉄砲隊を配備していた。島隊は銃火にさらされて壊滅。島左近自身も重傷を負って退却した。その間隙をぬうようにして、ここぞとばかりに、東軍の黒田長政の本隊、細川忠興、加藤嘉明などの諸隊が石田三成の本陣に斬りこんでいった。
笹尾山は混乱の渦の中にあった。石田三成みずからが陣頭指揮をした。重傷の島左近も槍を縦横にふりまわしながら戦ったが、東西入り乱れる兵士の中に、いつしか姿を消した。 この混乱にもかかわらず石田隊は持ちこたえていた。午前10時ころになっても、東西両軍の力の均衡は破られなかった。
そんななか、各所で白兵戦がくりひろげられていた。笹尾山の南方、天満山の麓に陣取った宇喜多秀家隊とそれを攻める福島正則隊が最初に衝突したのは、前述のように、午前8時ごろであったが、その後、両者、一進一退の攻防戦がつづいていた。
大馬印を押し立てて、六千あまりの兵を指揮するのは福島正則、それを迎え撃つ宇喜多秀家の一万七千の軍団。 今そこには、古戦場を記録する[関ヶ原古戦場」(字神田柴之内西田)の石碑が立っている。その場所は、背後に小丘が控える、水田のひろがる閑静な地である。そこが関ヶ原の開戦地であったとは到底思えない。
石碑のわきに立って瞑目すると、兵士たちの叫喚やどよめきが聞こえてきそうである。背後の山蔭から鬨の声があがるような気さえする。
この開戦地の碑がある場所から少し離れたところに宇喜多秀家の陣跡がある。そこは天満山と呼ばれる山の麓で、昼なお暗い、うっそうたる杉林につつまれた場所である。そこに天満神社がひっそりと建つが、合戦当時、いちばんの激戦地であったところとは思えない静けさに満ちている。
西軍の大谷吉継軍が陣を敷いていたのは、宇喜多秀家の陣のさらに後方であった。大谷軍は、目の前の松尾山にこもる小早川秀秋の万一の背信に備えるために、そこに布陣していたのである。これを東軍の藤堂高虎と京極高知軍とが攻撃した。
同じく西軍の小西行長軍は織田有楽、寺沢広高の軍勢と戦っていた。島津惟新の一千もみずからの陣を必死に死守していた。
* * *
すでに開戦から三時間という時がたっていた。笹尾山の石田三成は、そろそろ総攻撃開始を考えていた。陽はすでに頭上高くかかっている。霧もようやく消えて、青空が顔を出していた。
その時であった。笹尾山にひとすじの狼煙があがったのである。それは、かねてからの総攻撃開始の合図であった。総攻撃の狼煙を合図に、関ヶ原南方の松尾山に陣取る小早川秀秋軍と東方の南宮山麓にいる毛利秀元、吉川広家軍などが動く手はずになっていた。
この時、小早川軍一万五千有余、毛利らの軍勢二万八千あまり。 その合図とともに、西軍八万数千という総軍勢が戦闘に加わるはずであった。総大将石田三成もそれを期待していた。
ところが、狼煙があがったにもかかわらず、松尾山の小早川軍と南宮山の軍勢は動かなかった。なかでも、松尾山にいる小早川の去就は、かねてから懸念されていたことだった。不安が現実になったのである。それだけに三成の焦燥はたとえようもなかった。
この小早川の動きは、東軍の総大将徳川家康にとっても、かたずをのむ思いで見守るに値する関心事であった。 松尾山はちょうど東西両軍の動きを見下ろす位置にある山である。標高三百ほどの山頂に陣を張った小早川秀秋は、この時、何を考えていたのだろうか。
過ぎ去った過去のできごと、記憶、そのなかに渦巻く怨念、遺恨が、その時、秀秋の胸のうちにあらためてどす黒くよみがってきていた。
すでに秀秋は東軍にも通じていたのである。が、東西いずれの軍勢に加担するかについては、ぎりぎりまで逡巡していた。両軍から軍勢を動かすように迫るやつぎ早やの催促にもじっと動かなかった。それほどに東西両軍の勝敗のほどは定かではなかった。
ちょうど昼過ぎであっただろうか。ついに小早川秀秋は、号令を発したのである。その内容は、松尾山下に陣取る西軍の大谷吉継を攻撃するというものであった。松尾山に満を持していた一万五千ほどの軍勢は、いっせいに鬨の声をあげながら山を駆け降りて行った。
この小早川軍の動きが、結局、この戦いの成敗を決したのであった。小早川秀秋が東軍に加担するや、西軍のなかにあったいくつかの軍勢が同じように、裏切りをし、東軍に加わっていった。ここで一挙に、西軍の二万という勢力が東軍に寝返ったのである。
小早川軍の大谷軍攻撃を見届けたあと、徳川家康は東軍の一斉攻撃を命令した。時に午後一時。 小早川軍の攻撃にさらされた大谷軍は壊滅し、大谷吉継は自刃する。時を移さず、四千の小西行長軍、一万七千の宇喜多秀家軍も敗走する。行長、秀家の両将は伊吹山方面に姿をくらました。
同じ頃、南宮山付近に布陣していた毛利、吉川らの巨大な軍勢も退却していた。 そうしたなか、孤塁を守っていたのは笹尾山に布陣する石田三成軍であった。が、そこには東軍が雲霞のように迫っていた。
三成はいくどか自軍に攻撃命令を出すが、多勢に無勢、もはや敗退するほかなかった。やがて、西軍の総大将石田三成も北国街道を北に向けて退いていった。
最後に残ったのは、笹尾山の南方八百メートルほどに布陣していた島津惟新軍であった。島津軍は少数ながら鉄砲を使ってよく戦った。が、衆寡適せずであった。 あとは敗走するしかなかった。島津軍は敵中を突破し、北国街道を南下していった。窮鼠猫を噛むのたとえのような敗走であった。
* * *
天下分け目の戦いが終息したのは午後4時頃であった。その頃、空がにわかにかき曇り、やがて雨が沛然と降りはじめたという。 戦場のあちこちに数え切れないほどの戦死者の骸が無造作にころがっていた。旗さしものが散乱し、その中を、主を失った軍馬が悲しいいな鳴きをあげながら、所在なくあたりを駆けずりまわっていた。藤古川には死者の遺体があふれ、川が紅いに染まったという。
そういえば、松尾山から天満山に向かう途中に黒血川という名の川が流れている。関ヶ原の記憶を呼びもどさせるような川名である。 東軍が勝利の勝鬨をあげると、総大将徳川家康は、陣野場に置いた本陣で、討ち取られた西軍の武将たちの首実験を開始した。
それは恒例のものとはいえ、いまだかってないほどの、おびただしい数の首級であった。首実験したあと、それらの首級は、東西の首塚にねんごろに埋葬されたのである。 首実験を終えた家康は、その後、さらに西に移動し、天満山の西南、藤古川の台地上で、東軍諸将に引見した。年来の部下の者たちに交じって、この戦いの帰趨を決する役割を果たした小早川秀秋の顔もそこにあった。 ところで、戦い敗れた西軍の諸将は、どこに姿を消したのだろうか。
石田三成は笹尾山を逃れたあと、北国街道づたいに伊吹山中に姿を消した。小西行長も同じく伊吹山に逃げこんだ。宇喜多秀家は近江を目指して敗走した。
戦後、東軍による落ち武者狩りは執拗を極めた。それに百姓が手を貸した。山狩りはけもの道にまでおよび、落ち武者が探索された。
思えば関ヶ原の戦いからさかのぼること一千年ほど前、同じ地で、同じような天下分け目の戦いがおこなわれたのである。世に壬申の乱と呼ぶ。
その戦いは、藤古川をはさんでくりひろげられたと伝えられている。東軍の天武天皇と西軍の弘文天皇との争いは、結局、東軍勝利で終わった。
今はのどかな田園風景のなかにある古戦場。そこに点在する史跡のひとつひとつを訪ね歩きながら、私は、そこで命を落とした、数えきれない兵士たちのうめきのようなものを感じないではいなかった。
関ヶ原にはたしかに地の霊が埋めこまれているのである。









