秩父は山深い地である。いまでこそ、その深い山をぬって、舗装された山道が通じているが、その出来事が起きた時代には、どれほどか辺鄙な山峽であったことか想像される。
地図を広げて見ると、秩父という地が荒川によって引き裂かれ、東西に分断されている盆地状の地域であることが分かる。その荒川は、山梨、埼玉、長野三県の分水嶺にあたる甲武信岳に源を発して東に流れ、さらに北流して、この盆地を貫いている。
地元では、荒川を挟んで東側を東谷、西側を西谷(にしやつ)と呼ぶ。なかでも、西谷と呼ばれる地は、西方向に奥行きが深く、そこには大小の河川が山峽をぬうように流れて、荒川に注いでいる。
集落は、それら河川のつくる沢に沿って点々と連なっている。それらは山道をぬい、峠を越え、よもやこのようなところにと思われる山の急斜面や、谷の底にうずくまるように、突然、その姿を現すことがある。
集落はどれも家数が少ない。それは十戸、二十戸の規模である。家々の前に広がる、わずかな空間に耕地がつくられ、互いの耕地を結びつける私道が行き交っている。せこ道と呼ばれるこの私道が、唯一、村人たちの交流の回路になっている。
秩父は東西南北、山に囲まれていると言っていい。それがこの地を外界からへだてることになったと同時に、秩父という独特の風土を形づくったと言える。
* * *
その出来事の真相を明らかにするためには、明治十七年という遠い過去にさかのぼらなければならない。
当時、日本全国にはデフレの波が押し寄せていた。時の政府が明治一四年以来おこなっていた緊縮政策による結果である。政府が断行していた不換紙幣の整理と軍備拡張のための増税は、金融閉塞という名の金づまりをきたし、国民を苦しめていた。
養蚕による生糸の生産地として繁栄してきた秩父も例外ではなかった。
この頃の秩父の農民の主業は養蚕で、農耕山林の仕事はむしろ副業であった。いわば、彼らは小商品生産者的農民であったといえる。
ところが、その生産物である生糸の大暴落で、彼らは一様に高利貸からの借金がかさみ、ある者は一家逃散、ある者は自らの命を断つという仕方で、借金地獄から逃れようとする者が続出した。事態は悪化の一途をたどっていた。身代限りという名の生活破産が蔓延した。それは、昔からの生活基盤である共同体の崩壊を予感させた。
こうしたなか、高利貸たちだけが豊かさを享受していた。彼らは狡猾に農民に対した。
借金の累積に苦しむ農民には苛酷に、一方で役所や警察にはあらかじめ手を打つことで抱き込み、不当な借金の実態を隠蔽した。当然のことながら農民の生活は逼迫していった。
が、農民たちも耐え忍んでばかりいたのではなかった。山村共同体の崩壊を目の前にして、危機感は募り、彼らは自らを守るために組織づくりをはじめた。困民党の成立である。
やがてその組織は、急速にひろがっていった。組織づくりは山峽を縫い、耕地を駆け巡り、集落から集落へ隠密裡に何カ月にもわたって積み重ねられていった。
組織づくりの活動は容易ではなかった。困窮の極限にあってもなお現状に甘んじようとする農民を説得し、組織化するのは、まさに石に穴をうがつ努力に等しかった。
が、ついに、彼らの努力が成果を結ぶ時がくる。山林集会と呼ばれる農民たちの集まりが、警察の目を逃れ、深い山林の中で幾度も行われるようになる。
そうこうしている間にも、農民たちの生活はますます困窮化していった。今まで進めてきた金貸しとの話し合いによる交渉ではなにも解決しないことを、彼らは次第に悟っていった。
状況が切迫するなかで、一般農民がリーダーたちを突き上げていく。もはや直接行動に出るしかないというのが彼ら一般農民の考えであった。山は燃えていた。
* * *
ついに、明治一七年十一月一日が決起の日と定められた。そして、その日がやってくる。
晴れ渡った秋空が広がるその日の昼過ぎから夕刻にかけて、どの山峽の集落からも続々と農民たちが下吉田村の椋神社目指して動きはじめた。椋神社は阿熊渓谷を東にみる森につつまれた高台にある。
その数およそ三千名。いずれの農民も白襷、白鉢巻姿で、各々刀や火繩銃、竹槍を手にしていた。椋神社は秩父神社とともに秩父盆地を代表する神社である。
黒々とした杉の木立にまざって、見事に紅葉した大きな銀杏の木々が立ち並ぶ境内には秋の気配が濃く漂っていた。
神社のまわりに広がる田の畦道につくられた稲架には、取り込みの遅れた黄金色した稲の束が並べられていた。あるいは、迫り来る冬にそなえて麦まきのさなかであった。
そんな矢先であった。武装した農民たちが下吉田村にある椋神社に参集したのである。
日が落ちると共に、武装農民の黒い塊りが境内にあふれた。十四夜の月が煌々と中天に輝やく夜の神社。今、その神社の拝殿前にひとりの黒い男の影が浮かびあがっている。
それは総理にかつぎ上げられた田代栄助の小太りのずんぐりとした黒い影である。彼は大宮郷に住む信望の厚い博徒の貸元であった。
まず、田代が困民軍の役割を発表。つづいて、参謀長の菊池貫平が高らかに軍律五カ条を読みあげた。菊池は秩父の峠を越えて、はるばる信州から馳せ参じた代言人をなりわいとする男である。
午後八時、鬨の声と共に、甲乙二隊に分かれた軍団は、竹ぼらを吹き鳴らし、それぞれが小鹿野を目指して出発した。
部隊は、鉄砲隊、竹槍隊、帯剣隊とからなる二列の長い縦隊をなして進んで行った。その規模といい、規律のとれたさまといい、それは百姓一揆とはいえない、まさしくひとつの意志をもった農民の軍団であった。
甲大隊の隊長は新井周三郎といった。彼は小学校の若き教師である。甲隊千五百名ほどの農民は吉田川をさかのぼり、巣掛峠を越えて小鹿野の町を西から急襲した。
一方、乙大隊はこれまた教員の隊長飯塚森蔵の指揮のもと、椋神社をそのまま南に下り、下小鹿野に出、東から小鹿野町に入った。小鹿野の町を東西から挟撃する作戦であった。
小鹿野の町は街道筋に細長く延びる古い町で、町を背に低い山並みが連なっている。その山影が黒々と夜空を画し、町を一層暗くしていた。
当時、小鹿野町は大宮郷に次いで大きな町であった。商家も多く、西秩父の農村を後背地に控えて、高利貸が集まっていた。
困民軍が小鹿野を襲ったのは、そこに彼らが仇敵とする高利貸がいたからである。怒涛の勢いで町に入った農民軍は高利貸の家を打ち壊し、火を放った。が、そこには規律というものがあった。
農民軍団は、その夜、町の北はずれにある木立に包まれた諏訪神社(現小鹿神社)に参集し、近在の農家に炊き出しを命じて露営した。
町は不気味に静まりかえった夜を迎えた。 翌二日早暁、困民軍は隊列を組みながら黒い塊りとなって諏訪神社を出立。隊伍の先頭には「新政厚徳」の大旗がひるがえっていた。
目指すは郡都大宮郷である。鉄砲隊を先頭に、三千を越す農民軍は、長い隊列を組んで町の東方面に通じる街道を進む。進むうちに数が増えてゆく。
やがて軍団は小鹿野原と呼ばれる桑畠の広がる地に出る。その畠道をぬい、やがて赤平川を渡る。そこからは、ややゆるい登りとなり、それを登りつめると小鹿坂峠に出る。
時に午前十一時。峠からは、目の前に武甲山の無骨な山容が立ちはだかるのが望めた。眼下には秋の陽を溶かして、荒川がのどかに流れているのが見え隠れする。
その対岸には、黒い塊りとなった大宮郷の家並みが南北に細長く望める。農民たちの胸の内には、万感の思いがあふれていた。
それは、今ようやく、自分たちの苦しみが何がしか解き放たれるのだ、という思いであった。新しい世界をこれから自分たちでつくってゆくのだ、という希望に膨らんだ思いでもあった。
峠を少し降りたところに秩父札所二十三番の音楽寺がある。黒い軍団はそこにも群がっていた。
一瞬、皆が厳粛な気分に満たされている、その時であった。音楽寺の鐘が力をこめて打ち鳴らされた。
それはあらかじめ申し合わせておいた大宮郷へ突入するための合図であった。鐘の音は高らかに、響きのある音色を、澄みわたった大気のなかに溶けこませながら流れてゆく。
期せずして、勝鬨の声があがる。誰の胸の内にもはち切れる怒りがこみ上げてきていた。 歓声と共に、農民軍は、音楽寺から荒川に下るつづら折りの狭い山道をいっせいに駆け降りて行く。
秋色濃い荒川の河川敷きが目の前に広がる。誰もが一気に川を渡るつもりでいた。荒川の水嵩が、人が歩いて渡れるくらいになっていることを、彼らは先刻承知していたのである。
この時、彼ら農民軍の数は、駆け出しと呼ばれる強制参加の呼びかけの結果、五千という規模に膨らんでいた。この蜂起にあたって、駆け出しという伝統的な手法が使われたことには意味があった。それは共同体を守り抜くための、いわば暗黙の共同体規制であったのである。
われ先にと川を渡って行く農民軍の塊りは、こうして郡都大宮郷になだれ込んで行ったのである。
* * *
農民軍が大宮郷に入った時、郡の権力機関はすでに事の成り行きを察知して姿をくらましてしまっていた。
この事態は農民軍の予期せぬことであった。警察をはじめとする権力側の抵抗に遭うであろうことをみな予測していたのである。
が、実際はそうならなかった。農民たちの気持ちには少し調子抜けの感があったにちがいない。
それでも、彼らは事前の打ち合わせどおりに、郡役所、警察署、裁判所、監獄、そして高利貸を次々と急襲していった。総指揮をとったのは副総理の加藤織平であった。
猟銃が放たれるのを合図に、攻撃目標への乱入が始まる。書類が引き裂かれ、投棄され、その一部に火がつけられる。冷えきった空気に包まれた、決して広いとは言えない市中の街道筋には、至るところに紙切れが散乱し、そのさまは、あたかも吹雪が舞うようであったという。
壊された高利貸七軒、同じく火を放たれたもの三軒。いずれも貸金証書が破棄されたことは言うまでもない。
一方、豪家を対象に、軍用金の調達が行われた。その際、総理田代栄助名義の革命本部発行の受領書が出されている。また、刀剣の借用や炊き出しの要請も行われた。
今や大宮の町はパニック状態であった。商家のほとんどが鎧戸を閉めてしまっていたため、町は暗さが一層きわだった。その中を怒号と歓声がどよめき、農民軍の黒い塊りがうごめいていた。
疾風のように通り過ぎた農民軍の破壊行為が一段落すると、町は奇妙に静まりかえった。農民軍が、うっそうたる樹木に包まれた秩父神社の境内に撤退したからだ。すでに東の空がしらみはじめる頃であった。
その後、軍団は郡役所を革命本部と定め、分営を神社近くの小学校とし、そこに屯集したのである。
明けて十一月三日。その日は天朝節の日であった。一夜去って困民軍は、ここで急速に、その目標を失うことになる。昨夜来の騒ぎがまるで嘘のように、軍団全体の動きが鈍くなっていた。
その頃、憲兵隊と警察の一団が群馬県側から西谷の奥にある城峰山に進出し、早晩、大宮郷に向かうだろうという情報が困民軍の本営にもたらされた。
軍団は、それを迎え撃つために総勢を三隊に分けることに決定。甲隊は西からの襲撃に備え荒川の竹の鼻渡しを、乙隊は北からの攻撃に対して大野原を、そして、丙隊は大宮郷にとどまることになった。
その頃、しきりに虚報が飛び交っていた。それら虚報に躍らされて、軍団は統率を乱しはじめていた。当初の決定に反して、甲隊は小鹿野から下吉田方面へ、乙隊は大野原からさらに北上して皆野へ進む。
こうした動きのなかで、激しい戦闘も行われている。ひとつは、甲隊の別動隊五〇〇名が、城峰山のふもとにある矢納村で、群馬方面からやってきた警官隊と衝突、警察側に大きな損害を与えた。
さらに、皆野に進んだ乙隊は、憲兵隊と荒川の親鼻の渡し付近で戦闘をくりひろげ、優勢に戦いを進めた。憲兵隊はこの時、最新式の村田銃を使用している。
四日に入り、警察、憲兵隊、東京鎮台一中隊の守備態勢は一段と強化された。秩父に至るすべての街道が封鎖されたのである。
大宮郷にとどまっていた丙隊のほとんどが皆野にいる乙隊に合流した今、大宮郷はもぬけの殻になっていた。町内では青年層が赤鉢巻きで武装し、困民軍を迎え撃つために自衛隊が組織されていた。しばしの無政の郷は、はかなく消え去ったのである。
時を同じくして、大宮郷に警察と軍隊が迫っていた。荒川の両岸を大宮郷をめざした各一個小隊の東京憲兵隊は、皆野を通り、大宮郷に入った。十一月五日のことである。
すでにこの時、皆野に布陣していた困民軍の本営は解体し、田代栄助らの幹部は、いずこともなく姿をくらましていたのである。
この本隊の解体のあと、秩父郡に隣接する児玉郡の金屋に進出した大野苗吉に率いられた一隊があった。彼らは東京鎮台兵との激しい戦いのあと壊滅した。
一方、信州から参加した菊池貫平に率いられ、信州へ転戦した一隊があった。彼らは神流川沿いの群馬県側の山中谷をぬけ、佐久の東馬流まで転戦し、そこで力尽き壊滅した。今そこには、「秩父暴動戦死者之墓」と記された立派な碑が建てられている。
警察は、十一月五日、早くも事件参加者の逮捕を開始している。大宮郷、小鹿野、熊谷、八幡山に暴徒糾問所が設けられ取り調べがはじまった。
その結果、埼玉県内の逮捕者三三八六名という数にのぼった。内訳は重罪二九六名、軽罪四四八名、罰金二千六四二名というものであった。重罪中には、死刑七名を含む、行方知れずの者もいたのである。
* * *
事件は終息し、秩父の山峽に、一見、もとの静かさが戻ったかのようであった。
が、事件後、半年たった明治一八年六月二日付けの「東京日々新聞」は、秩父の現状を以下のようになまなましく伝えていたのである。
「大小の別なく、人家は皆食物に窮し、特に中等以下の人民の惨状は実に目も当てられず・・・。大抵右の貧民は小麦のフスマ或は葛の根を以て常食とし、死馬死犬のある時は悉く秣場(まぐさば)に持ち往きて皮を剥ぎ、其肉を食ふを最上とす」
生活の困窮の果てに蜂起した秩父の農民の意思は、強大な権力の前に空しく潰えたのであるが、事件後、彼らの窮状は、さらに苛烈をきわめ、農民たちの頭上に重くのしかかってきていたのである。
それでもなお、蜂起に参加した秩父の農民たちは、幾重にも連なる山々の峰を日々見つめながら生活するしか手だてはなかったのである。そこで生をうけ、育った者にとって、秩父は決して捨て去ることのできない場所であった。
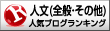
地図を広げて見ると、秩父という地が荒川によって引き裂かれ、東西に分断されている盆地状の地域であることが分かる。その荒川は、山梨、埼玉、長野三県の分水嶺にあたる甲武信岳に源を発して東に流れ、さらに北流して、この盆地を貫いている。
地元では、荒川を挟んで東側を東谷、西側を西谷(にしやつ)と呼ぶ。なかでも、西谷と呼ばれる地は、西方向に奥行きが深く、そこには大小の河川が山峽をぬうように流れて、荒川に注いでいる。
集落は、それら河川のつくる沢に沿って点々と連なっている。それらは山道をぬい、峠を越え、よもやこのようなところにと思われる山の急斜面や、谷の底にうずくまるように、突然、その姿を現すことがある。
集落はどれも家数が少ない。それは十戸、二十戸の規模である。家々の前に広がる、わずかな空間に耕地がつくられ、互いの耕地を結びつける私道が行き交っている。せこ道と呼ばれるこの私道が、唯一、村人たちの交流の回路になっている。
秩父は東西南北、山に囲まれていると言っていい。それがこの地を外界からへだてることになったと同時に、秩父という独特の風土を形づくったと言える。
* * *
その出来事の真相を明らかにするためには、明治十七年という遠い過去にさかのぼらなければならない。
当時、日本全国にはデフレの波が押し寄せていた。時の政府が明治一四年以来おこなっていた緊縮政策による結果である。政府が断行していた不換紙幣の整理と軍備拡張のための増税は、金融閉塞という名の金づまりをきたし、国民を苦しめていた。
養蚕による生糸の生産地として繁栄してきた秩父も例外ではなかった。
この頃の秩父の農民の主業は養蚕で、農耕山林の仕事はむしろ副業であった。いわば、彼らは小商品生産者的農民であったといえる。
ところが、その生産物である生糸の大暴落で、彼らは一様に高利貸からの借金がかさみ、ある者は一家逃散、ある者は自らの命を断つという仕方で、借金地獄から逃れようとする者が続出した。事態は悪化の一途をたどっていた。身代限りという名の生活破産が蔓延した。それは、昔からの生活基盤である共同体の崩壊を予感させた。
こうしたなか、高利貸たちだけが豊かさを享受していた。彼らは狡猾に農民に対した。
借金の累積に苦しむ農民には苛酷に、一方で役所や警察にはあらかじめ手を打つことで抱き込み、不当な借金の実態を隠蔽した。当然のことながら農民の生活は逼迫していった。
が、農民たちも耐え忍んでばかりいたのではなかった。山村共同体の崩壊を目の前にして、危機感は募り、彼らは自らを守るために組織づくりをはじめた。困民党の成立である。
やがてその組織は、急速にひろがっていった。組織づくりは山峽を縫い、耕地を駆け巡り、集落から集落へ隠密裡に何カ月にもわたって積み重ねられていった。
組織づくりの活動は容易ではなかった。困窮の極限にあってもなお現状に甘んじようとする農民を説得し、組織化するのは、まさに石に穴をうがつ努力に等しかった。
が、ついに、彼らの努力が成果を結ぶ時がくる。山林集会と呼ばれる農民たちの集まりが、警察の目を逃れ、深い山林の中で幾度も行われるようになる。
そうこうしている間にも、農民たちの生活はますます困窮化していった。今まで進めてきた金貸しとの話し合いによる交渉ではなにも解決しないことを、彼らは次第に悟っていった。
状況が切迫するなかで、一般農民がリーダーたちを突き上げていく。もはや直接行動に出るしかないというのが彼ら一般農民の考えであった。山は燃えていた。
* * *
ついに、明治一七年十一月一日が決起の日と定められた。そして、その日がやってくる。
晴れ渡った秋空が広がるその日の昼過ぎから夕刻にかけて、どの山峽の集落からも続々と農民たちが下吉田村の椋神社目指して動きはじめた。椋神社は阿熊渓谷を東にみる森につつまれた高台にある。
その数およそ三千名。いずれの農民も白襷、白鉢巻姿で、各々刀や火繩銃、竹槍を手にしていた。椋神社は秩父神社とともに秩父盆地を代表する神社である。
黒々とした杉の木立にまざって、見事に紅葉した大きな銀杏の木々が立ち並ぶ境内には秋の気配が濃く漂っていた。
神社のまわりに広がる田の畦道につくられた稲架には、取り込みの遅れた黄金色した稲の束が並べられていた。あるいは、迫り来る冬にそなえて麦まきのさなかであった。
そんな矢先であった。武装した農民たちが下吉田村にある椋神社に参集したのである。
日が落ちると共に、武装農民の黒い塊りが境内にあふれた。十四夜の月が煌々と中天に輝やく夜の神社。今、その神社の拝殿前にひとりの黒い男の影が浮かびあがっている。
それは総理にかつぎ上げられた田代栄助の小太りのずんぐりとした黒い影である。彼は大宮郷に住む信望の厚い博徒の貸元であった。
まず、田代が困民軍の役割を発表。つづいて、参謀長の菊池貫平が高らかに軍律五カ条を読みあげた。菊池は秩父の峠を越えて、はるばる信州から馳せ参じた代言人をなりわいとする男である。
午後八時、鬨の声と共に、甲乙二隊に分かれた軍団は、竹ぼらを吹き鳴らし、それぞれが小鹿野を目指して出発した。
部隊は、鉄砲隊、竹槍隊、帯剣隊とからなる二列の長い縦隊をなして進んで行った。その規模といい、規律のとれたさまといい、それは百姓一揆とはいえない、まさしくひとつの意志をもった農民の軍団であった。
甲大隊の隊長は新井周三郎といった。彼は小学校の若き教師である。甲隊千五百名ほどの農民は吉田川をさかのぼり、巣掛峠を越えて小鹿野の町を西から急襲した。
一方、乙大隊はこれまた教員の隊長飯塚森蔵の指揮のもと、椋神社をそのまま南に下り、下小鹿野に出、東から小鹿野町に入った。小鹿野の町を東西から挟撃する作戦であった。
小鹿野の町は街道筋に細長く延びる古い町で、町を背に低い山並みが連なっている。その山影が黒々と夜空を画し、町を一層暗くしていた。
当時、小鹿野町は大宮郷に次いで大きな町であった。商家も多く、西秩父の農村を後背地に控えて、高利貸が集まっていた。
困民軍が小鹿野を襲ったのは、そこに彼らが仇敵とする高利貸がいたからである。怒涛の勢いで町に入った農民軍は高利貸の家を打ち壊し、火を放った。が、そこには規律というものがあった。
農民軍団は、その夜、町の北はずれにある木立に包まれた諏訪神社(現小鹿神社)に参集し、近在の農家に炊き出しを命じて露営した。
町は不気味に静まりかえった夜を迎えた。 翌二日早暁、困民軍は隊列を組みながら黒い塊りとなって諏訪神社を出立。隊伍の先頭には「新政厚徳」の大旗がひるがえっていた。
目指すは郡都大宮郷である。鉄砲隊を先頭に、三千を越す農民軍は、長い隊列を組んで町の東方面に通じる街道を進む。進むうちに数が増えてゆく。
やがて軍団は小鹿野原と呼ばれる桑畠の広がる地に出る。その畠道をぬい、やがて赤平川を渡る。そこからは、ややゆるい登りとなり、それを登りつめると小鹿坂峠に出る。
時に午前十一時。峠からは、目の前に武甲山の無骨な山容が立ちはだかるのが望めた。眼下には秋の陽を溶かして、荒川がのどかに流れているのが見え隠れする。
その対岸には、黒い塊りとなった大宮郷の家並みが南北に細長く望める。農民たちの胸の内には、万感の思いがあふれていた。
それは、今ようやく、自分たちの苦しみが何がしか解き放たれるのだ、という思いであった。新しい世界をこれから自分たちでつくってゆくのだ、という希望に膨らんだ思いでもあった。
峠を少し降りたところに秩父札所二十三番の音楽寺がある。黒い軍団はそこにも群がっていた。
一瞬、皆が厳粛な気分に満たされている、その時であった。音楽寺の鐘が力をこめて打ち鳴らされた。
それはあらかじめ申し合わせておいた大宮郷へ突入するための合図であった。鐘の音は高らかに、響きのある音色を、澄みわたった大気のなかに溶けこませながら流れてゆく。
期せずして、勝鬨の声があがる。誰の胸の内にもはち切れる怒りがこみ上げてきていた。 歓声と共に、農民軍は、音楽寺から荒川に下るつづら折りの狭い山道をいっせいに駆け降りて行く。
秋色濃い荒川の河川敷きが目の前に広がる。誰もが一気に川を渡るつもりでいた。荒川の水嵩が、人が歩いて渡れるくらいになっていることを、彼らは先刻承知していたのである。
この時、彼ら農民軍の数は、駆け出しと呼ばれる強制参加の呼びかけの結果、五千という規模に膨らんでいた。この蜂起にあたって、駆け出しという伝統的な手法が使われたことには意味があった。それは共同体を守り抜くための、いわば暗黙の共同体規制であったのである。
われ先にと川を渡って行く農民軍の塊りは、こうして郡都大宮郷になだれ込んで行ったのである。
* * *
農民軍が大宮郷に入った時、郡の権力機関はすでに事の成り行きを察知して姿をくらましてしまっていた。
この事態は農民軍の予期せぬことであった。警察をはじめとする権力側の抵抗に遭うであろうことをみな予測していたのである。
が、実際はそうならなかった。農民たちの気持ちには少し調子抜けの感があったにちがいない。
それでも、彼らは事前の打ち合わせどおりに、郡役所、警察署、裁判所、監獄、そして高利貸を次々と急襲していった。総指揮をとったのは副総理の加藤織平であった。
猟銃が放たれるのを合図に、攻撃目標への乱入が始まる。書類が引き裂かれ、投棄され、その一部に火がつけられる。冷えきった空気に包まれた、決して広いとは言えない市中の街道筋には、至るところに紙切れが散乱し、そのさまは、あたかも吹雪が舞うようであったという。
壊された高利貸七軒、同じく火を放たれたもの三軒。いずれも貸金証書が破棄されたことは言うまでもない。
一方、豪家を対象に、軍用金の調達が行われた。その際、総理田代栄助名義の革命本部発行の受領書が出されている。また、刀剣の借用や炊き出しの要請も行われた。
今や大宮の町はパニック状態であった。商家のほとんどが鎧戸を閉めてしまっていたため、町は暗さが一層きわだった。その中を怒号と歓声がどよめき、農民軍の黒い塊りがうごめいていた。
疾風のように通り過ぎた農民軍の破壊行為が一段落すると、町は奇妙に静まりかえった。農民軍が、うっそうたる樹木に包まれた秩父神社の境内に撤退したからだ。すでに東の空がしらみはじめる頃であった。
その後、軍団は郡役所を革命本部と定め、分営を神社近くの小学校とし、そこに屯集したのである。
明けて十一月三日。その日は天朝節の日であった。一夜去って困民軍は、ここで急速に、その目標を失うことになる。昨夜来の騒ぎがまるで嘘のように、軍団全体の動きが鈍くなっていた。
その頃、憲兵隊と警察の一団が群馬県側から西谷の奥にある城峰山に進出し、早晩、大宮郷に向かうだろうという情報が困民軍の本営にもたらされた。
軍団は、それを迎え撃つために総勢を三隊に分けることに決定。甲隊は西からの襲撃に備え荒川の竹の鼻渡しを、乙隊は北からの攻撃に対して大野原を、そして、丙隊は大宮郷にとどまることになった。
その頃、しきりに虚報が飛び交っていた。それら虚報に躍らされて、軍団は統率を乱しはじめていた。当初の決定に反して、甲隊は小鹿野から下吉田方面へ、乙隊は大野原からさらに北上して皆野へ進む。
こうした動きのなかで、激しい戦闘も行われている。ひとつは、甲隊の別動隊五〇〇名が、城峰山のふもとにある矢納村で、群馬方面からやってきた警官隊と衝突、警察側に大きな損害を与えた。
さらに、皆野に進んだ乙隊は、憲兵隊と荒川の親鼻の渡し付近で戦闘をくりひろげ、優勢に戦いを進めた。憲兵隊はこの時、最新式の村田銃を使用している。
四日に入り、警察、憲兵隊、東京鎮台一中隊の守備態勢は一段と強化された。秩父に至るすべての街道が封鎖されたのである。
大宮郷にとどまっていた丙隊のほとんどが皆野にいる乙隊に合流した今、大宮郷はもぬけの殻になっていた。町内では青年層が赤鉢巻きで武装し、困民軍を迎え撃つために自衛隊が組織されていた。しばしの無政の郷は、はかなく消え去ったのである。
時を同じくして、大宮郷に警察と軍隊が迫っていた。荒川の両岸を大宮郷をめざした各一個小隊の東京憲兵隊は、皆野を通り、大宮郷に入った。十一月五日のことである。
すでにこの時、皆野に布陣していた困民軍の本営は解体し、田代栄助らの幹部は、いずこともなく姿をくらましていたのである。
この本隊の解体のあと、秩父郡に隣接する児玉郡の金屋に進出した大野苗吉に率いられた一隊があった。彼らは東京鎮台兵との激しい戦いのあと壊滅した。
一方、信州から参加した菊池貫平に率いられ、信州へ転戦した一隊があった。彼らは神流川沿いの群馬県側の山中谷をぬけ、佐久の東馬流まで転戦し、そこで力尽き壊滅した。今そこには、「秩父暴動戦死者之墓」と記された立派な碑が建てられている。
警察は、十一月五日、早くも事件参加者の逮捕を開始している。大宮郷、小鹿野、熊谷、八幡山に暴徒糾問所が設けられ取り調べがはじまった。
その結果、埼玉県内の逮捕者三三八六名という数にのぼった。内訳は重罪二九六名、軽罪四四八名、罰金二千六四二名というものであった。重罪中には、死刑七名を含む、行方知れずの者もいたのである。
* * *
事件は終息し、秩父の山峽に、一見、もとの静かさが戻ったかのようであった。
が、事件後、半年たった明治一八年六月二日付けの「東京日々新聞」は、秩父の現状を以下のようになまなましく伝えていたのである。
「大小の別なく、人家は皆食物に窮し、特に中等以下の人民の惨状は実に目も当てられず・・・。大抵右の貧民は小麦のフスマ或は葛の根を以て常食とし、死馬死犬のある時は悉く秣場(まぐさば)に持ち往きて皮を剥ぎ、其肉を食ふを最上とす」
生活の困窮の果てに蜂起した秩父の農民の意思は、強大な権力の前に空しく潰えたのであるが、事件後、彼らの窮状は、さらに苛烈をきわめ、農民たちの頭上に重くのしかかってきていたのである。
それでもなお、蜂起に参加した秩父の農民たちは、幾重にも連なる山々の峰を日々見つめながら生活するしか手だてはなかったのである。そこで生をうけ、育った者にとって、秩父は決して捨て去ることのできない場所であった。










