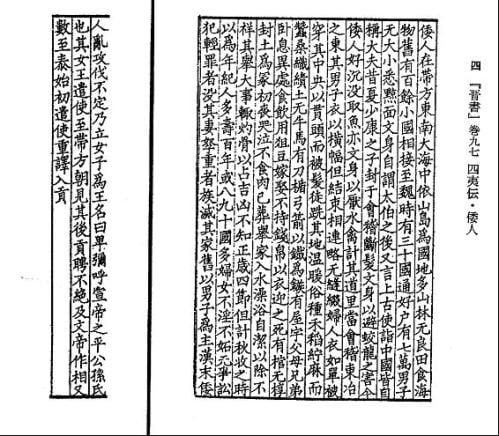呉国の縁地名として、「呉(くれ)」や「越前・越中・越後」が知られています。
「呉国」からの渡来人によって、「呉服」と漢字の読み方「呉音」が伝来しました。
古代日本国の基礎作りに貢献した文化人や技術者集団が呉国からの渡来人です。
『邑久町史』に近くの「山田庄の栗田は呉人にゆかりのある地名かも。」とあります。
『改訂邑久郡史上巻』に『播磨風土記』によれば、「呉人は応仁天皇の御世より帰化土着したるが如し」とあり、『改修 赤磐郡誌全』の漢・呉人に、「日本書紀 雄略天皇十四年の記録に、高月村大字牟佐(むさ・身狭村主は呉の帰化族)」とあります。
呉国よりの渡来人地名を高句麗の渡来人地名とする説があります。
呉を呉国ではなく句麗(クレ)とする説です。
高句麗は呉国からの渡来ルートの通過点です。
「呉国」からの渡来人によって、「呉服」と漢字の読み方「呉音」が伝来しました。
古代日本国の基礎作りに貢献した文化人や技術者集団が呉国からの渡来人です。
『邑久町史』に近くの「山田庄の栗田は呉人にゆかりのある地名かも。」とあります。
『改訂邑久郡史上巻』に『播磨風土記』によれば、「呉人は応仁天皇の御世より帰化土着したるが如し」とあり、『改修 赤磐郡誌全』の漢・呉人に、「日本書紀 雄略天皇十四年の記録に、高月村大字牟佐(むさ・身狭村主は呉の帰化族)」とあります。
呉国よりの渡来人地名を高句麗の渡来人地名とする説があります。
呉を呉国ではなく句麗(クレ)とする説です。
高句麗は呉国からの渡来ルートの通過点です。