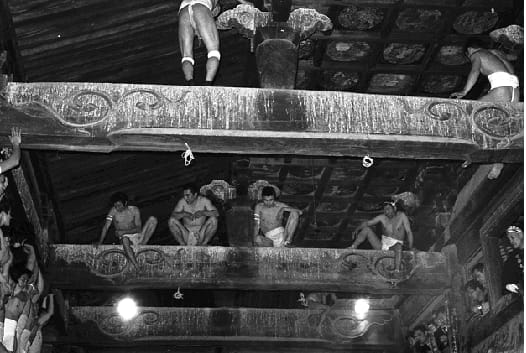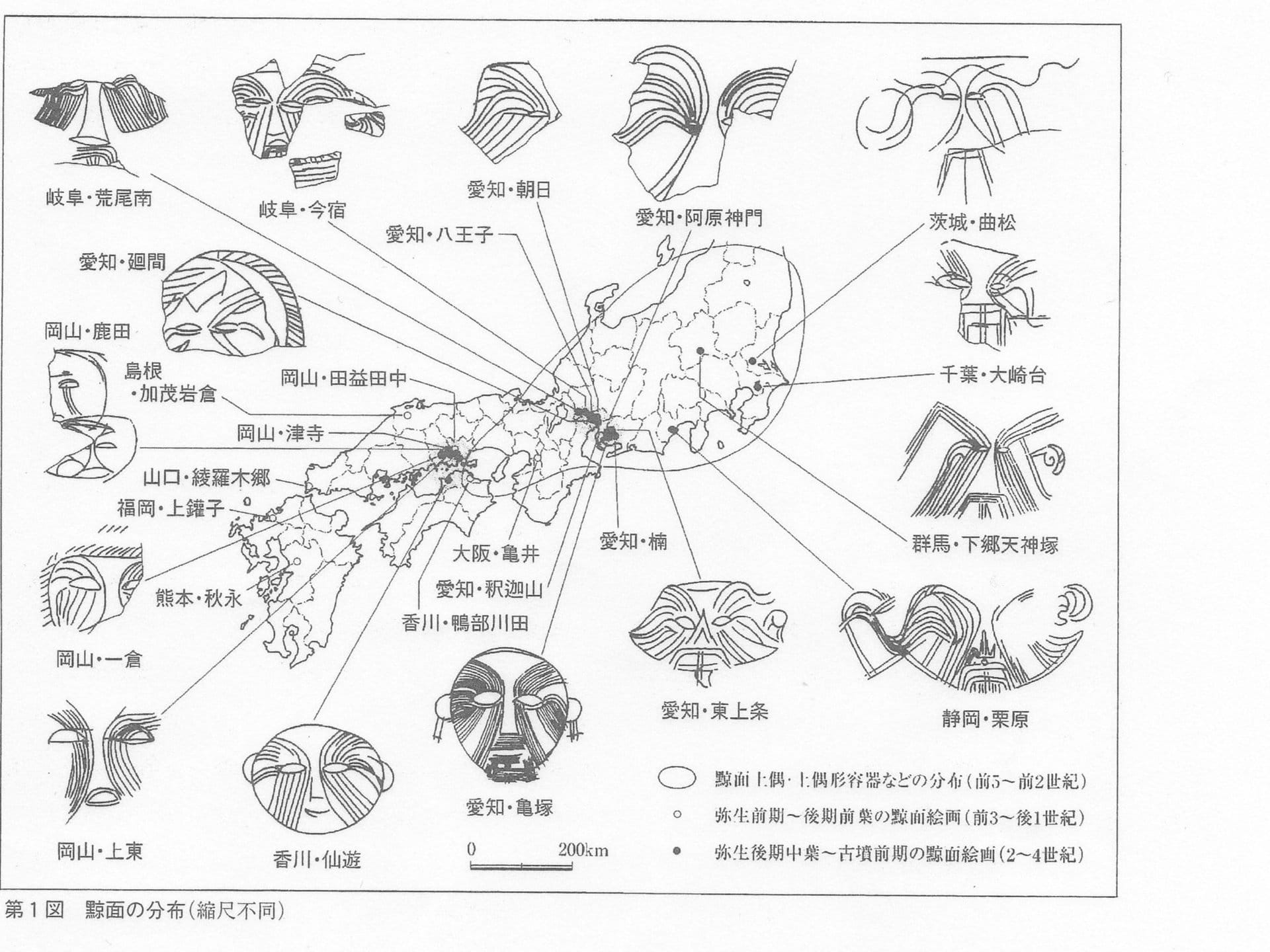林羅山(1583年~1657年)は徳川家康の信任を得て幕府文教政策の基礎を築きました。
江戸時代の朱子学者・林羅山の『本朝通鑑』に中巖圓月説を支持した「太伯皇祖説」があります。
「神武天皇論」で下記のように述べています。
『神武天皇論』に「余霜かに圓月が意を惟ふに、按ずるに諸書は日本を以て呉の太伯の後と為す。夫れ太伯は荊蟹に逃れ、髪を断ち身を文きて交龍と共に居る。其の子孫筑紫に来る。想ふに必ずせ時の人以て神と為ん。」
「渡来した賢人太伯の子孫が当時の人々に神として崇められたのであり、日本の皇室の祖神が、その本源を遡って見れば太伯に当たる」という。
「東山の僧・圓月、かつて日本紀を修す。朝儀協(かなわ)ずして果たされず。遂に其の書を焼く。余、ひそかに圓月が意(こころ)をおもうに、按(あん)ずる諸書、日本を以て呉の太伯の後と為す。
それ、太伯荊蛮に逃れ、断髪・文身し、交龍と共に居る。その子孫、筑紫に来る。思うに必ず時の人、以て神と為さん。
これ天孫、日向高千穂の峰に降るの謂か。当時の国人、疑いてこれを拒(ふせ)ぐの或いは、これ有るが、これ大己貴神、順(まつろ)い服せざるの謂か」

江戸時代の朱子学者・林羅山の『本朝通鑑』に中巖圓月説を支持した「太伯皇祖説」があります。
「神武天皇論」で下記のように述べています。
『神武天皇論』に「余霜かに圓月が意を惟ふに、按ずるに諸書は日本を以て呉の太伯の後と為す。夫れ太伯は荊蟹に逃れ、髪を断ち身を文きて交龍と共に居る。其の子孫筑紫に来る。想ふに必ずせ時の人以て神と為ん。」
「渡来した賢人太伯の子孫が当時の人々に神として崇められたのであり、日本の皇室の祖神が、その本源を遡って見れば太伯に当たる」という。
「東山の僧・圓月、かつて日本紀を修す。朝儀協(かなわ)ずして果たされず。遂に其の書を焼く。余、ひそかに圓月が意(こころ)をおもうに、按(あん)ずる諸書、日本を以て呉の太伯の後と為す。
それ、太伯荊蛮に逃れ、断髪・文身し、交龍と共に居る。その子孫、筑紫に来る。思うに必ず時の人、以て神と為さん。
これ天孫、日向高千穂の峰に降るの謂か。当時の国人、疑いてこれを拒(ふせ)ぐの或いは、これ有るが、これ大己貴神、順(まつろ)い服せざるの謂か」