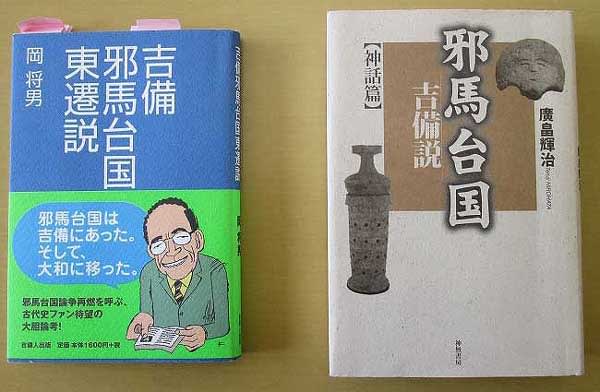昨日まで「おおく」と読み、今日から「、」を付けたので「たいはく」はありえません。
「大」の漢音は「タイ」、呉音は「ダイ」です。
最初は呉音で太伯と書き、漢音の時代に「、」の無い大伯(タイハク)と表記が変更されました。
古代から地名は「たいはく」でした。歴史学の初歩です。
参考文献も全て間違えています。
『角川日本地名大辞典』には「明治22年から昭和28年の邑久郡の自治体名・・・大伯が太伯と書かれたものと思われる」とある。
『岡山市の地名』には「明治22年(1889)合併し太伯村となり」とある。
これらの著者は調査しないで、文献をコピーして紹介しているだけです。
岡山県の郷土史家には、「郷土史研究とはコピーする事」と理解している人が多いように感じます。
「大」の漢音は「タイ」、呉音は「ダイ」です。
最初は呉音で太伯と書き、漢音の時代に「、」の無い大伯(タイハク)と表記が変更されました。
古代から地名は「たいはく」でした。歴史学の初歩です。
参考文献も全て間違えています。
『角川日本地名大辞典』には「明治22年から昭和28年の邑久郡の自治体名・・・大伯が太伯と書かれたものと思われる」とある。
『岡山市の地名』には「明治22年(1889)合併し太伯村となり」とある。
これらの著者は調査しないで、文献をコピーして紹介しているだけです。
岡山県の郷土史家には、「郷土史研究とはコピーする事」と理解している人が多いように感じます。