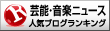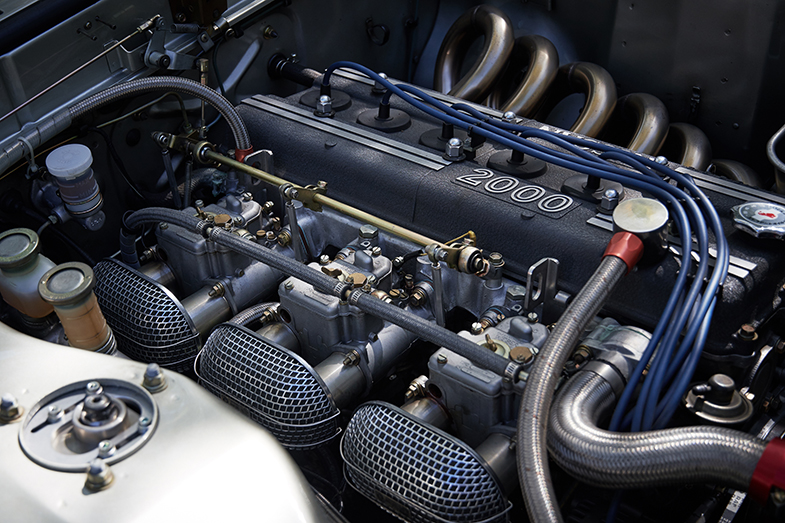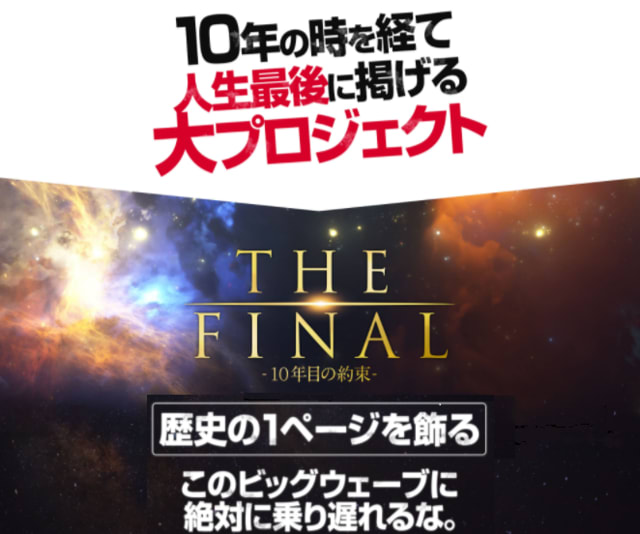「2017国際ロボット展」で見た、VRが進化させるロボット技術の未来
2017年11月29日から12月2日の4日間にかけて、東京ビッグサイトにて「2017国際ロボット展」が開催されました。

「国際ロボット展」は2年に一度開催されている、世界最大規模のロボットトレードショーです。会場では産業用ロボットを中心に、災害対応や介護の現場で活躍するサービスロボットなど、さまざまな種類のロボットとその関連技術についての展示が行われていました。
また会場では、ロボットの操作や産業用ロボットに動作を覚えさせる“教示”の際などに、VRを活用している事例を見ることができました。ここではそんなVRの観点から、会場の展示をいくつかピックアップしてご紹介します。
トヨタ自動車株式会社「T-HR3」
第3世代のTOYOTAヒューマノイドロボットである「T-HR3」は、マスター操縦システムによって人間型ロボットの全身を直感的に操ることができるという、世界初の操縦システムで動作するロボットです。

腕にマスターアーム、足にマスターフットを装着した操縦者が手足を動かすと、T-HR3もそれにシンクロして、まったく同じポーズを取ることができます。その光景は『Gガンダム』というか『パシフィック・リム』というか、まるでSF映画やアニメに登場する技術が現実になったかのような感動を覚えます。

またT-HR3は新開発のトルクサーボ技術を駆使することで、全身を協調させてバランスを維持したり、周囲との接触によって受ける力を柔らかく受け流したりすることも可能です。デモンストレーションのステージでは、片足で立つといったポーズを次々と披露しても、バランスを崩すことなく自立していました。

T-HR3の操縦者はVRヘッドセットのHTC Viveを装着しており、そこにはロボットの視線から見た立体映像が映し出されます。そのため、まるでロボットが操縦者の分身になったかのような感覚で、手足を動かすのはもとより、物をつかんで運ぶといった細かい作業を、直感的に行うことができるのです。


このようにリアルな遠隔操作技術とバランス制御技術、そしてVRが融合したT-HR3のインパクトは絶大で、デモンストレーションが行われるたびに多くの見学者が集まっていました。今回の「2017国際ロボット展」の中でも、ひときわ目立っていたロボットだったと言えるでしょう。
株式会社デンソーウェーブ「マルチモーダルAIロボット」
株式会社デンソーウェーブ、ベッコフオートメーション株式会社、株式会社エクサウィザーズの3社が開発した「マルチモーダルAIロボット」は、多指ハンドを装着した双腕型ロボットアームです。
このロボットアームは従来のロボットシステムでは難しかった、柔らかい不定形物を扱う複数の作業を実行することができます。「2017国際ロボット展」の会場では布製のタオルを畳んだり、野菜をつかんでサラダボウルに盛り付けるといったデモンストレーションが行われていました。

こうした作業をロボットに実行させるためには、これまで莫大な量のプログラミングを必要としていたそうです。しかしこの「マルチモーダルAIロボット」では、ディープラーニングとVR技術の組み合わせによって、ユーザーによるプログラミングなしに実行させることができます。
HTC Viveを装着したオペレーターは、ロボットに取り付けられた全天球カメラの映像を見ながら、リアルタイムに操作することができます。その状態でハンドセンサーを装着した腕を動かして、タオルを畳んだりサラダをつかんだりする動作を行うと、ロボットはその軌道とロボットアームやハンドから得られるセンサー情報を“学習”して、作業を覚えることができるのです。従来であれば複雑なプログラミングが必要だった動作を直感的に実行させるために、VR技術が活用されているわけです。

会場では、マルチモーダルAIロボットにサラダをつかむ動作を学習させる様子を見ることができました。ここではオペレーターの腕の動きと、ロボットの腕の動きがシンクロしています。
こうして作業を学習したロボットは、手順を自分自身で“考えながら”作業を行うようになり、たとえば畳んでいる途中のタオルを渡しても、そのことをちゃんと理解して作業を完遂できるとのこと。

写真のモニターの左側に表示された全天球カメラの映像では、ロボットが映像を通じて野菜の種類を認識していることがわかります。また右側の画面では、ロボットが次に行う手順を考えている様子が表示されています。
このように、マルチモーダルAIロボットのデモンストレーションは、ロボットだけでなくVRやAIなどの最新技術が集約された、密度の濃い内容となっていました。
ABB株式会社「RobotStudio+VR」
産業用ロボットの世界では、実際の製造ラインにロボットが導入された際の動作や工程時間を確認するため、事前にシミュレーションを行うことが重要なのだそうです。そこで、仮想空間にロボットシステムを配置して、実際と同じように動作させるシミュレーションソフトが用意されています。
しかし、ロボットの周囲に安全柵を配置する位置は適切なのか、オペレーターが快適に作業できるスペースが確保されているかなど、リアルスケールで現場を歩き回ってみて初めて確認できることも多いとのこと。そのために1部屋まるごと、場合によっては工場まるごとという規模で、実際にロボットを配置して検証することも行われているそうです。
産業用ロボットメーカーの大手企業であるABBでは、同社のソフトウェアであるRobotStudioにVRを組み合わせることで、ロボットが配置されたシミュレーション空間をリアルスケールで歩き回り、あたかも現場にいるかのような視点で確認することを可能にしています。「2017国際ロボット展」のABBブースでは、Oculus RiftとOculus Touchコントローラを使用したデモンストレーションが行われていました。

ロボットが配置されたシミュレーション空間には、HMDを装着した複数のユーザーがアクセスできるため、海外などの遠隔地にいる人とロボットを見ながら改善点などを話し合える、バーチャル・ミーティングが可能です。そのために、空間内の特定箇所を線で囲んで他のユーザーと共有したり、空間内に付箋を貼って改善点をメモしたりするといった機能も用意されているそうです。


写真のように、ロボットの動作や空間に対する操作は、ユーザーの手元に設定された仮想コントローラーで実行できます。
ABBの方にお話を伺ったところ、VRをどう活用するかというよりは、ロボットを導入するお客様に対してどのような提案ができるかということを考えて、このシステムを開発したとのこと。とはいえ、仮想空間をリアルスケールで体感できるというVRならではのメリットを、産業の現場で実用化している例として、非常に興味深い展示となっていました。
山梨大学工学部機械工学科 野田研究室「VRクレーン操作トレーニングシステム」
工場などで重い荷物を天井からロープで吊り下げて運ぶクレーンは、荷物が大きく揺れると危険が伴うこともあり、操作技術が求められます。5トン以上の荷物を運ぶ際にはクレーン運転士の免許資格が必要となるほか、それ以下の重さの荷物を運ぶ場合にも技能講習や特別教育を受ける必要があります。
そうしたクレーン操作をVRで学習できるのが、このシステムです。こちらはロボットと直接関係はありませんが、関連技術として会場に展示されていたものです。

こちらのシミュレーションでは、ユーザーの入力に応じて天井のクレーンが動作し、その動作に応じて荷物の揺れが再現されます。VRでのシミュレーションということで、実際に数トンもの重さの荷物を動かすこともなく、安全にクレーン操作が体感できます。現実には危険が伴うような操作をあえて行うことで、その危険性を実際に体感できるのも、VRならではのメリットだとのことでした。
こちらは大学での研究ということで、操作にはスーパーファミコンのコントローラーが使用されていましたが、現実のクレーンは「ペンダントスイッチ」と呼ばれる押しボタン式のコントローラーを使用しているため、機能自体は同一とのことでした。クレーン技能の教習所でも、このシミュレーションは好評だったそうですが、建物のスケール感やロープの太さなど、もう少し精度を上げたいとのこと。また、人によってはVR酔いに悩まされるという課題もあるそうです。
いずれにしても、こうした分野でもVRの活用が研究されているというのは、今後VRがどのように広がっていくかを考える上でも楽しみです。

最初に紹介したように、「2017国際ロボット展」はあくまでロボット技術のトレードショーであり、決してVRがメインのイベントではありません。しかし、その中でVRが有効に活用されている事例をこれだけ見ることができたのは、産業の現場でVRが着実にその可能性を広げている証だと言えるでしょう。その意味でも非常に意義深いイベントとなっていました。
X href="https://natalie.mu/music/gallery/news/237483/725123">
立ったまま会見に臨むYOSHIKI。
YOSHIKI