視覚的記憶について、いつだか書いたことがあるが、今日のNHKのBS放送「フロンティア」で「やっぱり」と言えることがあった。
ほんの短い時間の視聴で、言葉が使えない女の子の描いた絵が「素晴らしく正確なデッサン」になっていて、まさに天才的と驚かされた内容。私がかねてより、個人的な意見として「視覚的記憶力」を鍛えることが大事だと言ってきたが、女の子のそれは「写真機で撮影された画像を再現する能力とは異なる創造性を加味したデッサン力」なのだ。医師が「言葉が使えない人の視覚的記憶力は衰えない・・・・と、認知症の老人の言葉が口に出てこなくても、視覚的記憶力はお衰えていない」という。原始時代の壁画の例を挙げて、言葉がなくても視覚的な表現で、獲物である「鹿などの動物」を洞窟の壁に僅かな松明の光で再現描写していて、その肉薄した表現力のすばらしさは美術史の中でも特筆されてきた。
以前、同じくNHKの番組で「言葉の始まり」を語るテーマで、大学で言語学を研究する教授がアルタミラやラスコーの壁画を見ても「言葉が先に出来て、絵が描かれた」という、今回の番組で証明される「言語がなくても視覚的記憶力が働いている」という証明を「真逆」に捉えた意見を言っていたのを、私は「こいつアホウだ!!」と書いた記憶がある。言語学者を名乗ると「自尊心」から、根拠のない嘘が出たのだろう。
絵を描いていると「小学生の描写力」について驚嘆してきた経験を話した。図工の時間に先生から「今回は交通安全のポスターを描いてみよう」と言われて描いた小学生のポスターが「横断歩道前に自分が乗った自転車が止まるところを描いた少年のリアルな自転車と自分の顔」の表現力に驚いて・・・・どうして、小学生はこんな絵が描けるのだろうか?」と不思議に思った。この能力は年を取ると失われて行く。
これは「描写の才能が特別身についている」ということではなく、年を得ると失われて、同じようには描けなくなることは、人の人生においてごく自然なあり様なのだから。つまり教育機関で「言葉を使って表現する」ことを常態化すると、視覚的記憶より言語中枢がより多く働いてしまうということだろう。また「絵」にすることも生活からなくなる。
一つの例として思うことは、美術史を研究している人たちが「視覚的記憶力」があるかどうかと言えば、正直言って彼らには「無い」というべきだろう。なぜなら美術館に居て、自分の部屋で「他人が書いた資料、文献を読んでいるだけだから・・・」で、展示室の美術作品を観察しにいかないのである。例えば西洋美術館の学芸員に「所蔵品のモネのこれこれの図版を略式で良いので描いてみて」と言えば、誰も無能であろう。言語が先で視覚的記憶は不得手なのだ。問題は彼らが評論原稿を頼まれると「印刷物」を見て済ますことだ。
彼らが購入作品で「偽物」を買ってしまうのが残念だ。彼らが視覚的記憶力を持ち合わせていない証拠だが、その恥ずかしさも感じないのは、日常的に「物を作る、物を見る、そして理解する」訓練がされていないから。絵画や彫刻の作者である偉大な芸術家の制作意図を理解する感性や能力が求められるのに、本来研究者として理解、認識が不十分だと気が付かないのだ。自ら作る現場を持たないのは、美術史の仕事の範疇には「言葉」しかないからだろう。
どうだろうか、言葉で絵画を説明は出来ないが、彼らの言葉を聞いて、美術作品との関係が十分に得られると思うのは、彼らの仕事が「言葉での解説」だからだろう。19世紀初頭のサロンの評論家たちの言葉は「ゴマすりや売り込み」のようであったかもしれないが、ボードレールやワイルドの作品に対する評論の挑発は、もはや「言葉の暴走」だった。これが「近現代アート」の始まりで、作者の視覚的表現から、見る側の言葉が重視されて、そこに後続の作家たちが巻き込まれて観念アートになってしまう。
こうして「言葉の世界」で支配される時代には金や政治力を使う権力者には楽しい世の中なのかもしれない。トランプがいい例だろう。彼は視覚的記憶がないことが「混乱」を招くのだ。
言葉は人間にとって「知性を発達させた原動力」であったが、言葉だけで「身の回りの理解」が十分でないことは皆分かるだろう。
貴方も「視覚的記憶力」を養ってみたら如何か!!
それには「絵を描くこと」がまず一番手っ取り早い手段だ。今。私は水産高校で非常勤教師をやているが、高校生になったばかりの一年生に「意図的に絵を描くこと」で「視覚的記憶力」を確認させている。10分見て、1分で描くように指導しているが、彼らは耳を持たないから、よく見ないで思い付きで描き始めて、小学生だったころの才能は失せた図柄になる。まず「よく見て正確に描こう」と言っても、この「正確」が分からないから、横で「ここをよく見て、こうしなさい」と言い続けて・・・・。最終的に「ぼろくそにけなすか、褒めるか」である。人間褒められると「気持ちが良くなる」らしく、描く絵も良くなっていく。この満足感は「原始的」で、脳に刺激が与えられる。目の前にある「物」が目から脳を通して、スケッチブックの紙の上に展開していくことが「視覚的記憶力」であるから、これを繰り返す。こうして「言葉で表現できないことを画像に出来るようになる」のだ。絵は言葉以上に饒舌となる。
視覚的記憶は「白い紙と鉛筆」で、紙の上に新たな世界を作り出すことが出来るようになる。それが「無いものを在るがごとき」にする「芸術」の始まりなのだ。観念アートのような「言葉」のこじつけで始まらない創造なのだ。
私が山口に引っ越せたら、新しいアトリエに絵画教室を始めて、「貴方の心を描いてみませんか」と問いかけるつもりだ。もしそれが具体的に効果を生んだら、そこが私の死に場所になるだろう。
















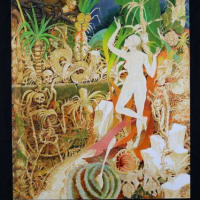


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます