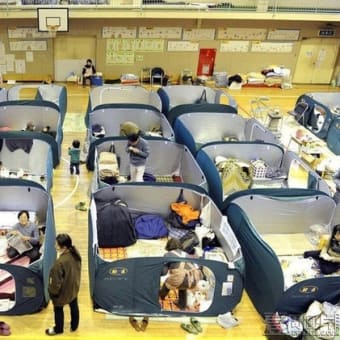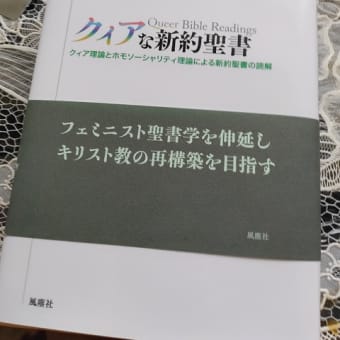電車に乗っていたら、若いお母さんがスマホをずっといじっていた。傍にはベビーカーに赤ちゃんである。僕が見てもわかったが、その赤ちゃんはぐずっていた。でも、そのお母さんは気にもとめず、スマホに心を奪われていた。
お母さんと子供の間に心的絆が形成されるのだろうか。心的絆をラポールという。
そこで思い出したのが、一昔前病院で見た風景である。よくあることであったので、一例を取り出してみる。子供がタンスの角に頭をぶつけたので、救急受診に来た。その子供は元気そのものだ。ただ心配だからということで、病院に来たのである。
診察して数分後、何事もなかったかのように、帰って行った。もちろん、子供に問題はないと医者が診断したのである。それで、かのお母さん、ほっと胸をなで下ろし、心配が解消されたということである。誰のための診察なのでしょう?
医者の診断は客観的なのだろう。では子供とお母さんは一心同体のような関係であるから、この二人の関係性からの“診断”は主観的ということになるだろう。しかし、一心同体ではなければ、子供とお母さんは異なる主観になるので、お母さんは子供がどういう状態か主観的に判断しようにも、判断するだけの知識や経験を持ち合わせなければ、判断することができない。そこで医者に診断(判断)してもらわないと、安心できないのだ。
子供とお母さんの関係が一心同体であるためには、いつも一緒にいて、お母さんが子供の反応や表情、状況をいつも観察し、その観察から意味を考え、そういうプロセスを子供の成長とともに実践しなければならない。
そうすることで、他人が気づかないであろう変化を、お母さんは見逃さなくなるはずだ。これは合理的とは言えないかもしれないが、人間の直観や暗黙知であるから、人間に備わった能力である。お母さんは子供との関係を構築するプロセスを通して、このような能力を自然と開発するのである。
そのような能力が欠けているから、自分の子供がたんすに頭を打って、だいじょうぶな状態なのかどうかを、自ら判断することができないのだ。
そして、ちょっとした医学情報なんかを知ると、自身の五感ではなく、その情報を演繹的に適応してしまい、ただ不安を高じらせることになる。情報や経験に裏打ちされていない知識は五感の邪魔になってしまうのである。このお母さん、真にお母さんだろうか。
そこで、冒頭の電車の中で僕が見た若いお母さん。スマホに気を取られて、子供を見ていないのだから、子供の母親になる気はないのかもしれないと思ったのだ。生物学的にはお母さんだが、この時心理的には他人である。
情報化社会とは、このような人間の能力が後退し、その代わりに効率的な情報で代替させる社会である。効率的になれば、効率的に目に見えて計算可能な世界だけが肥大化していく。前も書いたが、養老孟司が「人間がコンピュータに似る」というのは、こういう状況のことでもあるだろう。