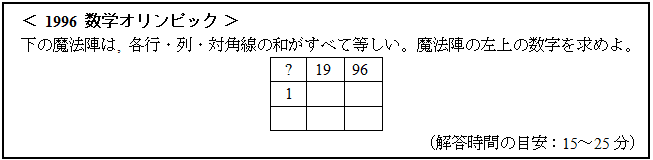思えば中学生の頃、私が数学を真剣に学び始めたのは
自分にコレといって得意なものが無いことに不安を感じたからでした。
皆が数学という学問の道に進むわけではないし、
数学は夢の実現のために必要なだけかもしれない。
もしかしたら、数学を好きにはなれなくても
今まで勉強してきた時間を無駄にしたくないから
数学を手放したくないだけかもしれない。
ただ1つ、ヘウレーカで学ぶ生徒全員の胸中に
「力をつけたい」という強い志があればよいのだと思います。
ブログはこれから小休止に入りますが、
その間もヘウレーカは、冬期講習に躍動しています。
たとえ学問の道へ進む気が無くても
たとえ将来の夢が今見つからなくても
たとえ一流大学に受かりたいだけであっても
たとえ数学が苦手であっても
たとえ文系の生徒であっても
たとえ進学校に通っていなくても
たとえ浪人生であっても
大切にしてほしいのは「数学に対する成長意欲」。
敷居の高い大学に進学するために
敷居の高い塾に足を踏み入れる覚悟をもった中高生に
「成長」という刺激をたくさん与えられればと思っています。
(数学好きの方ももちろん大歓迎です。)
……そろそろブログは第一幕を下ろします。
次回は年明けの更新になりますが、
読者の方も、よいお年をお過ごしください。
それでは、失礼いたします。
=============
数学専門塾ヘウレーカ
=============
自分にコレといって得意なものが無いことに不安を感じたからでした。
皆が数学という学問の道に進むわけではないし、
数学は夢の実現のために必要なだけかもしれない。
もしかしたら、数学を好きにはなれなくても
今まで勉強してきた時間を無駄にしたくないから
数学を手放したくないだけかもしれない。
ただ1つ、ヘウレーカで学ぶ生徒全員の胸中に
「力をつけたい」という強い志があればよいのだと思います。
ブログはこれから小休止に入りますが、
その間もヘウレーカは、冬期講習に躍動しています。
たとえ学問の道へ進む気が無くても
たとえ将来の夢が今見つからなくても
たとえ一流大学に受かりたいだけであっても
たとえ数学が苦手であっても
たとえ文系の生徒であっても
たとえ進学校に通っていなくても
たとえ浪人生であっても
大切にしてほしいのは「数学に対する成長意欲」。
敷居の高い大学に進学するために
敷居の高い塾に足を踏み入れる覚悟をもった中高生に
「成長」という刺激をたくさん与えられればと思っています。
(数学好きの方ももちろん大歓迎です。)
……そろそろブログは第一幕を下ろします。
次回は年明けの更新になりますが、
読者の方も、よいお年をお過ごしください。
それでは、失礼いたします。
=============
数学専門塾ヘウレーカ
=============