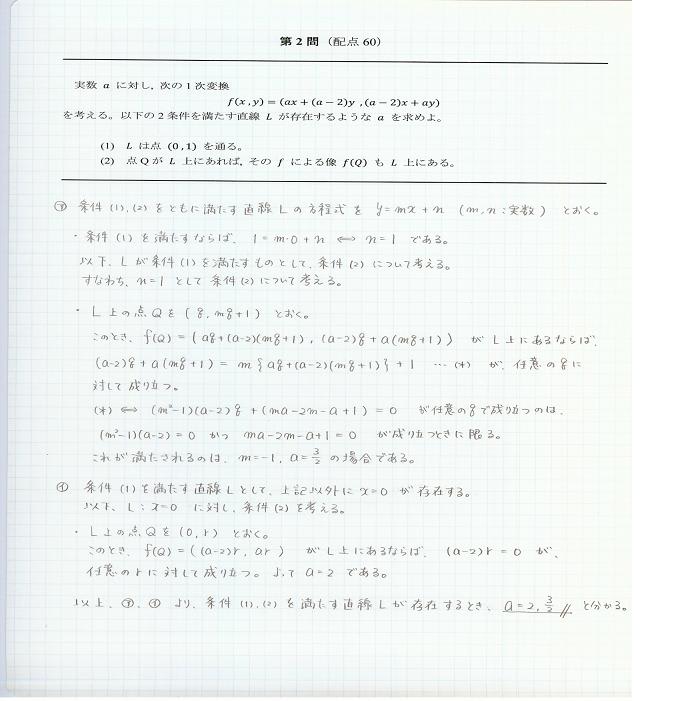最後に第4問。
回転軸に対して斜めに置かれた平面図形を回転させてできる回転体の体積を求める問題。


(1)は簡単ですが、(2)は今年唯一の、例年の東工大レベルです。
東大に関しても強く言えることですが、国公立2次で出題される立体は、形をイメージできないことがほとんど。
今回だって、おちょこのような形をした図形を回転軸に対して傾けながら回転させているのですから、出来上がりの形なんか想像できませんよね。
積分のもとでは、形を無理やりに想像する必要などありません。むしろ想像してはいけません。
「回転させる前の段階で切ってしまって、その切り口を回して断面を特定し、断面積を求め、積分」という流れです。
一言で表現するならば「切ってから回せ!」です。
これから本格的に入試対策に突入するなら、
回転体・非回転体は重大なテーマになりますから、数ヵ月後に備え、
「切ってから回せ!」というフレーズをお忘れなく。
さて、全体のまとめといきましょう。
難易度は、驚異的に易化しました。
私自身、見た瞬間に、すべての問題で解答への筋道が見切れたのは、東工大では久しぶりのことです。
最低3完近くはとれていないと、合格は厳しいかもしれません。
本来の東工大は、
・微積を主体とした計算がヘビー級の問題
・答えは視覚的にはすぐに見つかるが正確な論証の難しい問題
の少なくとも1つは毎年出題してきます。
今年の難易度が来年も続くとは思わず、
例年通りの重厚な問題を攻略する方針で学習したほうが良いでしょう。