①【私の注目点】
06 企画は未完成のまま「すぐ」に周囲に投げかける
「今やる人」は、完成するまで1人で抱えるなどということをまったく考えません。ある程度てきたらすぐに、上司や周囲に投げかけてしまいます。
「今やる人」は、すぐやるからこそ、その際の1人でできることの限界をよく知っています。しかし、自分1人ではできなくても、ほかの人やものの力を借りれば、当然できることの量や範囲が広がります。そのために、普段から周囲が自分に協力してくれる体制を作ることに、力を入れているのです。
僕自身の予備校講師という職業においては、この「取り返しのつかなさ」はかなり鮮明です。稚拙な説明をしてしまった、あるいは、時間配分を誤って説明が不十分だった箇所を見直して、次回から改善することはできます。しかし、最初の授業を聞いた生徒の聞いてしまった説明は、二度と消えない、そう、取り返しがつかないのです。
結局、少し酷な言い方になりますが、取り返すということは、まずできない、すべては「取り返しのつかない」という意識を持つことが大切なのです。
さらに、この取り返す、チャラになったという考え方には、二つの問題点があるのです。
一つは、取り返したんだからいいさ、と思うことで、最初の失敗の反省、原因究明がおろそかになるのではないか、ということです。失敗したからには何か原因があるはずです。その原因(たとえば、交渉のときの態度や情報収集不足)を究明して、改善を測らない限り、また同じ失敗を繰り返す可能性があります。にもかかわらず、次のチャンスでうまくいったことで、それを放置してしまうのは、自分で自分の成長を止めるようなこと。ならば「取り返しはつかない」と強く認識しておいたほうがよい、僕はそう考えています。
もう一つは、失敗という負の経験も、立派な財産だということです。
過去の失敗をほかの成功で消してしまうのではなく、成功経験と同様に、堂々と背負って生きていけばよいのではありませんか。僕は確かに、こういうミスをしてきた人間だ、しかし、今もこうやってしっかりチャレンジできている、と胸を張ればいいんです。
そして、失敗という、負の財産の管理のためには、自分の犯した失敗は、できればすぐに記録しておいたほうがいいんです。記憶が「今色」に染まる前の、その瞬間の印象が鮮明なときにしっかり記録して、その後背負っていけるよう、管理すべきなのです。
「普通の」人間は時間を管理することで、集中力を高めることができるのです。時間に追われるから、時間の制約を意識するから、だから、集中できる、それが凡人の普通のあり方ではないでしょうか?
記録するということは、自分に向き合うことにほかならないのです。だから、問題が明らかになってその改善も可能となるのです。
あなたも自分の「記録魔」になって、自分と向き合い、より素晴らしい自分をプロデュースしていってください。
「努力は裏切らない」という言葉があります。この言葉そのものは間違っていませんが、実は、少し補足が必要な言葉なのです。どう補えばよいかと言えば、「正しい方向でなされた努力は裏切らない」とすべきなのです。努力は、単に量だけでなく、方向性をもっているのです。ベクトル量なのです。
結果を出す人は違います。まず方向を先に確かめ、これでいいと思ったらすぐ実行に移し、必要な量に達するまで努力を続けるというパターンを取ることが多いのです。
こういう人は、この方向でいいかどうかという判断に迷いが生じた際には、ためらうことなくアドバイスを求めることができるのも特徴です。
逆に、先に書いたような不満をぶちまける人は、人のアドバイスをちゃんと聞かず、結局は自分の判断基準を押し通して、間違った方向での努力を続ける、当然の結果として上手くいかず、不満を抱く、これは悪循環以外の何ものでもありません。
本当に実現を願う夢や希望は、どんなに不可能に思われても、まずは記録すべきです。将来実現したい「コト」を、「コトバ」で表すことによって、まず自分に突きつけてみるのです。それが実現への第一歩です。
さらには、思い切って周囲の人に語ってみるのです。他人を利用して、自分にプレッシャーをかけて実現を促すことができるということです。
もう一つは、あなたの夢や希望を聞いた他人が、その実現の「架け橋」になってくれる場合もあるということです。
僕の知っている「できる人」はただ一人の例外もなく、お土産で人を喜ばせるのがうまい、つまり、お土産上手です。彼らは、相手の好みや趣味をさりげなく事前に調査して、生ものでない限りは、必ず前日には用意しておきます。多少、不便な場所にあっても、いや、不便な場所にあるからこそ、わざわざ買いに行きます。
なぜ、そんな面倒なことをするのか?それは先にも書いたように、お土産はモノを贈るのではなく、心を贈り、心遣いを伝えるものだと心得ているからです。
人は理屈だけで生きてはいません。嬉しい気分になると、ついそういう気持ちにしてくれた相手に対して好意的に動いてしまうものです。
世の中のヒット商品と言われるものの多くが、愚痴や不満をもとに世に現われたものです。例えば四色ボールペン。このように愚痴や不満は、物や環境の改変を促す重要な力となりうるものなのです。
歴史を学ぶ意義は、大きく分けて二つあると思います。一つは、自分なりの歴史観を作り上げること。これはなかなか難しいことでありますが、現実にどんなことが起きていて、どういうつながり(=因果関係)のなかで、どう変化していくのか、そういったことを落ち着いて自分なりに捉える眼を養うのに役立ちます。学校で無理やり暗記させられた、あの歴史がなんの役に立つんだ、もうごめんだと毛嫌いするのではなく、今の変化を捉えるための「鑑」=お手本として、もっともっと親しむべきだと思います。
もう一つは、歴史には敗者の姿が露わになっているという事実に基づきます。
敗因には勝因以上に普遍性があるのです。
圧倒的な第一位は、情報不足ではないかと思っています。
ほかにも決断力や行動力の欠如、慢心など、われわれが反面教師とすべき、多数の敗者の無残な姿が、歴史のなかにさらされているのです。「負けの法則」を読み取って、自らの成長に役立てるようにしましょう。
歴史は、実際に生きた人の姿の記録です。虚構のゲームの世界に存在しえない緊張感に満ちています。それに触れて、自らの生を引き締めてほしい、そんなことも思うのです。
文字だけの情報を一次元、パワーポイントなどを用いて図示した情報を二次元、さらに動画を用いて、リアルな動きを作った情報を三次元と考えて、それを場合に応じて適切に使い分けて行くべきだということなのです。
この三者の関係を考えると、まず、次元が上がるほど作成に手間がかかるという比例関係があります。そして、同じく上がるほど、わかりやすさ、インパクトは増していくという比例関係もあります。
最近の若い人のなかには、そんなに大した書類でもないのに、パワーポイントを駆使して、ずいぶん立派なものを作り上げる人がいます。そういう人は、どういう伝え方がベストなのかを考えずに、どんな情報も、いつも同じ方法で、つまりは同じ次元で伝えようとするのです。そのせいで時間がかかりすぎてほかの仕事を圧迫したり、さらには残業せねばならないような状況に陥ったりするようでは本末転倒です。
上方には、それを伝えるにあたって、ふさわしい次元が明確に存在するのです。だからその次元を見極めて情報伝達の方法を考えるべきなのです。
どのようにして使い分けていけばよいのでしょうか?使い分けのポイントは主に二つです。
まず、伝える情報量とわかりやすさの問題です。
文字情報にグラフや図、写真といった多彩色の視覚的な情報に加えて、「わかりやすい」情報に変換することが必要となるのです。場合によっては、動画を用いて説得力を増すことも必要なのです。
次に、情報の使い分けに際してもう一つのポイントがあります。それは情報を贈る相手が、どういう情報を発信する人物であるか、ということです。
人は、自分の発信するかたちの情報に慣れているだけでなく、それが適切な伝達方法であると、無意識に思い込んでいるものです。さらに言えば、自分の情報の次元よりも低い次元の情報を「わかりにくい」と判断しがちなのです。
「できる」人は、いつも自分を批判する自分を頭の中に住まわせていますから、絶えずその自分にチェックさせて、決して独りよがりにならないものです。そういう人は、普段から自分で自分を批判していることになるので、他者からの批判にも強いですね。
やってはいけないこととわかっていても、人はつい、好き嫌いで選んでしまうものなのです。それだけでなく、嫌いなものをダメなもの、悪いものとみなして自分を説得することに関しては、かなり高い能力をもっています。
残念なことですが、人には好き嫌いの感情を、しばしば善悪の判断とすり替えてしまうクセがあるのです。
座標軸を用意するのです。
②【感想など】
・過去の失敗経験をも、その記憶が鮮明なうちに、こと細かに記録し、自分と向きあい、背負って次に活かして行こうとする姿勢は立派過ぎる。(普通の人はそこまで自分に厳しくしない)
少しでも行動等を記録をすること、それを見返すことで、かなりの自己改善が期待できそうだ。
・努力は、やみくもに何時間もするのではなく、正しい方向性とは何かを常に考え、見極め、行っていくことが大事というのは頷ける。
まずは、方向性(計画)を定め、実行し、その結果を分析の上、修正して次の方向性(計画)に反映させていく。このサイクル(PCDA)が必須ということか。
・判断や対応においては、どんなに理性的に行おうと心掛けていても、つい、好き嫌いの感情に引っ張られがちとなるのは気をつけたいものだ。
③【今後、考えてみようと思うこと、実行してみようと思うこと】
・各種勉強において、簡便で無理なく、方向性(計画)の決定、手帳での各種記録の様式、勉強実行の分析・評価と、その方向性(計画)へのフィードバックする手法
・感情的な判断に陥ることを防ぐ方法の考察
【この本のAmazonへのリンク】
≪他のページ≫
★美術展・街歩きのページ
★私のTwitter
★私の読書メーター(全記録)
★読書日記(受験本)
・現代文勉強法の考察~各問題集を巡って~【田村のやさしく語る現代文】編
・現代文勉強法の考察~各問題集を巡って~【現代文のトレーニング入門編】編
・【現代文の勉強法01】要約力、文章構造分析力、アイデア創造の発問力の強化-日本語能力試験N2編(1) 問題10(1)
・【大学への数学1対1対応の演習】の使い方・勉強法-直観力鍛錬と問題構造分析-数学Ⅰ数と式 例題8
・【能力開発】図形センスを磨き、難問を制覇する-高校への数学「レベルアップ演習」編§7合同&線分比・面積比-
・【システム英単語勉強法】600語を20日間で記憶するためにエクセルを活用した覚え方
・【英語多読】目指せ!大学受験の英文読解で100万語!
【駿台模試】受ける意味と対策勉強内容:関連ページ
・高1:第1回H25.6.9
・高2:第1回H26.6.8


06 企画は未完成のまま「すぐ」に周囲に投げかける
「今やる人」は、完成するまで1人で抱えるなどということをまったく考えません。ある程度てきたらすぐに、上司や周囲に投げかけてしまいます。
「今やる人」は、すぐやるからこそ、その際の1人でできることの限界をよく知っています。しかし、自分1人ではできなくても、ほかの人やものの力を借りれば、当然できることの量や範囲が広がります。そのために、普段から周囲が自分に協力してくれる体制を作ることに、力を入れているのです。
僕自身の予備校講師という職業においては、この「取り返しのつかなさ」はかなり鮮明です。稚拙な説明をしてしまった、あるいは、時間配分を誤って説明が不十分だった箇所を見直して、次回から改善することはできます。しかし、最初の授業を聞いた生徒の聞いてしまった説明は、二度と消えない、そう、取り返しがつかないのです。
結局、少し酷な言い方になりますが、取り返すということは、まずできない、すべては「取り返しのつかない」という意識を持つことが大切なのです。
さらに、この取り返す、チャラになったという考え方には、二つの問題点があるのです。
一つは、取り返したんだからいいさ、と思うことで、最初の失敗の反省、原因究明がおろそかになるのではないか、ということです。失敗したからには何か原因があるはずです。その原因(たとえば、交渉のときの態度や情報収集不足)を究明して、改善を測らない限り、また同じ失敗を繰り返す可能性があります。にもかかわらず、次のチャンスでうまくいったことで、それを放置してしまうのは、自分で自分の成長を止めるようなこと。ならば「取り返しはつかない」と強く認識しておいたほうがよい、僕はそう考えています。
もう一つは、失敗という負の経験も、立派な財産だということです。
過去の失敗をほかの成功で消してしまうのではなく、成功経験と同様に、堂々と背負って生きていけばよいのではありませんか。僕は確かに、こういうミスをしてきた人間だ、しかし、今もこうやってしっかりチャレンジできている、と胸を張ればいいんです。
そして、失敗という、負の財産の管理のためには、自分の犯した失敗は、できればすぐに記録しておいたほうがいいんです。記憶が「今色」に染まる前の、その瞬間の印象が鮮明なときにしっかり記録して、その後背負っていけるよう、管理すべきなのです。
「普通の」人間は時間を管理することで、集中力を高めることができるのです。時間に追われるから、時間の制約を意識するから、だから、集中できる、それが凡人の普通のあり方ではないでしょうか?
記録するということは、自分に向き合うことにほかならないのです。だから、問題が明らかになってその改善も可能となるのです。
あなたも自分の「記録魔」になって、自分と向き合い、より素晴らしい自分をプロデュースしていってください。
「努力は裏切らない」という言葉があります。この言葉そのものは間違っていませんが、実は、少し補足が必要な言葉なのです。どう補えばよいかと言えば、「正しい方向でなされた努力は裏切らない」とすべきなのです。努力は、単に量だけでなく、方向性をもっているのです。ベクトル量なのです。
結果を出す人は違います。まず方向を先に確かめ、これでいいと思ったらすぐ実行に移し、必要な量に達するまで努力を続けるというパターンを取ることが多いのです。
こういう人は、この方向でいいかどうかという判断に迷いが生じた際には、ためらうことなくアドバイスを求めることができるのも特徴です。
逆に、先に書いたような不満をぶちまける人は、人のアドバイスをちゃんと聞かず、結局は自分の判断基準を押し通して、間違った方向での努力を続ける、当然の結果として上手くいかず、不満を抱く、これは悪循環以外の何ものでもありません。
本当に実現を願う夢や希望は、どんなに不可能に思われても、まずは記録すべきです。将来実現したい「コト」を、「コトバ」で表すことによって、まず自分に突きつけてみるのです。それが実現への第一歩です。
さらには、思い切って周囲の人に語ってみるのです。他人を利用して、自分にプレッシャーをかけて実現を促すことができるということです。
もう一つは、あなたの夢や希望を聞いた他人が、その実現の「架け橋」になってくれる場合もあるということです。
僕の知っている「できる人」はただ一人の例外もなく、お土産で人を喜ばせるのがうまい、つまり、お土産上手です。彼らは、相手の好みや趣味をさりげなく事前に調査して、生ものでない限りは、必ず前日には用意しておきます。多少、不便な場所にあっても、いや、不便な場所にあるからこそ、わざわざ買いに行きます。
なぜ、そんな面倒なことをするのか?それは先にも書いたように、お土産はモノを贈るのではなく、心を贈り、心遣いを伝えるものだと心得ているからです。
人は理屈だけで生きてはいません。嬉しい気分になると、ついそういう気持ちにしてくれた相手に対して好意的に動いてしまうものです。
世の中のヒット商品と言われるものの多くが、愚痴や不満をもとに世に現われたものです。例えば四色ボールペン。このように愚痴や不満は、物や環境の改変を促す重要な力となりうるものなのです。
歴史を学ぶ意義は、大きく分けて二つあると思います。一つは、自分なりの歴史観を作り上げること。これはなかなか難しいことでありますが、現実にどんなことが起きていて、どういうつながり(=因果関係)のなかで、どう変化していくのか、そういったことを落ち着いて自分なりに捉える眼を養うのに役立ちます。学校で無理やり暗記させられた、あの歴史がなんの役に立つんだ、もうごめんだと毛嫌いするのではなく、今の変化を捉えるための「鑑」=お手本として、もっともっと親しむべきだと思います。
もう一つは、歴史には敗者の姿が露わになっているという事実に基づきます。
敗因には勝因以上に普遍性があるのです。
圧倒的な第一位は、情報不足ではないかと思っています。
ほかにも決断力や行動力の欠如、慢心など、われわれが反面教師とすべき、多数の敗者の無残な姿が、歴史のなかにさらされているのです。「負けの法則」を読み取って、自らの成長に役立てるようにしましょう。
歴史は、実際に生きた人の姿の記録です。虚構のゲームの世界に存在しえない緊張感に満ちています。それに触れて、自らの生を引き締めてほしい、そんなことも思うのです。
文字だけの情報を一次元、パワーポイントなどを用いて図示した情報を二次元、さらに動画を用いて、リアルな動きを作った情報を三次元と考えて、それを場合に応じて適切に使い分けて行くべきだということなのです。
この三者の関係を考えると、まず、次元が上がるほど作成に手間がかかるという比例関係があります。そして、同じく上がるほど、わかりやすさ、インパクトは増していくという比例関係もあります。
最近の若い人のなかには、そんなに大した書類でもないのに、パワーポイントを駆使して、ずいぶん立派なものを作り上げる人がいます。そういう人は、どういう伝え方がベストなのかを考えずに、どんな情報も、いつも同じ方法で、つまりは同じ次元で伝えようとするのです。そのせいで時間がかかりすぎてほかの仕事を圧迫したり、さらには残業せねばならないような状況に陥ったりするようでは本末転倒です。
上方には、それを伝えるにあたって、ふさわしい次元が明確に存在するのです。だからその次元を見極めて情報伝達の方法を考えるべきなのです。
どのようにして使い分けていけばよいのでしょうか?使い分けのポイントは主に二つです。
まず、伝える情報量とわかりやすさの問題です。
文字情報にグラフや図、写真といった多彩色の視覚的な情報に加えて、「わかりやすい」情報に変換することが必要となるのです。場合によっては、動画を用いて説得力を増すことも必要なのです。
次に、情報の使い分けに際してもう一つのポイントがあります。それは情報を贈る相手が、どういう情報を発信する人物であるか、ということです。
人は、自分の発信するかたちの情報に慣れているだけでなく、それが適切な伝達方法であると、無意識に思い込んでいるものです。さらに言えば、自分の情報の次元よりも低い次元の情報を「わかりにくい」と判断しがちなのです。
「できる」人は、いつも自分を批判する自分を頭の中に住まわせていますから、絶えずその自分にチェックさせて、決して独りよがりにならないものです。そういう人は、普段から自分で自分を批判していることになるので、他者からの批判にも強いですね。
やってはいけないこととわかっていても、人はつい、好き嫌いで選んでしまうものなのです。それだけでなく、嫌いなものをダメなもの、悪いものとみなして自分を説得することに関しては、かなり高い能力をもっています。
残念なことですが、人には好き嫌いの感情を、しばしば善悪の判断とすり替えてしまうクセがあるのです。
座標軸を用意するのです。
②【感想など】
・過去の失敗経験をも、その記憶が鮮明なうちに、こと細かに記録し、自分と向きあい、背負って次に活かして行こうとする姿勢は立派過ぎる。(普通の人はそこまで自分に厳しくしない)
少しでも行動等を記録をすること、それを見返すことで、かなりの自己改善が期待できそうだ。
・努力は、やみくもに何時間もするのではなく、正しい方向性とは何かを常に考え、見極め、行っていくことが大事というのは頷ける。
まずは、方向性(計画)を定め、実行し、その結果を分析の上、修正して次の方向性(計画)に反映させていく。このサイクル(PCDA)が必須ということか。
・判断や対応においては、どんなに理性的に行おうと心掛けていても、つい、好き嫌いの感情に引っ張られがちとなるのは気をつけたいものだ。
③【今後、考えてみようと思うこと、実行してみようと思うこと】
・各種勉強において、簡便で無理なく、方向性(計画)の決定、手帳での各種記録の様式、勉強実行の分析・評価と、その方向性(計画)へのフィードバックする手法
・感情的な判断に陥ることを防ぐ方法の考察
【この本のAmazonへのリンク】
≪他のページ≫
★美術展・街歩きのページ
★私のTwitter
★私の読書メーター(全記録)
★読書日記(受験本)
・現代文勉強法の考察~各問題集を巡って~【田村のやさしく語る現代文】編
・現代文勉強法の考察~各問題集を巡って~【現代文のトレーニング入門編】編
・【現代文の勉強法01】要約力、文章構造分析力、アイデア創造の発問力の強化-日本語能力試験N2編(1) 問題10(1)
・【大学への数学1対1対応の演習】の使い方・勉強法-直観力鍛錬と問題構造分析-数学Ⅰ数と式 例題8
・【能力開発】図形センスを磨き、難問を制覇する-高校への数学「レベルアップ演習」編§7合同&線分比・面積比-
・【システム英単語勉強法】600語を20日間で記憶するためにエクセルを活用した覚え方
・【英語多読】目指せ!大学受験の英文読解で100万語!
【駿台模試】受ける意味と対策勉強内容:関連ページ
・高1:第1回H25.6.9
・高2:第1回H26.6.8











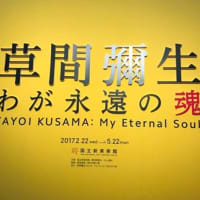






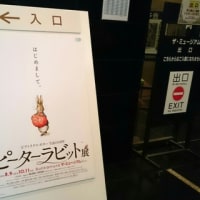

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます