渓流で釣りをしているとたまにサバのような模様の渓流魚が釣れることがある。
初めて釣ったのは確か中学生のころ。つまり45年以上前のこと。
釣った直後、水から抜き上げる時にはアマゴに見えたが手元まで寄せるとゴギに見えた。そしてよくよく見ると背中の模様がサバ模様。
直感的にアマゴとゴギの交雑種だと思った。
その後も、釣れる頻度はそう多くなかったが数年に一度釣れるという感じで、たいていは同じ川の似たような場所で釣れていた。
私が釣っていたのはヤマメ・アマゴ(以後「アマゴ」と記す)体形だったが、バンブーロッドビルダーの前川さんに見せていただいた交雑種の標本はイワナ・ゴギ(以後「ゴギ」と記す)体形だった。雄雌のうちどちらがアマゴでどちらがゴギかで体系が決まるのだろう。
また、このような魚が生まれるのは、おそらく成熟の遅れたアマゴがゴギのペアリングをかく乱したり、その逆だったりなのだろう。
しかしなぜサバ模様になるのか?
アマゴは淡い色の背景に濃い色の斑点、ゴギは濃い色の背景に淡い色の斑点。ゴギは虫食い形の斑点も混じる。この両者が交雑するとサバ模様、つまり淡い背景に濃い虫食い模様になる。
この両者が交雑することでどうしてサバ模様になるのか疑問だったが、その後ゴギを卵からふ化させて飼育する機会があり、その時にゴギも模様の出来はじめはアマゴと同じ淡い背景に濃い斑点であることに気づいた。この濃い斑点が次第に広がってつながり、元々の淡い背景が斑点として残るのだ。
つまり交雑種の模様はゴギの模様が形成される過程が途中で止まったもので、アマゴ模様とゴギ模様は同じメカニズムに支配されており、終点が異なるだけだと理解した。
似たような交雑種で人工的に作出されたものにタイガートラウトがある。これも虫食い模様だ。
通常はこれらの交配種は体内で配偶子が形成されないので繁殖能力を持たない。
ヨーロッパアルプスの南側河川にマーブルトラウトと呼ばれているマスがいる。体の模様はブルックトラウトのような虫食い模様だが鰓蓋あたりの模様を見るとブラウントラウトの模様に似ている。しかしマーブルトラウトには繁殖能力があり、ブラウントラウトとブルックトラウトの交雑種であるとの報告はない。またマーブルトラウトはブラウントラウトと交配することも知られている。ひょっとしたらも太古の昔にブラウントラウトの遺伝子に何らかの異常が起こって模様形成が途中で止まらないように変異したものが生きながらえてきた種なのかもしれない。
っと、ここまではまだプロローグである。
話の本題はここから。
20年位前だったか、なんという番組だったか忘れたが、海外の大学の偉い先生が理科好きの子供向けに講演をしている番組をたまたま視た。その番組の中でチューリングの方程式という言葉が出てきた。京都大学の近藤滋博士がタテジマキンチャクダイの体表面の模様をチューリングの方程式で再現したうえで模様が後ろから前へ移動してゆくことを予想し、観察実験の結果、模様が確かに前へ移動していることが確認され、その論文が1995年に報告されたという内容を含んでおり、シマウマやキリン、ヒョウ、トラといった動物の模様がチューリングの方程式で作り出すことができる云々の内容だった。
この時に、アマゴ×ゴギ交配種の模様もチューリングパターンだよね~っと感じてアランチューリングに興味を持ったのだ。
とはいえ当時はまだインターネットは今ほど普及しておらずチューリングの方程式について詳しく知る手立てはなかった(興味はあったが熱意はそれほどでもなかった)。
7~8年前にかみさんがベネディクト・カンバーバッチ主演のドクターストレンジのDVDをレンタルしてきた。そしてベネディクト・カンバーバッチがアランチューリングを演じている映画があることを知った。当然そのDVDを借りて視たのだが、チューリングパターンについては全く触れられていなかったのが残念だった。
そんなこんなで、チューリングの方程式に関して興味はあるが熱意はそれほどでもない時間が長く続いたのだが、大阪大学でチューリングパターンを用いた研究が行われていることを最近知った。そう、近藤博士はいくつかの大学や研究所を転任されて2009年から大阪大学で教壇に立たれていたのだった。
大阪府立大学と大阪市立大学は仕事で少し関係があったのだが大阪大学は縁がなかったねー。
そして思い出したようにチューリングパターンについて改めて勉強を始めようという気になってきたのだが、お約束通り、勉強し始めたわけではないところが重要(笑)。
波が描き出す海面の様々な模様はもちろんのこと、海を泳ぐ小魚の群れの形もチューリングパターンだろう。宇宙に散在する銀河や暗黒物質の分布もチューリングパターンに違いない。チューリングパターンは2成分の反応拡散方程式から得られるが、これを3成分以上に増やすことで世の中で起こっている現象のすべてが説明できるような気がしてきた。
何年か前にも投稿したが、どんな生物でも体を構成する全ての細胞は同じ遺伝子を持っているにもかかわらず、体のどこにあるかによってその形と機能が異なる。一つの細胞から分裂し、細胞が増えてゆくにしたがって細胞は自分が何になるべきか知っていたかのように分化してゆく。これにも反応拡散系が作用しているのだろう。つまり細胞または生物の発育初期段階に外から何らかのシグナルを与えることで狙った器官に分化させることが可能なはずだ。
ES細胞やiPS細胞は(一時期話題となったSTAP細胞も)再生医療への利用を目指して開発が続いているが、これらの幹細胞をそのまま患部に接種しても狙った組織になってくれる保証はない。したがって接種前に何になるべきかを幹細胞に教える必要がある。この研究なしに再生医療はない。そしてこの研究を加速させるのが反応拡散系の理解だろうと勝手に期待しているところではある。
しかし、反応拡散系のシミュレーションで狙った器官への分化が得られたとして、しょせんコンピュータ上でシミュレーションに与えるパラメータは数値データである。細胞に向かってこのパラメータを叫んだり紙に書いて培養シャーレの下に置いてみたところで細胞にパラメータは入力されない。
細胞に対して何を行えば適切なパラメータとして作用するのか?
この解明は至難を極めるだろうな。
ゲノムを解析してその発現を促す方が手っ取り早いのかもしれない。
研究のために欲しい生体組織が必要な時、今は培養細胞を使うか、培養できていない組織の場合は生物から取り出すしかない。培養細胞にしてもシャーレの底に単層に培養するのが関の山で立体的な組織を作れるには至っていない。
人工的に試験管やフラスコの中に立体的な組織を形成させることができれば医療の研究はどれだけ加速できるだろう?少なくとも実験動物を殺す必要がなくなる。
さらに、この技術が発展して牛肉を作ることができれば牛を殺す必要がなくなり牛を飼う必要もなくなり、地球温暖化問題が解決に向かう。
さらにさらに、魚肉を作ることができれば、漁師は命を懸けて荒れた海に出て行く必要がなくなる。資源管理も必要なくなる。
未来の人類が、宇宙ステーションでおいしいフィッシュバーガーが食べれるように、この技術を早く実用化していただきたいものだ。










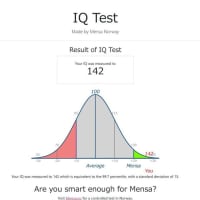
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます