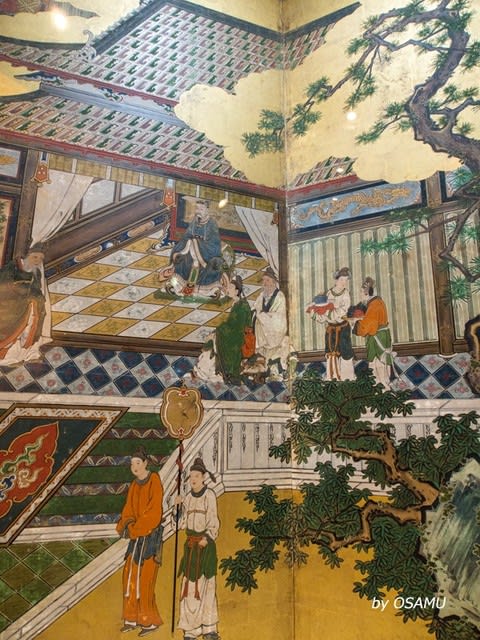撮影日:2019年12月14日
今年最後の名残の紅葉と各地で見かける山茶花を撮りに行ってきました。
公園内の至るところに咲いていて、しかもたくさん、写真もたくさん撮りました。
1)陸上競技場周辺で

2)陸上競技場周辺で

3)ガマ池周辺で

4)ガマ池周辺で

5)ガマ池周辺で
確か、今年最初の撮影(1月19日)は庄内緑地の山茶花でした。息が長いですね。

6)寒椿でしょうか

7)ドウダンツツジの紅葉

8)紅、黄、緑のグラデーションが見られました

9)絵画的な仕上がりになりました

10)ガマ池を囲むドウダンツツジと山茶花とラクショウ
モミジのように真っ赤ではありませんが、枯色が落ち着いた感じです

11)アングルを変えて

12)身なのでしょうか

13)左手にボート池、右手はピクニック広場です
こちらはメタセコイヤ

14)ゲートボール場に沿って立つメタセコイヤ

15)マンサク、もう来春の準備が始まっています

16)落ち着いた色でも陽があたっていると綺麗です

17)黄色も映えます

18)名残のモミジ

19)本当にこれが見納めです

昨年から始めたこのブログ、今年は1年やり遂げることができました。
来年も色々な所に出かけて、多くの写真を撮りたいと思います。
今年最後の名残の紅葉と各地で見かける山茶花を撮りに行ってきました。
公園内の至るところに咲いていて、しかもたくさん、写真もたくさん撮りました。
1)陸上競技場周辺で

2)陸上競技場周辺で

3)ガマ池周辺で

4)ガマ池周辺で

5)ガマ池周辺で
確か、今年最初の撮影(1月19日)は庄内緑地の山茶花でした。息が長いですね。

6)寒椿でしょうか

7)ドウダンツツジの紅葉

8)紅、黄、緑のグラデーションが見られました

9)絵画的な仕上がりになりました

10)ガマ池を囲むドウダンツツジと山茶花とラクショウ
モミジのように真っ赤ではありませんが、枯色が落ち着いた感じです

11)アングルを変えて

12)身なのでしょうか

13)左手にボート池、右手はピクニック広場です
こちらはメタセコイヤ

14)ゲートボール場に沿って立つメタセコイヤ

15)マンサク、もう来春の準備が始まっています

16)落ち着いた色でも陽があたっていると綺麗です

17)黄色も映えます

18)名残のモミジ

19)本当にこれが見納めです

昨年から始めたこのブログ、今年は1年やり遂げることができました。
来年も色々な所に出かけて、多くの写真を撮りたいと思います。