今回の冊子「地方議会人」の特集は、住民にとっても情報として知ってもらいたい興味のあることではないのかと思い載せました。 普代村議会の状況や、偏っているかも知れませんが個人的感想も入れさせてもらいました。報酬や定数は村民の方々には時々聞かれます。意見も言われます。 情報は判断材料になります。 このブログの、少ない読者ではありますが少しでも参考になればと。
平成20年4月から議員報酬を日当制にしたことで全国から注目を集めた福島県の矢祭町。
いまだに揺れているのだろうか・・・詳しくはこちら
議員報酬「日当制」 <矢祭ショック!>福島県 「地方議会人」5月号(②の山梨学院の先生より)
『日当交付の対象を議会活動(本会議・委員会等への出席)に限定して議会議員活動を狭めたことや、政務活動費や議会事務局の充実を行わなかったことから、議会力を低下させるものである。』という見方です。
『とりわけ町村議会では、日当制の方が現行の報酬よりも増額するという自治体も多い。』
なぜ増額なのかはよくわかりません。
マスゴミでよく取り上げられますが「政務調査費」という、報酬外の収入は普代村議会ではありません。
7年前に福島県飯舘村に議員研修の一環で参加した中で、矢祭町の議員が「日当制を決めるのに議論もなく、数週間で決定してしまった。」と不満をもらしていました。
「そもそもが日当制は議員不要論から出た発想であった。」というような意見でした。
「議員になりたい、バッジをを付けたいという単なる名誉のためだけに立候補する人もいる。そんな人は報酬はなんぼでも関係ない。議員の仕事もしない。」というようなことも言っていました。
確かに、ある程度の年金をもらっている人にとっては、議員報酬はいくらでも困るものではありません。 非常に面白くなさそうだった記憶があります。
個人的愚痴になりますが、たまに聞かれます。
「1カ月にに何回ぐらい議会に行くのか?」
なんと答えていいのか困ります。役場に会議として行くのは何回もありません。
決算・予算等の定例会がある月は多い。それ以外の月は2回程度の時も珍しくない。
「それで報酬もらえるならいいなあ。」と言われます。
役場に出向く回数で判断されます。(月20回と言えばよかったと後悔します(笑 )
議会関係のほか、議員になったことで年々あて職や、出席、顔出しなどが増えてきます。
自分の仕事以外に毎月コンスタントに一週間から多いときは15日以上は予定表が埋まる。
補佐役(妻など)がいないと仕事との両立は難しい。仕事や身内の緊急ごとが重なるとどうにもならない。
妻は緊急時協力隊として常に待機してもらっている。が失礼をする所もたびたびです。
全部に出席は不可能ですが、それでも「議員なんだから」と出席しないことを言われたりします(笑
仕事を持つ議員は誰でも経験していると思います。
議員は万能を求められますが、議員の何を見て評価するのか住民それぞれの判断に委ねられます。
議員批判というのは、万能でないことへのそれなのかもしれません。
そういったことの解決策としては、次の議員報酬の在り方も関わってきます。
専任でやれるだけのものであれば、「本業」がライフワークから抜けるだけで自由度は高まります。
収入と時間だけで言えば、村議員は「公務員を退職した年金を受けている人」というのが適しているような気もします。
<議員報酬の基礎調査を行った会津若松市議会の試み広がる>
『A領域:議会活動 B領域:議員活動
C領域:議会活動・議員活動に付随した活動(質問や議案に関する調査等)
X領域:それ以外の議員活動(議員としてかかわる住民活動)
この領域のそれぞれの時間数を選定する。そこで算定された時間数を、
首長(村長)の活動日数と比較する。その割合に基づき、首長の給与から議員の報酬を割り出す。』
という方法だそうです。
『この方式は、住民と議論する際の素材であって、科学的な基準ではない。
また、議員活動を示しただけでは、』 (各領域にこれくらい時間を費やしましたというだけでは)
『「だから何?」と住民から言われるだけである。住民福祉の向上につながったのか自己評価する』
説明が必要であると言っている。
確かに、住民生活の視点でどうであったかという説明ができなければ、パート勤務に出たのと
たいして変わらないことになる。
『この方式は、容易に時間給の発想と結びつく。しかも、活動する議員とそうでない議員との差も肯定される。
・・・・(途中略)これは全議員が活動してほしいという規範的意味がある。』
ということで、議員の活動の差が分かりやすくなるということなのでしょう。
『この議論で多様な属性を有する議員を登場させることができるかという重要な論点が浮上する。
会津若松市議会の場合、年収700万となっている。兼職も多いが専業もいる。』
財政規模の小さい町村議会にはとても当てはまらないが、議員報酬の議論の裏にはその資質向上の課題が含まれて
いるという意味では参考になると思います。
こういった議論(議員報酬・議員定数・住民との関係性)は我々議員・議会はいくらでも避けることができます。
住民との関係性についても、いくらでも距離を置くことができます。
議会、議員が「課題」として表沙汰にしない限り、議論のテーブルには乗りません。
「寝た子を起こす」ことにもなりかねないという恐怖もあります(笑
しかし、動く議会は動いています。 住民は詳しく内容を把握できないので住民から議論として出ようはないです。
普代村議会は、今度改選してからは委員会の「総務」と「産業経済」との所属を分けたこともあり、
自発的な「委員会活動」が積極的になりました。(議員になって10年。自発的委員会活動は初めてです)
住民との意見交換会もなんとか挑戦しはじめ委員会活動など、その忙しい感は増しています。
これを維持していくには、テンションの低さもさることながら、すでに今の議員数ではきつくなっているのかとも思います。(特に有職議員には)
小規模議会でも大規模でも、最低の「委員会」数は必要で、その活動・議論時の活発性は人数が少ないほど弊害が出ます。(少ないと議論もなくナアナアとなり、一人の意見だけで決してしまう。)
(再び山梨大の先生)↓
『討議できる人数として一委員会につき少なくても7~8人必要である。
科学的根拠があるわけではない。積極的討議ができる経験知である。』 と言っています。
普代は4人から5人。議長役となる委員長を除けば、3~4人の審議となります。
雰囲気が分かろうというものです。 闘議(討議)にはならない。
改選前は委員会にはみんながダブって所属していました。
委員会活動もなく別に影響することはなかったのですが、どの委員会も同じメンバーで
委員会の認識がないまま出席していました。(自分がどの委員会で出席していたのか自覚していた記憶がない)
『委員会数は同じでも、複数所属により議会全体の定数を削減することは理論上可能である。
しかし、複数所属を実践した飯田市議会では、しっかりした審議はむずかしいとして、一つの委員会の
所属に戻している。』 という例もあるようです。
最後に、
根本的には、住民の疑問として議会が本当に必要なのか? どう役に立っているのか?
議会がなくても村長・職員がいて村は何とかなっているのではないのか?
議場で質問してそれがどうしたのか?
という想いは感じていると思います。 自分も感じている疑問です(><)
10年経験させていただき、「村民のために役に立っている」という実感はない。
自分がそこまでの活動をしていないからだと思います。 議員ひとりではなにも動きません。
「議会と首長は車の両輪の関係で対等の立場」だと比喩的に言われますが、
両輪というより議会はホイールのナットぐらいのものです。
首長の権限がはるかに大きい。ナットが一つ二つぐらいなくても車は動けます。
(巻頭言の中邨先生)↓
『二元制では首長と議会は対等という見方である。これは間違いである。日本は予算編成権、人事権、再議権をはじめ、議会予算など、多数の権限を首長に与える「強い首長制」を採用している。』
『首長と議会は対等などと誤認している限り、議会改革にたいした成果は期待できない。』
『地方議員は弱い立場に立つ議会機能をどう強化するか、その点を目玉にしなければならない。』
『もう一つ住民の議会不信を招く原因がある。ウラ舞台で行われている政治交渉をオモテに出す工夫を重ねなければならない。』
と手きびしい。












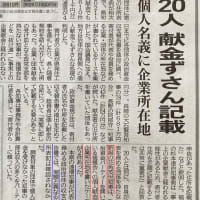
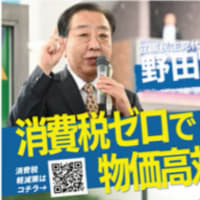


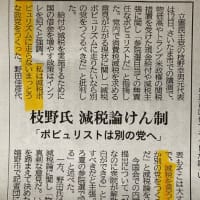



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます