勤めている会社が破産しては困るので、「あまり借金するな」「設備投資はするな」
「従業員の福利厚生は控えろ」という従業員はいません。
借金し、設備投資しなければ生産量を増やし、お金を増やすことはできません。
シャッキンしてでも給与を払ってもらいたいと思うのが従業員です。
それが従業員の安定と安心になります。
政府に例えれば、国民の富と安心ですが、政府のシャッキンは非難します。
現在、政府の借金約1,100兆円です。
この借金が「家計の金融資産分を上回ったら破綻する」という学者さんもいるらしいです。
政府の借金が、国民の預金とか現金の総額より多くなれば破綻するという意味です。
しかしです、
政府の借金が増えれば、「家計の金融資産」は増えていく仕組みだといいます。
政府の借金が「家計の金融資産分を上回る」ことはありえないという事になります。
政府の借金が増えるほど、民間のお金が増えるというのが現実の仕組みのようです。
それと一致したことを主張し、危機感を持った大西つねきさんという人がいます。
「政府の国債残高と国民の金融資産はイコールである」といって、国民は騙されているか、政府は勘違いしていると、全国をボランティア同然に講演して歩いている元外資系金融機関の専門家がいます。
そもそも国民が借金してはいないので、政府の借金と家計を比較するのはおかしいのです。
「Aさんちの借金がBさんちの預金を上回ればAさんちの家計が破綻する」という論理になります。
変です。少しだけじゃなく、大変です。
では、政府の借金はどこまで行けば破綻するのでしょう?
金利が上がらない限り無限だそうです。金利の話はよく分かりません。
まあ、「政府の借金で日本は破綻する」は幻想である可能性大ではないか?
その可能性を歴史が証明
明治からの政府の借金統計があるようです。
聞きかじって書きます。
「財政破綻論」は今から44年前
1975年 通常予算において初の赤字国債発行(三木内閣)
大平正芳大蔵相「万死に値する!一生かけて償う。」と発言したそう。
このとき債務残高 約32兆円➡今その34.5倍
1982年 鈴木善幸首相 「財政非常事態宣言」
このとき債務残高 約205兆円➡今その5.4倍
1995年 武村正義蔵相 「財政危機宣言」
当時、家計の金融資産も同程度に低かったはずです。
それが家計の金融資産も34倍以上になったはずで、国民のカネも増えているはず。
政府の借金を返して、大平さん当時まで戻し、国民も貧乏になりたいわけではないはずです。
「政府の借金を減らす」ことは、市場に金が投入されなくなり国民が貧困化することです。
今そのプチ状態なりつつあるのではないか?と思うのです。
緊縮財政政策継続中で、国民から搾り増税して借金を減らすというのですから。
2018年の政府の債務残高約1,100兆円は、1970年の152.6倍となるそうです。
初めての「財政破綻論」から44年。 大平さんはこの金額で破綻せずいることにひっくり返っているのではないか? 「いつ破綻するのだ?!」と言って。
こういうのを聞くと、石油が枯渇すると騒がれたことを思い出します。
もう50年も前に、「石油はあと30年しか持たない。」「いやいや10年だ。」とか言われ騒がれました。
今にすれば完全なフェイク情報でした。
政府は最近まで「景気がいい」ような情報を流していますが、今金利が非常に低い。
金利が低い要因は、「借り手がない」からです。それは景気、経済状況が悪い、あるいは先行き不安で投資しないから借りません。
だから金利が上がらないのが市場原理で、借り手がないほど悪化している証明です。
政府のミスリードが招いているということはないのでしょうか。
どの口から「景気がいい」と言えるのでしょうか?
政府は木を見て森を見ず。一部の上場企業しか見ない判断をしているように見えます。
そこに末端の庶民は存在していないかのように。
そんな統計の取り方をしているのかも知れません。
「投票結果を真摯に受け止め」とぬかすそばから辺野古国民の意思が無視されて、埋め立てを平然と進める政府。
我々末端国民も辺野古国民と同じに、地方の国民を無視した政策を進めていくのだろうと思う今日この頃です。















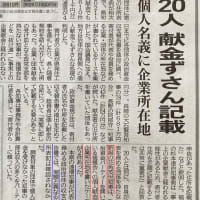
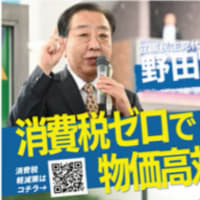


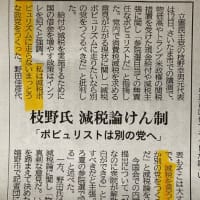
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます