今年最後の北回り鵜鶏神楽巡業が3/25堀内漁村センターで行われました。神楽の事はあまりよく分かりませんが、文化財に指定され、追手門学院大学・民俗学の橋本先生の話を聞く機会もあったり、少しずつなじんできています。
今年は関東方面からのツアー客と八戸からの観光バスツアーもあり、100人1以上と思われる人手となりました。

北回りは普代村・野田村・久慈市を回るということのようです。

神楽の前の1時間ぐらい(ごご2時ごろまで)各地の宿主さんの話があり、裏方のご苦労もあることを知りました。
いよいよ神楽がはじまりです。



関東からのツアー客の方々と楽しく談笑させていただきました。(写真はお開き直前で人も減っていますが)
話は飛びますが、桜は、「咲く(サク)」ということばがついた唯一の花だそうです。
「サク」は「先、崎」「坂」などと共通のことばだそうで、木の枝の先に咲く花は命の象徴でもあるといいます。
咲くということばを含む桜の花は、日本人にとって「生と死」に対する美意識を象徴しているのだそうです。
これを読んで、河津桜のことを思い出し、やはり日本人は桜に特別の想いをいだくものなのかなあとつくづく・・・
そして「生と死」といえば・・・神様。 神様といえば・・・神楽。
神話に、コノハナサクヤヒメとイワナガヒメの説話があるそうです。
このイワナガヒメ(岩長姫)、きのうの神楽に毎度でてまいります。
よく分からないで見ているのですが、
「ニニギノミコトは美しいコノハナサクヤヒメに一目惚れをし妻乞いをしますと、父のオオヤマツミは姉のイワナガヒメ(岩長姫)も一緒に嫁がせる。
ところが
こう言ってはナンですが、イワナガヒメは「ブス」だった。
ニニギノミコトは「ブス」はいらないと追い返してしまった。
オオヤマツミ(父)は怒ります。
二人を嫁がせたのには意味がある。コノハナサクヤヒメは華やかな栄光を、イワナガヒメは岩のように強固に末永く続くことを祈ってのことだったのだ。
イワナガヒメを返した以上、ニニギの栄光は長く続くまい。そう呪いを送ります。
それ以来、神々の命は長く続かなくなってしまったのだそう。」
とまあ、
こんな分かるような分からないような神話です。
タマタマ目にした文章で、前日の神楽との縁を感じて読みました。
横浜から来たというツアーのお客様が、興味深いことを言っていました。
「神楽を観光客用に見せるための仕掛けをしているところはいっぱいあります。ここは観光客用でなく、地元の人が行事としてやっている、その空気を一緒に感じることができるので我々にとっては貴重な体験です。」
観光用のヤラセでは、人を引き付けることはできないということなんですねぇ。逆に観光客に盛り上げてもらった神楽となりました。















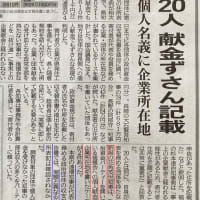
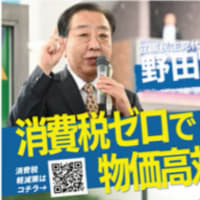


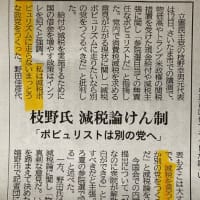
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます