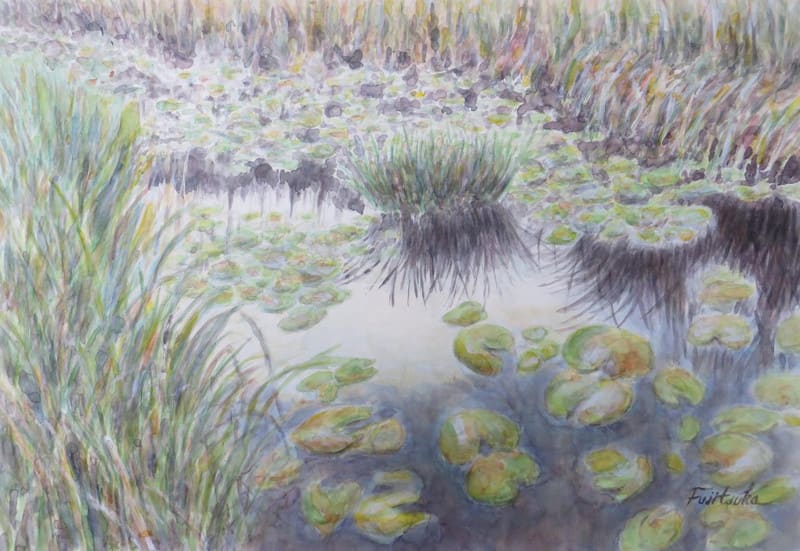北勢線の起点「西桑名」駅
鉄道大好きの「鉄道マニア」たちの人気ラインである三重県の三岐鉄道北勢線沿いを、水彩画で描いている古川幾男さんの作品展が30日、北勢線星川駅に近い「星川サンシティ」(桑名市星川)で始まりました。「桑名のスケッチと仲間の写真展―北勢線と員弁街道」。6月1日(日)まで、わずか3日間の開催ですが「鉄旅」を兼ねていかがですか。
古川さんは桑名市で生まれ、育ち、東京で勤めを終えたあと帰郷。絵筆とカメラを手に「ふるさと桑名」を歩き、その作品をブログ「桑名のスケッチ」
http://blog.livedoor.jp/ikuo16125/
で発表するとともに、先週開催した僕たち水彩画グループ「風の游子展」のメンバーとしても活躍しています。
古川さんが水彩画、写真の主なテーマにしているのは、JR・近鉄桑名駅そばの西桑名駅から、いなべ市阿下喜駅まで20.4㌔を13駅で結ぶ北勢線。ナローゲージという線路の幅が762㍉しかない全国でも珍しい路線ですが、ことし開通100周年を迎え、全国から鉄道マニアが訪れています。
今回展示しているのは3、4号サイズから10号サイズまで計36枚。街なかを走る電車、無人駅、線路を渡る自転車の女性、車内の乗客、遅れまいと走る女子高生などを巧みな筆さばきで描いています。鉄道をテーマにすると、ともすれば同じような構図になりがちですが、一枚一枚に沿線住民の暮らしを感じさせるあたり、さすが古川さんです。
同時に展示されている写真の中にも、古川さんが数枚出しています。
古川さんは話します。
「東京から帰って、ふるさとの変貌ぶりに驚き、絵と写真で残しておかねばと思いました。7年ほど前から始めましたが、北勢線沿線でもまだスケッチできたのは半分ぐらい。まだまだ続けます」