既に読んだ方もおられるかと思いますが、幾らか老人ボケしている私ですから、読み返し頂いたコメントで勉強したいと考えここに転載します。
そこで頂いたコメントの中から幾つかのコメントを紹介いたします。またそのコメントに対し充分に答え切れていないものを、このブログで補足していきたいと思います。
コメント
01. 2010年10月29日 18:36:07: IOzibbQO0w
http://www.boj.or.jp/theme/currency/okane/index.htm
貨幣は、日本銀行ではなく、政府が発行しています。貨幣は、独立行政法人造幣局が製造した後、日本銀行へ交付されますが、この時点で貨幣が発行されたことになります。
貨幣も銀行券と同様に、日本銀行の取引先金融機関が日本銀行に保有している当座預金を引き出すことを通じて、世の中に送り出されます。
http://www.boj.or.jp/theme/currency/stat/index.htm
02. 縄文ビト 2010年10月29日 21:38:05: egUyw5BLxswRI : g6DT8nixac
IOzibbQO0wさんコメントありがとうございました。
ただ私が書こうとしていることは、簡単に言えばこのような貨幣の仕組みがなぜできたのかということになります。そこには長い時間をかけて現在の仕組みまで到達してきたということです。ただそのような仕組みだけでは片つけられなくなっているのが今の経済情勢ではないのでしょうか。
私が考えていることは根本から貨幣を考えることによって、どのような使われ方をしていけばいいのかということです。
また何かありましたらコメントを入れてください。
02. 2010年10月30日 01:39:35: IqDrSmvKOo
お爺ちゃんは、もう少し長生きして待ってれば、「貨幣はなぜ市中に溢れてしまうのか」と嘆いて、「貨幣に保存機能があったら、人間社会はうまくいっていたはずである。」とか言う羽目になる事態に出会えるよw
今「貨幣」だと多くの人が思い込んでいる福澤諭吉を印刷した紙片と通帳上の数字に実際に保存機能があるのか、歴史的体験ができるよw
それで、そのブログの主張は一行目から間違えていたことを痛感することになるよw
もちろん、二行目以下は言うまでもないw
その「貨幣」は、お上(おかみ)が発行したという信用だけが頼りのものだw
そのお上が何十年も借金を重ねて飲む打つ買うの放蕩三昧をしてきたのが現在だw
しかし、今まで下々(しもじも)は、景気が悪くなれば、お上がそうすることで不景気をしのげるんだというケインズ様の教えを信じ合ってきたww
しかし、不景気は深まるばかりだ。
戦後最長の景気と言われた時期にすら苦しむ者は多かったw
邪教だと気づくには遅すぎたw
長らく信心してきたその教えが邪教であると見抜いた者は、この島には今も少数しかいないw
墺太利(オーストリア)の福音の伝来を知っている者は、わずかだw
実際にはケインズよりも遡って百年以上前から邪教を操る者たちに経済学が支配され始めたw
神器の一つ「貨幣」の本体がすり替えられていたのだw
貨幣は、お上が決めるものではなく、市場が決めるものであり、交換と保存の用を足す品物に過ぎないw
それは、歴史的に金銀であるw
保存機能が高いものが好まれるのは当然だw
長期計画が可能になり文明が生まれるw
それを「規制」で取り去るというアイデアは文明の否定だw
まさしく、このお爺ちゃんは、旧石器時代に憧れているw
ブログで自分の意見を発信できるのは、文明のお蔭なのにw
それどころか、その年(70歳代)まで生きれないw
生産性が下がって実際の富(資本)が減少しているうえに、お上の御乱行に費やされて、さらに経済は悪化しているw
お上にさらに御乱行して頂けば「ギャップ」が埋まる!、お上の借金から「貨幣」をもっとたくさん作り出せばいい!と邪教を説く者たちが叫き立てているw
その自滅的な教義をオウム返しする信者たちの扇動が日に日に高まっているw
お爺ちゃんが待ち望む日(貨幣が保存機能を失う日)がさらに近づくw
そして、「自身の労働を貨幣に換える」機会も奪わた者が続出しているのも、お上が決めた「規制」があるためだw
04. 縄文ビト 2010年10月30日 06:30:59: egUyw5BLxswRI : g6DT8nixac
IqDrSmvKOoさんコメントありがとうございました。
>お爺ちゃんは、もう少し長生きして待ってれば、「貨幣はなぜ市中に溢れてしまうのか」と嘆いて、「貨幣に保存機能があったら、人間社会はうまくいっていたはずである。」とか言う羽目になる事態に出会えるよw
J 現在の貨幣に保存機能が無く、将来保存機能を持つということですか?
>今「貨幣」だと多くの人が思い込んでいる福澤諭吉を印刷した紙片と通帳上の数字に実際に保存機能があるのか、歴史的体験ができるよw
J この文章もひじょうに関心が涌く文章です。つまりは貨幣がいらなくなる社会ということでしょうか。
>貨幣は、お上が決めるものではなく、市場が決めるものであり、交換と保存の用を足す品物に過ぎないw
それは、歴史的に金銀であるw
J 金銀、それは量的に限界があるものです。そして現在でも金銀が高騰しているのも希少性ゆえです。もし金銀を貨幣にしていれば、現在よりまして市中に出回る量の不足から輪をかけたデフレになりますよ。それを嫌気して金本位制を捨て、紙幣の発行にしたことではないですか。 IqDrSmvKOoさんには解りきったことでしたが。
>生産性が下がって実際の富(資本)が減少しているうえに、
J 人間の労働から離れてロボット等が生産する商品としては、確実に生産性は上がっていますよ。そのことによってインフレにならなくなっているのが現状ではないですか。
また>資本が減少している。これは株が下がったことを言っているのですかな?
もう少し続けられたらコメントを通して続けてください。できればもう少し解りやすく書いていただければ、理解できる人が多くなるはずですが。でも久しぶりに考えさせられました。
5. Monster 2010年10月30日 09:40:52: rnKrp.8thaSuQ : vObzQxM5Pc
お金は何のために造るのか。それは生産を引き出すためであると越前福井藩の三岡八郎は知っていました。
だから坂本龍馬が江戸幕府を征伐する軍資金がないといったときに、金はあると言ったのですな。
金は信用があれば造り出すことができるが、その担保は生産力である。そこで、三岡八郎は、この供給余力を引き出すために政府紙幣を発行すればいいと提案します。
坂本龍馬は頭のいい人でしたから、すぐに理解しました。
金は生産力からうまれると。
そこで、三岡八郎を西郷、大久保に強く推薦しました。
慶応三年から慶応4年(明治元年)、鳥羽伏見の戦いの軍資金から国家財政の2年間ぶんの95%を政府紙幣でまかなったのです。
だから政府紙幣がなければ明治維新はなかったと言われるのです。
現在の日本もデフレギャップが500兆円ほどありますから、それだけ発行すれば閣議だけで発行できて、1年で高度経済成長が達成できるでしょう。
06. 2010年10月30日 10:07:55: ZTceO6aYDc
Wを多用する03はこの手の話になるといつも出てくる御仁だと思われるが、自説の結論だけ言って何故そうなるかの説明がほとんどない(できない)のはいつものとおり。縄文ビト氏もお分かりのように、文章自体が支離滅裂ですから突っ込むだけ無駄です。たぶんデフレギャップの概念が理解できないのでしょう。
07. 2010年10月30日 10:14:20: K582KxQR8o
貨幣は信用のしるしでしょう。 ケインズより遥かな昔から取引の仲介として使われてきた。 金や銀が好まれたのは、何時までも光っているところが嬉しかったのでしょう。 定型化されて単位が生まれてさらに使いやすくなった。 もとが信用だから取引の規模と頻度が拡大すれば金や銀が不足する。 だから現在はただの紙ッ切れになった。 自然発生的に生まれたものだが、時の権力者が貨幣の発行権を独占している。 実際には時の権力者と裏口で取引した金融業者が紙幣発行の権利を持っているということ。 本来は物とサービスの交換のための補助的な機能だったはずの金融業が、権力と結びついて支配構造の中の重要な部分を占めるに至ったのでしょう。 取引が拡大するには貨幣も増加しなければならないが、取引が減少すれば流通通貨も減少するのは当然のこと。 通貨や信用自体が取引されるようになれば、物理的な通貨の存在は必要でなくなる。 ブッキングだけされてあれば良いのだが、取引の証拠として証券が出来てこれも通貨として勘定には加算される。 貨幣は何故市中から消えたかという設問であれば、取引の減少や価格の逓減によって流通通貨も減少するということでしょうな。 一般的には景気が悪いという状態だから流通通貨も減ってしまう。 様々な形態の資産勘定があり、一応はそれらが通貨の単位で計られているから、経済の規模を示す数値は大きくてもそれが物流に関係の無い信用取引の部分が大半であれば、流通通貨は不要であるといえるでしょう。 中央銀行なる組織が、調整と称して不要な分を引き上げているから通貨が減ってしまうというのが正解。 日本のGDPは大雑把に言えば500兆円だが、流通通貨の合計は75兆円程度の筈です。 これを増やせばインフレになり、さらに減らせばデフレがひどくなる。 多少のインフレの方にシフトしたければ消費と投資(投機ではない)を増やせば良い。 それを実現するのには権力者に対する一般の信認が必要だろうと思います。 経済は人間の心理的なファクターが大きく影響するので、権力者(総理大臣だけのことじゃなくて、社会の支配者)に対する信用が薄ければ沈滞するのでしょう。 N.T
08. 縄文ビト 2010年10月30日 10:44:10: egUyw5BLxswRI : g6DT8nixac
rnKrp.8thaSuQ : vObzQxM5Pさんコメントありがとうございました。
確かにおっしゃることは解ります。紙幣はある意味政府の信用力にかかっていると言えます 。ある意味というのは他に交換財としての貨幣に変わるものがないという意味です。それゆえになんとしても一国一通貨を守ろうとするわけです。他の通貨に対しては偽札になるわけです。
>だから政府紙幣がなければ明治維新はなかったと言われるのです。
J その時代だからできたのです。庶民が交換財として流通する貨幣が欲しかったからと、信用力があったからだと言えます。
ただそれだからといって、政府発行紙幣を増刷すれば確実に信用力のある通貨を使いたがるでしょう。そのとき信用力のない通貨は交換においてその価値を減じてしまいます。
つまり信用力のある通貨は現在の基軸通貨としてのドルに例えられます。ドルは大量に増刷した結果信用力を失い他の国の通貨に対し価値を減じてしまいました。でも交換財として変わるものが無ければやむなく使っているのが現状ではないですか。
09. 縄文ビト 2010年10月30日 11:00:27: egUyw5BLxswRI : g6DT8nixac
K582KxQR8o さんコメントありがとうございます。
>貨幣は何故市中から消えたかという設問であれば、取引の減少や価格の逓減によって流通通貨も減少するということでしょうな。
J これをこれから書こうということです。おっしゃっている意味は貨幣を通して交換の回数が減ってしまったということではないのでしょうか。
>中央銀行なる組織が、調整と称して不要な分を引き上げているから通貨が減ってしまうというのが正解。
J 問題はどのようにして引き上げるかと言うことになります。中央銀行が強権力で引き上げるわけではありませんし、銀行が抱えている通貨を理由をつけて引き上げるわけだと言えます。そのとき銀行に集まった通貨はどのようにして集めたのかと言うことになります。
ここからは私がブログで書いていくことになりますので…
まだコメントは残っています野で次回紹介いたします。
そこで頂いたコメントの中から幾つかのコメントを紹介いたします。またそのコメントに対し充分に答え切れていないものを、このブログで補足していきたいと思います。
コメント
01. 2010年10月29日 18:36:07: IOzibbQO0w
http://www.boj.or.jp/theme/currency/okane/index.htm
貨幣は、日本銀行ではなく、政府が発行しています。貨幣は、独立行政法人造幣局が製造した後、日本銀行へ交付されますが、この時点で貨幣が発行されたことになります。
貨幣も銀行券と同様に、日本銀行の取引先金融機関が日本銀行に保有している当座預金を引き出すことを通じて、世の中に送り出されます。
http://www.boj.or.jp/theme/currency/stat/index.htm
02. 縄文ビト 2010年10月29日 21:38:05: egUyw5BLxswRI : g6DT8nixac
IOzibbQO0wさんコメントありがとうございました。
ただ私が書こうとしていることは、簡単に言えばこのような貨幣の仕組みがなぜできたのかということになります。そこには長い時間をかけて現在の仕組みまで到達してきたということです。ただそのような仕組みだけでは片つけられなくなっているのが今の経済情勢ではないのでしょうか。
私が考えていることは根本から貨幣を考えることによって、どのような使われ方をしていけばいいのかということです。
また何かありましたらコメントを入れてください。
02. 2010年10月30日 01:39:35: IqDrSmvKOo
お爺ちゃんは、もう少し長生きして待ってれば、「貨幣はなぜ市中に溢れてしまうのか」と嘆いて、「貨幣に保存機能があったら、人間社会はうまくいっていたはずである。」とか言う羽目になる事態に出会えるよw
今「貨幣」だと多くの人が思い込んでいる福澤諭吉を印刷した紙片と通帳上の数字に実際に保存機能があるのか、歴史的体験ができるよw
それで、そのブログの主張は一行目から間違えていたことを痛感することになるよw
もちろん、二行目以下は言うまでもないw
その「貨幣」は、お上(おかみ)が発行したという信用だけが頼りのものだw
そのお上が何十年も借金を重ねて飲む打つ買うの放蕩三昧をしてきたのが現在だw
しかし、今まで下々(しもじも)は、景気が悪くなれば、お上がそうすることで不景気をしのげるんだというケインズ様の教えを信じ合ってきたww
しかし、不景気は深まるばかりだ。
戦後最長の景気と言われた時期にすら苦しむ者は多かったw
邪教だと気づくには遅すぎたw
長らく信心してきたその教えが邪教であると見抜いた者は、この島には今も少数しかいないw
墺太利(オーストリア)の福音の伝来を知っている者は、わずかだw
実際にはケインズよりも遡って百年以上前から邪教を操る者たちに経済学が支配され始めたw
神器の一つ「貨幣」の本体がすり替えられていたのだw
貨幣は、お上が決めるものではなく、市場が決めるものであり、交換と保存の用を足す品物に過ぎないw
それは、歴史的に金銀であるw
保存機能が高いものが好まれるのは当然だw
長期計画が可能になり文明が生まれるw
それを「規制」で取り去るというアイデアは文明の否定だw
まさしく、このお爺ちゃんは、旧石器時代に憧れているw
ブログで自分の意見を発信できるのは、文明のお蔭なのにw
それどころか、その年(70歳代)まで生きれないw
生産性が下がって実際の富(資本)が減少しているうえに、お上の御乱行に費やされて、さらに経済は悪化しているw
お上にさらに御乱行して頂けば「ギャップ」が埋まる!、お上の借金から「貨幣」をもっとたくさん作り出せばいい!と邪教を説く者たちが叫き立てているw
その自滅的な教義をオウム返しする信者たちの扇動が日に日に高まっているw
お爺ちゃんが待ち望む日(貨幣が保存機能を失う日)がさらに近づくw
そして、「自身の労働を貨幣に換える」機会も奪わた者が続出しているのも、お上が決めた「規制」があるためだw
04. 縄文ビト 2010年10月30日 06:30:59: egUyw5BLxswRI : g6DT8nixac
IqDrSmvKOoさんコメントありがとうございました。
>お爺ちゃんは、もう少し長生きして待ってれば、「貨幣はなぜ市中に溢れてしまうのか」と嘆いて、「貨幣に保存機能があったら、人間社会はうまくいっていたはずである。」とか言う羽目になる事態に出会えるよw
J 現在の貨幣に保存機能が無く、将来保存機能を持つということですか?
>今「貨幣」だと多くの人が思い込んでいる福澤諭吉を印刷した紙片と通帳上の数字に実際に保存機能があるのか、歴史的体験ができるよw
J この文章もひじょうに関心が涌く文章です。つまりは貨幣がいらなくなる社会ということでしょうか。
>貨幣は、お上が決めるものではなく、市場が決めるものであり、交換と保存の用を足す品物に過ぎないw
それは、歴史的に金銀であるw
J 金銀、それは量的に限界があるものです。そして現在でも金銀が高騰しているのも希少性ゆえです。もし金銀を貨幣にしていれば、現在よりまして市中に出回る量の不足から輪をかけたデフレになりますよ。それを嫌気して金本位制を捨て、紙幣の発行にしたことではないですか。 IqDrSmvKOoさんには解りきったことでしたが。
>生産性が下がって実際の富(資本)が減少しているうえに、
J 人間の労働から離れてロボット等が生産する商品としては、確実に生産性は上がっていますよ。そのことによってインフレにならなくなっているのが現状ではないですか。
また>資本が減少している。これは株が下がったことを言っているのですかな?
もう少し続けられたらコメントを通して続けてください。できればもう少し解りやすく書いていただければ、理解できる人が多くなるはずですが。でも久しぶりに考えさせられました。
5. Monster 2010年10月30日 09:40:52: rnKrp.8thaSuQ : vObzQxM5Pc
お金は何のために造るのか。それは生産を引き出すためであると越前福井藩の三岡八郎は知っていました。
だから坂本龍馬が江戸幕府を征伐する軍資金がないといったときに、金はあると言ったのですな。
金は信用があれば造り出すことができるが、その担保は生産力である。そこで、三岡八郎は、この供給余力を引き出すために政府紙幣を発行すればいいと提案します。
坂本龍馬は頭のいい人でしたから、すぐに理解しました。
金は生産力からうまれると。
そこで、三岡八郎を西郷、大久保に強く推薦しました。
慶応三年から慶応4年(明治元年)、鳥羽伏見の戦いの軍資金から国家財政の2年間ぶんの95%を政府紙幣でまかなったのです。
だから政府紙幣がなければ明治維新はなかったと言われるのです。
現在の日本もデフレギャップが500兆円ほどありますから、それだけ発行すれば閣議だけで発行できて、1年で高度経済成長が達成できるでしょう。
06. 2010年10月30日 10:07:55: ZTceO6aYDc
Wを多用する03はこの手の話になるといつも出てくる御仁だと思われるが、自説の結論だけ言って何故そうなるかの説明がほとんどない(できない)のはいつものとおり。縄文ビト氏もお分かりのように、文章自体が支離滅裂ですから突っ込むだけ無駄です。たぶんデフレギャップの概念が理解できないのでしょう。
07. 2010年10月30日 10:14:20: K582KxQR8o
貨幣は信用のしるしでしょう。 ケインズより遥かな昔から取引の仲介として使われてきた。 金や銀が好まれたのは、何時までも光っているところが嬉しかったのでしょう。 定型化されて単位が生まれてさらに使いやすくなった。 もとが信用だから取引の規模と頻度が拡大すれば金や銀が不足する。 だから現在はただの紙ッ切れになった。 自然発生的に生まれたものだが、時の権力者が貨幣の発行権を独占している。 実際には時の権力者と裏口で取引した金融業者が紙幣発行の権利を持っているということ。 本来は物とサービスの交換のための補助的な機能だったはずの金融業が、権力と結びついて支配構造の中の重要な部分を占めるに至ったのでしょう。 取引が拡大するには貨幣も増加しなければならないが、取引が減少すれば流通通貨も減少するのは当然のこと。 通貨や信用自体が取引されるようになれば、物理的な通貨の存在は必要でなくなる。 ブッキングだけされてあれば良いのだが、取引の証拠として証券が出来てこれも通貨として勘定には加算される。 貨幣は何故市中から消えたかという設問であれば、取引の減少や価格の逓減によって流通通貨も減少するということでしょうな。 一般的には景気が悪いという状態だから流通通貨も減ってしまう。 様々な形態の資産勘定があり、一応はそれらが通貨の単位で計られているから、経済の規模を示す数値は大きくてもそれが物流に関係の無い信用取引の部分が大半であれば、流通通貨は不要であるといえるでしょう。 中央銀行なる組織が、調整と称して不要な分を引き上げているから通貨が減ってしまうというのが正解。 日本のGDPは大雑把に言えば500兆円だが、流通通貨の合計は75兆円程度の筈です。 これを増やせばインフレになり、さらに減らせばデフレがひどくなる。 多少のインフレの方にシフトしたければ消費と投資(投機ではない)を増やせば良い。 それを実現するのには権力者に対する一般の信認が必要だろうと思います。 経済は人間の心理的なファクターが大きく影響するので、権力者(総理大臣だけのことじゃなくて、社会の支配者)に対する信用が薄ければ沈滞するのでしょう。 N.T
08. 縄文ビト 2010年10月30日 10:44:10: egUyw5BLxswRI : g6DT8nixac
rnKrp.8thaSuQ : vObzQxM5Pさんコメントありがとうございました。
確かにおっしゃることは解ります。紙幣はある意味政府の信用力にかかっていると言えます 。ある意味というのは他に交換財としての貨幣に変わるものがないという意味です。それゆえになんとしても一国一通貨を守ろうとするわけです。他の通貨に対しては偽札になるわけです。
>だから政府紙幣がなければ明治維新はなかったと言われるのです。
J その時代だからできたのです。庶民が交換財として流通する貨幣が欲しかったからと、信用力があったからだと言えます。
ただそれだからといって、政府発行紙幣を増刷すれば確実に信用力のある通貨を使いたがるでしょう。そのとき信用力のない通貨は交換においてその価値を減じてしまいます。
つまり信用力のある通貨は現在の基軸通貨としてのドルに例えられます。ドルは大量に増刷した結果信用力を失い他の国の通貨に対し価値を減じてしまいました。でも交換財として変わるものが無ければやむなく使っているのが現状ではないですか。
09. 縄文ビト 2010年10月30日 11:00:27: egUyw5BLxswRI : g6DT8nixac
K582KxQR8o さんコメントありがとうございます。
>貨幣は何故市中から消えたかという設問であれば、取引の減少や価格の逓減によって流通通貨も減少するということでしょうな。
J これをこれから書こうということです。おっしゃっている意味は貨幣を通して交換の回数が減ってしまったということではないのでしょうか。
>中央銀行なる組織が、調整と称して不要な分を引き上げているから通貨が減ってしまうというのが正解。
J 問題はどのようにして引き上げるかと言うことになります。中央銀行が強権力で引き上げるわけではありませんし、銀行が抱えている通貨を理由をつけて引き上げるわけだと言えます。そのとき銀行に集まった通貨はどのようにして集めたのかと言うことになります。
ここからは私がブログで書いていくことになりますので…
まだコメントは残っています野で次回紹介いたします。










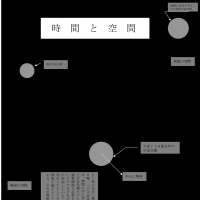
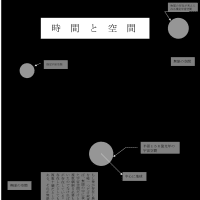



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます