>スペインは、16-17世紀、南米大陸に進出して、各地から大量の金銀を略奪し、また鉱山を開発した。これがスペインを経由してヨーロッパ各国に流入した。その量は、銀16,886トン、金181トンという。この大量の金銀の流入が、ヨーロッパの価格水準を上昇させた。これは価格革命と呼ばれている。
上記はコラムニスト原田泰氏の富とは何かの引用であるが。私も貨幣を研究しているものとして「富とは何か」の関連性があるものとして書いていきたい。
そこで価格革命の説明を簡単にしておきたい。
価格革命とは16世紀半ば以降新大陸発見に伴いアメリカ大陸から大量の銀がヨーロッパに流入し、銀価格が下落したことから、他の物価の高騰を招いたことによる。これはインフレといわれるものであるがその原因としていくつかの解説が行われている。
その中で16世紀西欧における人口急増に原因があるという論者(川北稔)の需給関係のバランスが崩れたためという見方と、貨幣量が大量に増加してしまったためという見方がある。
【原因論】(ネット上の検索)このような物価騰貴の原因については,基本的に通貨的要因を強調する意見と一般商品の需給バランスを重視する学説とがあって対立している。
そこで私の意見だが、貨幣を交換財であるとみなすことから、次に何との交換をするのかということになる。当然貨幣は商品との交換である、つまり貨幣を介して商品を買うという行為、それを貨幣と商品との交換をしていることになると考えてしまうだろう。だが買う立場の人が貨幣を持つているという前提がそこにはある。商品を買おうとする人はその貨幣(お金)をどのようにして手に入れたのか、たぶんその人は自分が働いて得た給料であるということになるだろう。
つまり私が言いたいのは貨幣は労働によって得ることのできる交換財であるということだ。相手が売る商品も当然のこと労働で作り出したものである。
物を売る、または買う行為、それは両者が貨幣を介して労働を交換していることになる。その行為が安定している状態であれば交換は1対1の労働の交換になる。だが貨幣量が多くなれば、その貨幣量に対し労働によって作られる商品が品薄となりやがては商品の価格が上がっていく。これがインフレである。その状態では不足した商品を作るために活発な経済活動となり好況を呈する。だが初期の状態では一部の人間による買占めという行為が発生し商品は上がるが労働賃金は据え置かれたものになる。
現在の経済はそこに色々な行為、買占め、売り惜しみ、やがては作りすぎた商品を売るために他国への貿易、それも行き詰れば消費側の未来の労働を担保としたローンでの販売となる。
やがて借りたローンの支払いが不能となったとき、過剰になった商品はデフレ状態をもたらす。










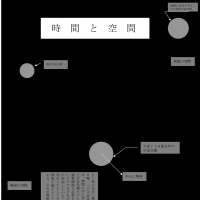
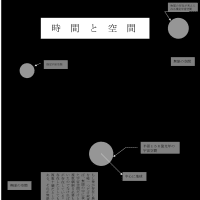



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます