ここまで書いてきて気になることは、なぜここまで事態を放置し世界的に金融危機を叫ばせなくてはならなかったこと、単なるユーロ圏の統合に問題があったということだけでは済まされないと考える。どこに原因があるのか、そしてあったのかということを考えなくてはならない。
そこで考えられることは財政赤字の元になった理由ではないかといえる。
単なるドイツ、フランスの人たちが働き者で、その他の赤字国が働き者ではないということだけで、国債を増刷し赤字になってしまったのが原因であるという風潮はもっともな理由となるのか。この先いくらユーロが変動為替相場制の中で値下がりしても問題は解決していくのだろうか。ということになる。
そこで現在叫ばれているのは今の危機を日々煽りながらも、この問題の解決は長期にわたると言われている。それまでユーロという通貨は日本円に対し値下がりをしていく。日本はますます空洞化の道を歩まなくてはならないだろう。そしてなぜかそこには、貨幣を利用したマジックを感じてしまう。
ギリシャ危機の最初の原因となった記事が朝日新聞10月10日の朝刊に載っていた。『低金利 重ねた借金』「ユーロの宴終わった」。それによると、だが記事が長いため、かいつまんで書いていきたい。
2001年ユーロ通貨が流通しはじめると便乗値上げが起きた。交換レートは1ユーロ340ドラクマと決められたのに。多くの商店は100ドラクマだったものを1ユーロで売った。物価は総じて3倍になった感じだという。「楢篠 ここでなぜ3倍にしたのかの意味がつかめない」給料が一気に3倍になるはずはない。だが物価と給与の間を生めるものがあらわれた。
低利のローンだ。インフレに苦しんだドラクマのころと違い、大国ドイツの後ろ盾があるユーロには信用があった。中略 ベンツやB M Wのディーラーが大通りに並んだ。家電店には最新の輸入品が現れた。ユーロ建てのローンで借りた国民は手が届かなかった輸入品をこぞって買い揃えた。中略 銀行も貸した。フランスのB N P パリバ、スペインのサンタンデール。スイスのU B S。大手銀がギリシャの顧客を奪いあった。融資の審査も甘めだった。
ユーロの信用で、政府も低利で国債を発行して借金ができた。欧州連合(E U)からの補助金を元手にした公共事業が経済を押し上げた。高速道路が延び、空港は新しくなった。五輪の競技場が次々に建った。宴の陰で、国の財政も家計も借金が膨らんでいった。(以上は新聞記事より引用)
これはまさにリーマンと同じではないかと考える。両者に問題となるのはお互いに自国(ユーロ圏ではユーロ)の通貨(紙幣)をいかに多く流通させるかという命題がある。このためには手段を選ばない。
リーマン問題以前のアメリカでは機軸通貨(貿易決済)としてのドルを世界に渡さなくてはならない。紙幣は印刷機さえ回せばいくらでも刷れる。ただ流通させるには至難の業になる。多くの人(ここでは輸出入業者、もしくは国)に持ってもらうには紙切れといえども通貨である、物が買えることができる。多くの紙幣を流通させるためとはいえ「タダ」でやる訳にはいかない。ここで二つの方法がある、一つは相手から物を買う方法、リーマンの場合は中国・日本・世界中から物を買うことによって世界中にドル札を持ってもらうことができた。ただ世界から物を買うだけではそのはけ口が必要となる、そこでアメリカでは低利、もしくは低所得者にも審査を緩め、貸付をし住宅を建てさせることにした。やがて住宅バブルの発生となる。ここでは最初の出だしはいかに多くの紙幣を流通させるかということが重要な点となる。結果としてのバブル発生は織り込み済みといえるのではないか。
最初の流通通貨が100とすれば200を流通させるには印刷した通貨を如何に流通させるか、ここに通貨発行益(シニョリッジ)が発生する。王権時代は王が印刷した紙幣で王自身の物を購入した。現代ではその通貨発行益が誰のものになっているのかを今後書いていきたい。
そこで考えられることは財政赤字の元になった理由ではないかといえる。
単なるドイツ、フランスの人たちが働き者で、その他の赤字国が働き者ではないということだけで、国債を増刷し赤字になってしまったのが原因であるという風潮はもっともな理由となるのか。この先いくらユーロが変動為替相場制の中で値下がりしても問題は解決していくのだろうか。ということになる。
そこで現在叫ばれているのは今の危機を日々煽りながらも、この問題の解決は長期にわたると言われている。それまでユーロという通貨は日本円に対し値下がりをしていく。日本はますます空洞化の道を歩まなくてはならないだろう。そしてなぜかそこには、貨幣を利用したマジックを感じてしまう。
ギリシャ危機の最初の原因となった記事が朝日新聞10月10日の朝刊に載っていた。『低金利 重ねた借金』「ユーロの宴終わった」。それによると、だが記事が長いため、かいつまんで書いていきたい。
2001年ユーロ通貨が流通しはじめると便乗値上げが起きた。交換レートは1ユーロ340ドラクマと決められたのに。多くの商店は100ドラクマだったものを1ユーロで売った。物価は総じて3倍になった感じだという。「楢篠 ここでなぜ3倍にしたのかの意味がつかめない」給料が一気に3倍になるはずはない。だが物価と給与の間を生めるものがあらわれた。
低利のローンだ。インフレに苦しんだドラクマのころと違い、大国ドイツの後ろ盾があるユーロには信用があった。中略 ベンツやB M Wのディーラーが大通りに並んだ。家電店には最新の輸入品が現れた。ユーロ建てのローンで借りた国民は手が届かなかった輸入品をこぞって買い揃えた。中略 銀行も貸した。フランスのB N P パリバ、スペインのサンタンデール。スイスのU B S。大手銀がギリシャの顧客を奪いあった。融資の審査も甘めだった。
ユーロの信用で、政府も低利で国債を発行して借金ができた。欧州連合(E U)からの補助金を元手にした公共事業が経済を押し上げた。高速道路が延び、空港は新しくなった。五輪の競技場が次々に建った。宴の陰で、国の財政も家計も借金が膨らんでいった。(以上は新聞記事より引用)
これはまさにリーマンと同じではないかと考える。両者に問題となるのはお互いに自国(ユーロ圏ではユーロ)の通貨(紙幣)をいかに多く流通させるかという命題がある。このためには手段を選ばない。
リーマン問題以前のアメリカでは機軸通貨(貿易決済)としてのドルを世界に渡さなくてはならない。紙幣は印刷機さえ回せばいくらでも刷れる。ただ流通させるには至難の業になる。多くの人(ここでは輸出入業者、もしくは国)に持ってもらうには紙切れといえども通貨である、物が買えることができる。多くの紙幣を流通させるためとはいえ「タダ」でやる訳にはいかない。ここで二つの方法がある、一つは相手から物を買う方法、リーマンの場合は中国・日本・世界中から物を買うことによって世界中にドル札を持ってもらうことができた。ただ世界から物を買うだけではそのはけ口が必要となる、そこでアメリカでは低利、もしくは低所得者にも審査を緩め、貸付をし住宅を建てさせることにした。やがて住宅バブルの発生となる。ここでは最初の出だしはいかに多くの紙幣を流通させるかということが重要な点となる。結果としてのバブル発生は織り込み済みといえるのではないか。
最初の流通通貨が100とすれば200を流通させるには印刷した通貨を如何に流通させるか、ここに通貨発行益(シニョリッジ)が発生する。王権時代は王が印刷した紙幣で王自身の物を購入した。現代ではその通貨発行益が誰のものになっているのかを今後書いていきたい。










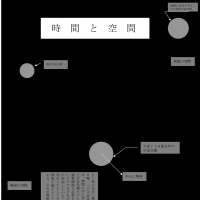
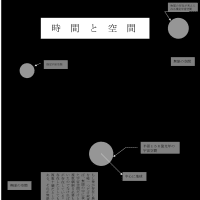



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます