こっきです。
ご無沙汰しております。
今、FBのほうで「富根報徳番楽を支える人々。」と一週間くらい前から更新しているのですが、ある方からとてもうれしいお言葉を頂きましたので、パソコンに向かった次第です。
ここからは私の言葉ではなくその方の文面です。
全国的に名前は知られずとも、郷土芸能(秋田では番楽といいます)を、地道に続けておられる方がいます。
生まれた時からその地に住み、風土を感じながら、番楽と共に歩み、生きた芸能を継承している方々です。
こういった方々には、上方で「能」の一流とされる人にはない魅力や、日本で有名とされている(下手な)芸能人とは全く違う力があると感じます。
以前、私は五城目の中村集落にあるガンバ句を取材したことがありました。
その当時で一番歌を知っていて、一番踊ることができた男性は、足を痛めてからはそれを継承すること叶わず。ほんの3年前のことです。
その男性は「もともと地域外には門外不出だったんだが、このままでは廃れてしまう。地域外の人でも、興味を持たれた方には教えたいと思いはある」
と、悲しそうな表情で話されていました。
私は、その時やってみたいと申し出たのですが、女性では不可ということで、とても残念な気持ちになりました。
今は、五城目は「山内番楽」の子どもたちによる「内川ささら」だけと聞いています。
せめて、それらを地道に継承していく人々が、人間国宝とまではいかなくても、文化功労賞の対象になれば、名前が知れて、継承しようと地域に帰ってくる人や興味があって話を聞きに来る若者がいるかもしれないと思ったりもしましたが、そういう「側」の評価や賞賛、「有名になること」は、もしかしたらこの方々には全く興味ないことなのかもしれません。
無名であるが故、後を継がなければいけないと苦悩する「能」役者のようなプレッシャーを感じることなく、常に身近であり、自然体で、自身の生と共にあることが、更に魅力的な舞台をつくりあげてきたのでしょうから・・・・。
とはいえ、地域外の人間がどんなに「勿体ない」と言っても、そこに住む地域の人々が必要なければ、自然に消えてしまうのが郷土芸能です。
地域外の人間では、本来の意味で入り込めない「仕方のないこと」です。
「単なる郷土芸能ごとき」、「古い芸能」、面倒くさい近所づきあい」。
そうやって、故郷を去って方々の中にも、少しでも思い出としてもらいたい景色があります。自分が何を捨てて、何を選んで今の地に住んでいるのか。
それらを、望んでも、手に入れることのできない人間にとっては、少し羨ましいと思ってしまうのは、無いものねだりなんでしょうけど。
技は、鍛錬の賜物です。
寝食をするように生活の一部として舞ってきた者だけが習得できるもの。
番楽が体に染みついた技というものは、競いようがない。
けれど、彼らの想いを継承していこうと頑張っている若者が、能代にはいます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここからは、これを読んで私の率直な感想を少しお話したいと思います。
おそらく私個人の感想ではなく、会のみんなが共感してくれると思いますが、継承とかあまり考えていません。
番楽は楽しいことをする(酒を飲む)口実であって、大義名分に隠れておいしい酒が飲みたいそれが本心です。
なんで、関係なくBBQなんかもやりますし、師匠と弟子の関係は存在すらしていますが、「仲間」としてのとらえ方が我々番楽には正しい言葉だと感じています。
「みんなで楽しくやろう~」
これは、9月に神社で行われる「作番楽」に見に来ていただければ、感じていただけると思っています。
是非一度、いらしてください。
ご無沙汰しております。
今、FBのほうで「富根報徳番楽を支える人々。」と一週間くらい前から更新しているのですが、ある方からとてもうれしいお言葉を頂きましたので、パソコンに向かった次第です。
ここからは私の言葉ではなくその方の文面です。
全国的に名前は知られずとも、郷土芸能(秋田では番楽といいます)を、地道に続けておられる方がいます。
生まれた時からその地に住み、風土を感じながら、番楽と共に歩み、生きた芸能を継承している方々です。
こういった方々には、上方で「能」の一流とされる人にはない魅力や、日本で有名とされている(下手な)芸能人とは全く違う力があると感じます。
以前、私は五城目の中村集落にあるガンバ句を取材したことがありました。
その当時で一番歌を知っていて、一番踊ることができた男性は、足を痛めてからはそれを継承すること叶わず。ほんの3年前のことです。
その男性は「もともと地域外には門外不出だったんだが、このままでは廃れてしまう。地域外の人でも、興味を持たれた方には教えたいと思いはある」
と、悲しそうな表情で話されていました。
私は、その時やってみたいと申し出たのですが、女性では不可ということで、とても残念な気持ちになりました。
今は、五城目は「山内番楽」の子どもたちによる「内川ささら」だけと聞いています。
せめて、それらを地道に継承していく人々が、人間国宝とまではいかなくても、文化功労賞の対象になれば、名前が知れて、継承しようと地域に帰ってくる人や興味があって話を聞きに来る若者がいるかもしれないと思ったりもしましたが、そういう「側」の評価や賞賛、「有名になること」は、もしかしたらこの方々には全く興味ないことなのかもしれません。
無名であるが故、後を継がなければいけないと苦悩する「能」役者のようなプレッシャーを感じることなく、常に身近であり、自然体で、自身の生と共にあることが、更に魅力的な舞台をつくりあげてきたのでしょうから・・・・。
とはいえ、地域外の人間がどんなに「勿体ない」と言っても、そこに住む地域の人々が必要なければ、自然に消えてしまうのが郷土芸能です。
地域外の人間では、本来の意味で入り込めない「仕方のないこと」です。
「単なる郷土芸能ごとき」、「古い芸能」、面倒くさい近所づきあい」。
そうやって、故郷を去って方々の中にも、少しでも思い出としてもらいたい景色があります。自分が何を捨てて、何を選んで今の地に住んでいるのか。
それらを、望んでも、手に入れることのできない人間にとっては、少し羨ましいと思ってしまうのは、無いものねだりなんでしょうけど。
技は、鍛錬の賜物です。
寝食をするように生活の一部として舞ってきた者だけが習得できるもの。
番楽が体に染みついた技というものは、競いようがない。
けれど、彼らの想いを継承していこうと頑張っている若者が、能代にはいます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここからは、これを読んで私の率直な感想を少しお話したいと思います。
おそらく私個人の感想ではなく、会のみんなが共感してくれると思いますが、継承とかあまり考えていません。
番楽は楽しいことをする(酒を飲む)口実であって、大義名分に隠れておいしい酒が飲みたいそれが本心です。
なんで、関係なくBBQなんかもやりますし、師匠と弟子の関係は存在すらしていますが、「仲間」としてのとらえ方が我々番楽には正しい言葉だと感じています。
「みんなで楽しくやろう~」
これは、9月に神社で行われる「作番楽」に見に来ていただければ、感じていただけると思っています。
是非一度、いらしてください。














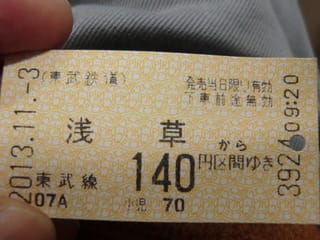



 予想はしていましたが
予想はしていましたが




