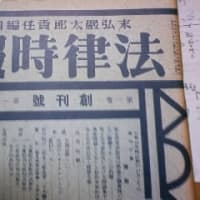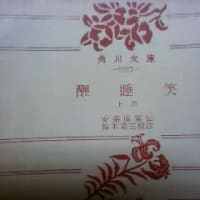「売買は賃貸借を破る」(Kauf bricht Miete)。土地の賃貸借で、賃貸人である土地所有者Aが第三者Cにその土地を譲渡した場合、賃借人Bが有する賃借権は旧所有者Aに対する相対的な債権的な権利ですから、新所有者Cに対して賃借権を主張することはできません。したがって、賃借人Bが建物を建てて住んでいる場合にも、新所有者Cからの建物収去・土地明け渡し請求に応じなければならないわけです。
ちなみに、 「売買は賃貸借を破る」の原則は、所有権絶対の原則を根拠にするものです。
もっとも、登記した不動産賃借権には対抗力が認められてはいる(民法605条)のですが、賃借人には賃貸人に対する登記請求権は認められていませんから(逆にいうと、賃貸人には登記義務などないのです)、賃貸人が好意的に登記してくれない限り、民法605条の出番はないのです。
こういう状況が「地震売買」を生んできたわけです。地震売買。耐震構造を偽装したマンション売買の話ではありません。(とうとう小嶋社長が詐欺容疑で逮捕されましたね)
かつて、日露戦争(1904年/ひとつくれよう、ロシアにげんこつ)後の地価高騰の際、地代値上げのために、賃貸土地の仮装売買が盛んに行われたようです。単に地代の値上げを要求しても、賃借人が承諾してくれませんから。これがいわゆる「地震売買」。賃借人は新所有者に対して土地を明け渡すか、地代の値上げを承諾せざるを得ない状況に陥ったわけです。
このような売買は、地震と同じように借地上の建物の存在を危うくすることから、「地震売買」などとよばれたわけです。
このような弊害をなくすために、1909年に「建物保護ニ関スル法律」、いわゆる建物保護法が制定されました。借地人が借地上に登記した建物を有するときには、第三者に借地権を対抗できるようになったわけです。
この趣旨が現在では、1991年に制定された借地借家法に引き継がれているわけです(借地借家法10条、31条)。判例によれば、「登記」は所有権登記(いわゆる「権利の登記」)でなくても、 「表示の登記」でもよい(最判昭50.2.13)とされている点は評価できますが、その登記は家族名義では対抗力がない(最判昭41.4.27)とする点では借地人の保護としては不十分ですね(だって、不動産取引は登記簿中心主義・現地検分主義ですからね)。
このように現在では、特別法によって「売買は賃貸借を破らない」場合が認められているわけです(所有権絶対の原則の修正)。
では、ここで問題です。考えてみましょうね。
借地人が借地上に建物を所有しているが、借地権の登記も建物の登記も有しない場合、要するに借地権の対抗力がない場合には、借地人は悪意の新所有者の建物収去・土地明け渡し請求に応じなければならないのでしょうか。(文中にヒントがあります)