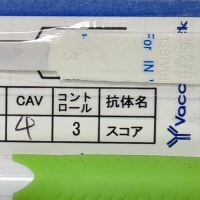私に限ったことではなく、日々の仕事で頻繁に使用する道具…仕事じゃなくても、「使い勝手」が良いものに自然となっていることが多いと思います。
今回は、耳の処置をする際の「綿棒」。
私は、耳の処置(外耳道洗浄)は日々行う処置だからこそ、非常に気をつけることと、洗浄するのであればどうやって最大の効果が得られるかが治療の肝だと昔から考えています。
開業する以前、私は関東のいくつかの動物病院を転々としていました。決して仕事ができる人材ではなく、どちらかというといわゆるポンコツという扱いでした。
最初の職場は、外耳道洗浄の際、鉗子を使いなさいと言われました。

「モスキート鉗子」
その当時はそれで覚えようとしていました。
短い期間で退職し、次の職場では…
「耳に道具を入れるな。事故が起こる。洗浄液だけ入れて洗浄せよ。」
ということで、そうしていました。
3つめの職場。
獣医師が何人かいましたが、それぞれがめいめい好きな方法でやっていました。
4つめの職場。
この綿棒を使いなさい。ただ、耳垢を奥に押し込んだら取れなくなるから気をつけて、あとは状態を見て処置しなさい。

「ルーツェ式棬綿子」
このような経験があり、動物病院の世界では、前の職場で教わったことが別の職場ではNGということもあることを学びました。
となると。
結論としては、当たり前ですが「耳に合わせて最適を考える」のが一番だろうと思います。
小型犬の細い耳では耳垢溶解液で耳垢を溶かしたあとルーツェ式で除去して洗浄液が良いですし、大型犬の大きく深い耳では耳垢溶解液、洗浄液を入れてジャブジャブ洗えます。奥に残る場合はルーツェ式で除去することもあります。
腫れて出血している耳では刺激性のない洗浄液を用い綿棒入れずに済ませますし、猫だと洗浄液を入れるのを極端に嫌がることが多いので、液を耳に入れずにちょっと浸けただけのルーツェ式やモスキート鉗子のほうが処置しやすいこともあります。
動物の性格や状態によっては、洗浄せずに点耳薬を入れて、飲み薬を開始して腫れや痛みが引いてからじっくり処置、ということもあります。
手数、手段は多いに越したことはないので、ポンコツなりにいろいろな病院を見た結果得られたものもあったとは思います。
その、耳の処置で使いなれてて大事な道具「ルーツェ式」が最近生産終了してしまったということで…慌てて探しました。
開業16年で、折れたりとかで○○本廃棄したので、△△本あればあとXX年は持つかな、といった本数を購入。
いわゆる普通の綿棒は自分の感触では硬いので、耳垢採取には使いますが、洗浄処置では使いにくいんですよね。もちろん使ってる先生も多いと思うので、いわゆる「好み」の範囲です。
ということで、またひとつ、使い慣れた道具が生産終了したので、これからも使うために確保したのと、
これから、もっと使い勝手の良い道具が出てきたら良いな、と淡い期待を持ったのでした。
高知 きたむら動物病院
犬と猫の一般診療・内科・皮膚科・内分泌・理学療法
高知県高知市北川添24-27 088-880-5123
休診日 水曜日 日曜日 祝日
受付時間
月・火・木・金・土
9:00-12:00 14:30-17:45